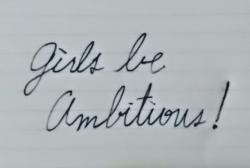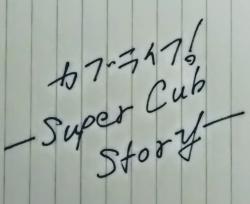金曜日の夜。
るなは自宅でテレビをつけた。
年末の音楽番組を放送していたらしく、るなはボンヤリ眺めるように見ていた。
「さて、札幌から生中継です!」
画面が切り替わると、小雪の舞う大通公園が映った。
「次は、ライラック女学院アイドル部のみなさんです!」
アナウンサーに紹介されてメンバーが映った。
「はーいみなさーん、北海道が生んだスクールアイドル、ライラック女学院アイドル部でーす!」
決め台詞とともに、英美里が笑顔いっぱいに反応する。
「今日はですね、大切な話がありまして…」
英美里はひと呼吸おいてから、
「実はメンバーの花島るなちゃんが体調不良でいないんですけど、今日はるなちゃんに生電話したいと思います!」
るなはキョトンとした。