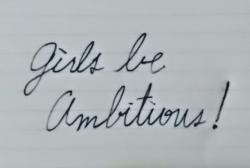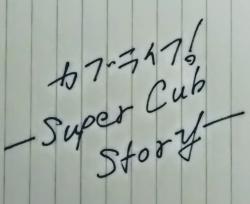事実、昨年のリラ祭の人気投票の際には、二日目まで圏外だった優子が三日目のトークイベントで広島弁のトークを繰り出した途端、ジャンプアップの六位に上昇し、小さいながらも個別のファンサイトまで出来ていた。
「うちらはアイドル部って看板だけど、中身はエンターテイメントだけじゃない。藤子みたいに作家になったって、雪穂みたいに女優になっても別に誰もなんにも言わない」
コーチでもある草創期の元メンバー・乾美波に言わせるとそんな感じである。
だからだりあのように落語をやっても、みな穂たちのようにコントをしても有り得るのが、アイドル部の強みでもあり個性でもある。
「正統派ではない、邪道だ」
という声もなくはない。
それでも、
「昔SMAPやAKBがやっていたようなことをやっていて批難されるのは、一種の選り好みで差別みたいなもんだよね」
という当時の雪穂砲をラジオで炸裂させると、途端に非難は激減した。
そうしたキャラクターの強い三年生──優海、すみれ、雪穂、千波である──がいた時代の新加入メンバーが紺野ひまりと花島るなで、そこに優子と英美里、さらに竹実香織の五人がいる。
この内ひまりとるな、香織は地元組で、英美里は函館、優子は道外からの初加入メンバーであった。
その中で新しくボーカルに加わったのは、子役時代にミュージカルに出た経験のあるひまりと、ギャル姿でガールズバンドを組んでいた時期のあったるなである。
更にその後、みな穂が二度目のくじ引きで部長を再び引き当て、三年生になったときに入ってきたのがだりあとひかる、そして鶴岡さくら、藤浦薫、龍造寺翔子の計五人であった。