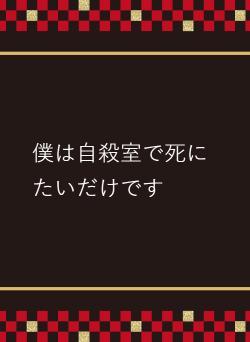・
・【教室に戻ると】
・
僕とノエルちゃんが教室に戻ってくるなり、紗英が近付いてきて、こう言った。
「言いたいことは分かるが、全員が全員そうではない! 何故なら俺には俺という個性があるから!」
力強くそう言い放ちつつ、ノエルちゃんのことを若干睨んでいる様に見えた紗英に、僕は少し背筋が凍った。
いやでも確かにその紗英の言っていることが僕はよく分かる。
紗英はそういう”型でハメていく言動”というモノが好きではないから。
それに対してノエルちゃんは余裕そうに、前髪をかきあげながら、こう言った。
「まあまあ、のちのち分かりますよっ」
と鼻をツーンと上げ、やけに自信あり気で一体何なんだろうと僕は思ってしまった。
仲良く個性を尊重すればいいのに。
ノエルちゃんはそう言うと、さっさと自分の席に戻って座った。
僕はなんだかモヤモヤしてしまった。
本当にノエルちゃんのことを助けてしまって良かったのだろうか、と、さえ、思ってしまった。
そのタイミングでチャイムが鳴った。
「じゃっ、また四限目前の休みに」
そう僕には笑顔で言った紗英。
そして僕も紗英も自分の席に着いた。
しかし三限目の授業はなかなか頭に入ってこなかった。
ずっとモヤモヤしていたから。
四限目前の休み時間に僕はすぐに紗英の席へ行った。
「ん? そんなに急いで何? 何か用?」
その時、僕は何も言葉を決めていないのに、ただただ紗英の近くに行ってしまったことに気付いた。
何も言葉が出ずに、うんうん唸っていると、紗英は立ち上がって、僕の肩を叩きながら、
「大丈夫、大丈夫、昔に戻っただけ。またいちからノエルに説明していけばいいだけだからさっ」
と、ちょっと困った笑顔を浮かべながらそう言った。
昔、か。
そうだ、昔は皆、紗英のこの感じにまだ慣れていなくて、ちょっと除け者扱いみたいにしていた人もいたなぁ。
でも紗英は紗英で。ずっと紗英は紗英で。
結果、この学校の人全員、紗英のこの感じに慣れたのだ。
一人称が”俺”のことだって、もう注意する先生すらいない。
そうか、だからノエルちゃんも慣れればいいんだ、紗英に。
早く慣れてくれるといいな。
四限目の授業も終わり、給食。
「ちょっとぉ! そこの君ぃ! もっとアタシのご飯! もっと盛ってよぉ!」
ノエルちゃんがまた自分の給食の盛りに注文をつけている。
言われた給食当番のマサルは、困りながら、
「余ったらあとで自分で盛ればいいだろ!」
と言っている。
それに対してノエルちゃんは、
「どうせ余るんだから今から多めに入れてよ! ケチぃっ!」
と引かない。
本当にノエルちゃんは引かないなぁ。
まるでそう決めているみたいだ。
それくらい頑固に引かないような気がする。
僕は給食当番をしている紗英の分も配膳するため、二回列に並ぶと、その二回目で、ノエルちゃんが自分の席に座りながら、
「あっ! 給食二個分食べようとしてる! ズルい! ズルい!」
と言ってきたので、ここは冷静に説明しようと、
「これは今、給食当番をしている紗英の分だよ」
と、出来る限り落ち着いた声で言うと、
「うぅ~! それくらい知ってる!」
と言って、自分の席に既に置いている給食を荒くどかしてから、机に突っ伏した。
給食の時、机は前・左右をみんなの机と合わせているので、配膳された給食が落ちることはないけども、他の人の給食と当たって、少しこぼれそうになっていた。
何か怖いなぁ、と思っていると、スープの配膳を担当していた紗英が、
「二回目の配膳だと分かるって、ノエル、誠一のことをよく見ているんじゃないか?」
と小声で言ってきたので、何でだろうと思った。
う~ん、いくら考えても理由は分からない。
そんなことより、紗英の配膳を済まして、自分の席について、給食当番も全て終わって『いただきます』と、なった。
近くのクラスメイトと、やけにデカくと妙に赤色のバッタの話をしながらご飯を食べていると、何だか視線を感じて、チラっとそっちを見ると、僕からの目線をそらすノエルちゃんの姿があった。
確かに紗英が言っていた通り、ノエルちゃんが僕のことを見ているような、何でだろう……と思う暇も無く、隣の席のタクマくんが、
「あのバッタ、多分山の主だぜ?」
と言ってきて、
「さすがに山の主、バッタじゃなくて熊クラスのデカさでしょ」
とツッコんだけども、さらにタクマくんは、
「だってあの山、やけにバッタ多いじゃん、バッタ製造工場でもあればあれだけどさ」
という怒涛の謎のボケ発言を喰らってしまい、考える隙が無かった。
ノエルちゃんがやけに僕のことを見ていたことを思い出したのは、帰りのホームルームが終わった直後だった。
一応またスベリヒユの採取でもしようかなと思った時に、思い出した。
そうだ、このスベリヒユってノエルちゃんのためだ、と思った時に。
そのタイミングで誰かに後ろから話し掛けられた。
「あの、誠一、ちょっといいかな?」
紗英よりは高い声で、少し可愛らしいこの声は。
振り返ると、そこにはノエルちゃんが立っていた。
「またスベリヒユの料理、作ってほしいんだけどもっ」
何だか妙にモジモジしながら言っていたことが印象的だった。
二限目と三限目の間の長休みでは、全然そんな感じじゃなかったのに。
でもまあ良かったは良かった。
だってスベリヒユ採取したほうがいいか分からなかったから。
「じゃあやっぱり今後、ずっとスベリヒユの料理作ったほうがいいかな?」
「うん、お願いっ」
とちょっとした会話をしたタイミングで、座っている僕の頭に何か置かれて、その真上から声がした。
「じゃ! 俺も手伝うから!」
紗英だ。
紗英が僕の頭の上に、アゴを置いているらしい。
逆にというかなんというか、体勢つらくないかな。
僕は頭をクイクイ動かして、紗英の頭をどかしたら、その場に立ち上がり、紗英やノエルちゃんのほうをそれぞれ目配せしながら、僕は
「紗英も、ノエルちゃんが食べるスベリヒユを採取しているんだ。だからノエルちゃんも紗英と仲良くしてほしいんだ」
と言うと、紗英がちょっと嫌な顔をしながら、
「いや別にそんなこと言わなくてもいいし! 俺は誠一と一緒にいたいだけだし!」
と言うと、ノエルちゃんが、
「やっぱり好きなんじゃなぁ~い」
とまたクスクス笑いながら、ツインテールを揺らしながら、そう言った。
さっきのモジモジとは打って変わって、また性格が悪い感じだ。
それでまたカチンときたみたいで、紗英は
「好きは好きだよ! 誠一のこと好きだから一緒にいるんだよ! だけどな! 付き合いたいとかそういうことじゃないんだよ!」
と声を張り上げながら言うと、ノエルちゃんはそんなことありえないでしょ、みたいな顔をしながら、
「恋としても好きなくせにさぁ!」
と言って笑った。
何かこのまま二人で言い合いをさせたら良くないと思って、僕はランドセルに机の中の道具を詰めて、すぐさま立ち上がり、
「じゃ! じゃあ紗英! またスベリヒユ採取に行こう!」
と紗英の腕を引っ張りながら、歩き出した。
すると、紗英もそれに合わせて、僕と一緒に教室の外に出た。
教室の外に出るなり、紗英が
「何であんなムカつくことばかり言うんだろ! 本当に嫌になる!」
と本気で怒っていた。
いやまあ紗英の気持ちはよく分かるけども。
ノエルちゃんも恩とか感じて、仲良くしてくれればいいのになぁ。
・【教室に戻ると】
・
僕とノエルちゃんが教室に戻ってくるなり、紗英が近付いてきて、こう言った。
「言いたいことは分かるが、全員が全員そうではない! 何故なら俺には俺という個性があるから!」
力強くそう言い放ちつつ、ノエルちゃんのことを若干睨んでいる様に見えた紗英に、僕は少し背筋が凍った。
いやでも確かにその紗英の言っていることが僕はよく分かる。
紗英はそういう”型でハメていく言動”というモノが好きではないから。
それに対してノエルちゃんは余裕そうに、前髪をかきあげながら、こう言った。
「まあまあ、のちのち分かりますよっ」
と鼻をツーンと上げ、やけに自信あり気で一体何なんだろうと僕は思ってしまった。
仲良く個性を尊重すればいいのに。
ノエルちゃんはそう言うと、さっさと自分の席に戻って座った。
僕はなんだかモヤモヤしてしまった。
本当にノエルちゃんのことを助けてしまって良かったのだろうか、と、さえ、思ってしまった。
そのタイミングでチャイムが鳴った。
「じゃっ、また四限目前の休みに」
そう僕には笑顔で言った紗英。
そして僕も紗英も自分の席に着いた。
しかし三限目の授業はなかなか頭に入ってこなかった。
ずっとモヤモヤしていたから。
四限目前の休み時間に僕はすぐに紗英の席へ行った。
「ん? そんなに急いで何? 何か用?」
その時、僕は何も言葉を決めていないのに、ただただ紗英の近くに行ってしまったことに気付いた。
何も言葉が出ずに、うんうん唸っていると、紗英は立ち上がって、僕の肩を叩きながら、
「大丈夫、大丈夫、昔に戻っただけ。またいちからノエルに説明していけばいいだけだからさっ」
と、ちょっと困った笑顔を浮かべながらそう言った。
昔、か。
そうだ、昔は皆、紗英のこの感じにまだ慣れていなくて、ちょっと除け者扱いみたいにしていた人もいたなぁ。
でも紗英は紗英で。ずっと紗英は紗英で。
結果、この学校の人全員、紗英のこの感じに慣れたのだ。
一人称が”俺”のことだって、もう注意する先生すらいない。
そうか、だからノエルちゃんも慣れればいいんだ、紗英に。
早く慣れてくれるといいな。
四限目の授業も終わり、給食。
「ちょっとぉ! そこの君ぃ! もっとアタシのご飯! もっと盛ってよぉ!」
ノエルちゃんがまた自分の給食の盛りに注文をつけている。
言われた給食当番のマサルは、困りながら、
「余ったらあとで自分で盛ればいいだろ!」
と言っている。
それに対してノエルちゃんは、
「どうせ余るんだから今から多めに入れてよ! ケチぃっ!」
と引かない。
本当にノエルちゃんは引かないなぁ。
まるでそう決めているみたいだ。
それくらい頑固に引かないような気がする。
僕は給食当番をしている紗英の分も配膳するため、二回列に並ぶと、その二回目で、ノエルちゃんが自分の席に座りながら、
「あっ! 給食二個分食べようとしてる! ズルい! ズルい!」
と言ってきたので、ここは冷静に説明しようと、
「これは今、給食当番をしている紗英の分だよ」
と、出来る限り落ち着いた声で言うと、
「うぅ~! それくらい知ってる!」
と言って、自分の席に既に置いている給食を荒くどかしてから、机に突っ伏した。
給食の時、机は前・左右をみんなの机と合わせているので、配膳された給食が落ちることはないけども、他の人の給食と当たって、少しこぼれそうになっていた。
何か怖いなぁ、と思っていると、スープの配膳を担当していた紗英が、
「二回目の配膳だと分かるって、ノエル、誠一のことをよく見ているんじゃないか?」
と小声で言ってきたので、何でだろうと思った。
う~ん、いくら考えても理由は分からない。
そんなことより、紗英の配膳を済まして、自分の席について、給食当番も全て終わって『いただきます』と、なった。
近くのクラスメイトと、やけにデカくと妙に赤色のバッタの話をしながらご飯を食べていると、何だか視線を感じて、チラっとそっちを見ると、僕からの目線をそらすノエルちゃんの姿があった。
確かに紗英が言っていた通り、ノエルちゃんが僕のことを見ているような、何でだろう……と思う暇も無く、隣の席のタクマくんが、
「あのバッタ、多分山の主だぜ?」
と言ってきて、
「さすがに山の主、バッタじゃなくて熊クラスのデカさでしょ」
とツッコんだけども、さらにタクマくんは、
「だってあの山、やけにバッタ多いじゃん、バッタ製造工場でもあればあれだけどさ」
という怒涛の謎のボケ発言を喰らってしまい、考える隙が無かった。
ノエルちゃんがやけに僕のことを見ていたことを思い出したのは、帰りのホームルームが終わった直後だった。
一応またスベリヒユの採取でもしようかなと思った時に、思い出した。
そうだ、このスベリヒユってノエルちゃんのためだ、と思った時に。
そのタイミングで誰かに後ろから話し掛けられた。
「あの、誠一、ちょっといいかな?」
紗英よりは高い声で、少し可愛らしいこの声は。
振り返ると、そこにはノエルちゃんが立っていた。
「またスベリヒユの料理、作ってほしいんだけどもっ」
何だか妙にモジモジしながら言っていたことが印象的だった。
二限目と三限目の間の長休みでは、全然そんな感じじゃなかったのに。
でもまあ良かったは良かった。
だってスベリヒユ採取したほうがいいか分からなかったから。
「じゃあやっぱり今後、ずっとスベリヒユの料理作ったほうがいいかな?」
「うん、お願いっ」
とちょっとした会話をしたタイミングで、座っている僕の頭に何か置かれて、その真上から声がした。
「じゃ! 俺も手伝うから!」
紗英だ。
紗英が僕の頭の上に、アゴを置いているらしい。
逆にというかなんというか、体勢つらくないかな。
僕は頭をクイクイ動かして、紗英の頭をどかしたら、その場に立ち上がり、紗英やノエルちゃんのほうをそれぞれ目配せしながら、僕は
「紗英も、ノエルちゃんが食べるスベリヒユを採取しているんだ。だからノエルちゃんも紗英と仲良くしてほしいんだ」
と言うと、紗英がちょっと嫌な顔をしながら、
「いや別にそんなこと言わなくてもいいし! 俺は誠一と一緒にいたいだけだし!」
と言うと、ノエルちゃんが、
「やっぱり好きなんじゃなぁ~い」
とまたクスクス笑いながら、ツインテールを揺らしながら、そう言った。
さっきのモジモジとは打って変わって、また性格が悪い感じだ。
それでまたカチンときたみたいで、紗英は
「好きは好きだよ! 誠一のこと好きだから一緒にいるんだよ! だけどな! 付き合いたいとかそういうことじゃないんだよ!」
と声を張り上げながら言うと、ノエルちゃんはそんなことありえないでしょ、みたいな顔をしながら、
「恋としても好きなくせにさぁ!」
と言って笑った。
何かこのまま二人で言い合いをさせたら良くないと思って、僕はランドセルに机の中の道具を詰めて、すぐさま立ち上がり、
「じゃ! じゃあ紗英! またスベリヒユ採取に行こう!」
と紗英の腕を引っ張りながら、歩き出した。
すると、紗英もそれに合わせて、僕と一緒に教室の外に出た。
教室の外に出るなり、紗英が
「何であんなムカつくことばかり言うんだろ! 本当に嫌になる!」
と本気で怒っていた。
いやまあ紗英の気持ちはよく分かるけども。
ノエルちゃんも恩とか感じて、仲良くしてくれればいいのになぁ。
・
・【ある日のこと】
・
そんなこんなで、毎日校庭にあるスベリヒユを採取しては、二限目と三限目の長めの休み時間にノエルちゃんへ料理を作っていた時だった。
今日、学校にやって来たノエルちゃんはあからさまに調子が悪そうで、席に着くとすぐに胃のあたりをさすっては、うんうんと唸っていた。
その時、僕と紗英は朝の下処理を早めに終えて、もう教室に戻ってきていたので、僕は僕の席に、紗英はその隣の席に座って、何気ない会話をしていた。
でもその、やけにデカくて妙に赤いバッタの話は止めて、ノエルちゃんの話を始めた。
「何か最近、ノエル、ずっと胃のあたりさすっていない? 特に今日、酷そうだし……」
心配そうにそう言った紗英。
確かに僕も1週間前からその傾向を感じていた。
でもお腹はすいているし、食べたいと言っていたので、いつも通りスベリヒユ料理を振る舞っていたのだけども。
どうすればいいんだろうと考えていると、紗英が立ち上がり、
「誠一! 直接聞きに行くよ!」
と言ったので、僕も立ち上がり、ノエルちゃんの席へ行った。
ノエルちゃんは明らかに具合が悪そうにしていたので、僕は困りながら
「ちょっと、ノエルちゃん大丈夫? 具合が悪いなら今日は休んだほうがいいよっ」
と言うと、ノエルちゃんは僕を見るなり、少しモジモジしながら、
「アタシのこと見てたんだ、もぅ……」
と微笑みながら、そう言ったので、
「いやたいした返答になっていないよ、ほら、保健室に連れていこうか?」
と返した。
ノエルちゃんは初めてスベリヒユ料理を振る舞った日の放課後以降、どうも僕に対してだけモジモジして喋るようになってしまった。
紗英の『自分のことを俺ということ』や『それぞれ個性がある』などのことはおろか、僕にも全然慣れてくれない。
「なぁ、ノエル、俺が肩を貸してやってもいいぞ」
と紗英がノエルちゃんに手を差し伸べると、それは振り払って
「それなら誠一がいい……でも、別に、大丈夫……アタシ、寝るから……」
と言って、それ以降は、机にうつ伏せになって、そのまま僕たちのことを無視してしまった。
「本人がそういう気ならしょうがないな」
と言って紗英はさっきいた席に戻り、僕も席に戻った。
でもノエルちゃんのことが心配で心配でしょうがなかった。
その後、ノエルちゃんにスベリヒユ料理を振る舞って、給食も食べていたから、まだ大丈夫だとは思うんだけども、何だかなぁ。
だからせめて何か手伝えないかと思って、放課後、スベリヒユ採取を止めて”オオバキボウシ”を採取することにした。
・【ある日のこと】
・
そんなこんなで、毎日校庭にあるスベリヒユを採取しては、二限目と三限目の長めの休み時間にノエルちゃんへ料理を作っていた時だった。
今日、学校にやって来たノエルちゃんはあからさまに調子が悪そうで、席に着くとすぐに胃のあたりをさすっては、うんうんと唸っていた。
その時、僕と紗英は朝の下処理を早めに終えて、もう教室に戻ってきていたので、僕は僕の席に、紗英はその隣の席に座って、何気ない会話をしていた。
でもその、やけにデカくて妙に赤いバッタの話は止めて、ノエルちゃんの話を始めた。
「何か最近、ノエル、ずっと胃のあたりさすっていない? 特に今日、酷そうだし……」
心配そうにそう言った紗英。
確かに僕も1週間前からその傾向を感じていた。
でもお腹はすいているし、食べたいと言っていたので、いつも通りスベリヒユ料理を振る舞っていたのだけども。
どうすればいいんだろうと考えていると、紗英が立ち上がり、
「誠一! 直接聞きに行くよ!」
と言ったので、僕も立ち上がり、ノエルちゃんの席へ行った。
ノエルちゃんは明らかに具合が悪そうにしていたので、僕は困りながら
「ちょっと、ノエルちゃん大丈夫? 具合が悪いなら今日は休んだほうがいいよっ」
と言うと、ノエルちゃんは僕を見るなり、少しモジモジしながら、
「アタシのこと見てたんだ、もぅ……」
と微笑みながら、そう言ったので、
「いやたいした返答になっていないよ、ほら、保健室に連れていこうか?」
と返した。
ノエルちゃんは初めてスベリヒユ料理を振る舞った日の放課後以降、どうも僕に対してだけモジモジして喋るようになってしまった。
紗英の『自分のことを俺ということ』や『それぞれ個性がある』などのことはおろか、僕にも全然慣れてくれない。
「なぁ、ノエル、俺が肩を貸してやってもいいぞ」
と紗英がノエルちゃんに手を差し伸べると、それは振り払って
「それなら誠一がいい……でも、別に、大丈夫……アタシ、寝るから……」
と言って、それ以降は、机にうつ伏せになって、そのまま僕たちのことを無視してしまった。
「本人がそういう気ならしょうがないな」
と言って紗英はさっきいた席に戻り、僕も席に戻った。
でもノエルちゃんのことが心配で心配でしょうがなかった。
その後、ノエルちゃんにスベリヒユ料理を振る舞って、給食も食べていたから、まだ大丈夫だとは思うんだけども、何だかなぁ。
だからせめて何か手伝えないかと思って、放課後、スベリヒユ採取を止めて”オオバキボウシ”を採取することにした。
・
・【オオバキボウシ収穫】
・
「オオバキボウシって何だっけ?」
放課後、紗英と校庭を歩いている時に聞かれた。
「オオバキボウシというのは、別名ウルイとか、ヤマカンピョウとか言われるモノで、まあこれも食べられる野草なんだ」
「いやまあそうだろうけども、スベリヒユと何が違うんだよ。もしかすると採取しやすいのか?」
「ううん、採取の難易度は普通だよ、ほら、あった」
僕は校庭の中をちょろちょろと流れている小川の傍にあったオオバキボウシを指差した。
「何かアスパラガスみたいだな」
「実際アスパラガスのように一本の軸になっているわけじゃなくて、葉っぱが巻かれた状態で出てきているんだ」
「でもまあヒョロヒョロ・ミサイルだな」
「いやヒョロヒョロならもうミサイルとしての尊厳無いでしょっ、綺麗な黄緑色だし」
僕と紗英はオオバキボウシの近くにしゃがんだ。
紗英はオオバキボウシを指でピンピンはじきながら、
「瑞々しいな、まるで水」
「いやその場合は水でたとえないでしょ、果物とかでたとえなよ」
「いやでも頑なに水だな、だって水って瑞々しいじゃん」
「水は正直瑞々しいとは言わないよ、水はもう、マジで水だよ、水でしかないよ」
すると、紗英はどうしようもないな、といった感じの表情を浮かべながらこう言った。
「いや、瑞々しいイコール水だろ、二度も”ミズ”って言ってるんだから間違いない」
「じゃあもう分かったよ、こっちが折れるよ、紗英もノエルちゃんみたいに頑固だね!」
「いやノエルよりは頑固じゃない、ノエルは岩だし、俺は砂まぶした粘土くらい」
「砂まぶしてあったら、もはや粘土も岩だよ」
「じゃあ砂糖まぶした揚げパン」
「急においしそうになった!」
「だろっ!」
と親指を立てながら言った紗英。
いや。
「おいしそうに言うことを正解としていないから! そんな嬉しそうにされても分からないよ!」
「いやもうおいしそうは正解だろ! おいしそうなだけで全て正解だろ! この世は!」
「そんな単純じゃないよ、世界は!」
「いやでも、おいしそうが不正解な時はほぼ無いだろ?」
「確かにそうかもしれないけどもっ」
そう僕が言ったことで、満足げに頷いた紗英。
いやいや。
「何でスベリヒユからオオバキボウシにするのかの話、聞きたくない?」
「それよりも揚げパンに鰹節をまぶしてみたい」
「急に何の話! あとおいしそうじゃない! 不正解じゃん!」
「俺、最近、体から、鰹節って出るんじゃないかなと思い始めているんだ」
「出ないよ! 出たと思ったモノはきっと垢だよ!」
僕がそうツッコむと、紗英はムッとした表情になりながら、
「垢なんてない! 綺麗にしているから! その垢を越えた向こう側から鰹節が出てきそうなんだよ!」
「垢を越えた向こう側は皮膚だよ! グロテスクな話になっちゃうから止めてよ!」
「じゃあもう必殺技! 必殺技的に鰹節手裏剣が手と手を重ねた隙間から出るんだ!」
「また必殺技になった! 何で紗英の必殺技は体から食べ物が最多なんだ!」
「やっぱり食べ物っていいよね、という想いが強いです」
と言いながら、頭をぺこりと下げた紗英。
「いや別に頭は下げなくていいよ、というかもうこっちが頭下げるからオオバキボウシにする理由を話させてよ」
「いいよ、そんなことしなくて、普通に理由を話してくれよ、気になってはいるんだ」
「じゃあ必殺技がどうとか言わないでよ……」
「教えて、教えてっ」
やっと言える流れになったので、僕は一息ついて、ちゃんと覚えたことを言えるようにしてから話し出した。
「オオバキボウシは健胃(けんい)や整腸(せいちょう)などに効く、漢方薬のような一面があるんだ」
「なるほど、偉くなれるわけだ」
「いや権威じゃないよ、権利に威力の権威じゃなくて、健やかな胃で健胃だよ」
「胃が健康になるってこと?」
「そうそう」
紗英は分かったらしく、ニコニコしながら頷くと、こう言った。
「伊賀、健康になるか……伊賀、忍者か! 鰹節手裏剣!」
そう言って手のひらを手のひらで、すごい速度でこすり合わせたので、全然分かっていないと思った。
「伊賀って、伊賀忍者の伊賀じゃなくて、胃! 内臓の胃! が! 健康になるってこと!」
「じゃあ鰹節手裏剣は関係無いということか?」
「いやまあ伊賀忍者の時点で鰹節手裏剣は関係無いよ!」
「まあまあ、本当はちゃんと分かっているよ、大丈夫大丈夫、胃が健康になるってことか……それ! ノエルにうってつけじゃん!」
「いや今そのテンション! やっぱり分かっていなかったんじゃないのっ!」
「そんな野草があるなんて、すごいな野草! もうお医者さんじゃん!」
「いやまあ本当はちゃんとお医者さんに見てもらったほうがいいんだけども、そういう効能がある野草もあるということで」
「サバイバルって食えればいいと思っていたけども、そういうのもあるってのは勉強になるなぁ」
そう言ってどこからともなくメモ帳を取り出して、書き始めた紗英。
そういう目指すべき方向に対して勤勉なところは、本当に尊敬できるなぁ。
というわけで。
「今日はこのオオバキボウシを採取します」
メモを書き終えた紗英は、
「俺もちゃんと手伝うぜ! 忍者並の素早さでな!」
と言って明るく笑った。
そして僕たちはオオバキボウシを採取していった。
・【オオバキボウシ収穫】
・
「オオバキボウシって何だっけ?」
放課後、紗英と校庭を歩いている時に聞かれた。
「オオバキボウシというのは、別名ウルイとか、ヤマカンピョウとか言われるモノで、まあこれも食べられる野草なんだ」
「いやまあそうだろうけども、スベリヒユと何が違うんだよ。もしかすると採取しやすいのか?」
「ううん、採取の難易度は普通だよ、ほら、あった」
僕は校庭の中をちょろちょろと流れている小川の傍にあったオオバキボウシを指差した。
「何かアスパラガスみたいだな」
「実際アスパラガスのように一本の軸になっているわけじゃなくて、葉っぱが巻かれた状態で出てきているんだ」
「でもまあヒョロヒョロ・ミサイルだな」
「いやヒョロヒョロならもうミサイルとしての尊厳無いでしょっ、綺麗な黄緑色だし」
僕と紗英はオオバキボウシの近くにしゃがんだ。
紗英はオオバキボウシを指でピンピンはじきながら、
「瑞々しいな、まるで水」
「いやその場合は水でたとえないでしょ、果物とかでたとえなよ」
「いやでも頑なに水だな、だって水って瑞々しいじゃん」
「水は正直瑞々しいとは言わないよ、水はもう、マジで水だよ、水でしかないよ」
すると、紗英はどうしようもないな、といった感じの表情を浮かべながらこう言った。
「いや、瑞々しいイコール水だろ、二度も”ミズ”って言ってるんだから間違いない」
「じゃあもう分かったよ、こっちが折れるよ、紗英もノエルちゃんみたいに頑固だね!」
「いやノエルよりは頑固じゃない、ノエルは岩だし、俺は砂まぶした粘土くらい」
「砂まぶしてあったら、もはや粘土も岩だよ」
「じゃあ砂糖まぶした揚げパン」
「急においしそうになった!」
「だろっ!」
と親指を立てながら言った紗英。
いや。
「おいしそうに言うことを正解としていないから! そんな嬉しそうにされても分からないよ!」
「いやもうおいしそうは正解だろ! おいしそうなだけで全て正解だろ! この世は!」
「そんな単純じゃないよ、世界は!」
「いやでも、おいしそうが不正解な時はほぼ無いだろ?」
「確かにそうかもしれないけどもっ」
そう僕が言ったことで、満足げに頷いた紗英。
いやいや。
「何でスベリヒユからオオバキボウシにするのかの話、聞きたくない?」
「それよりも揚げパンに鰹節をまぶしてみたい」
「急に何の話! あとおいしそうじゃない! 不正解じゃん!」
「俺、最近、体から、鰹節って出るんじゃないかなと思い始めているんだ」
「出ないよ! 出たと思ったモノはきっと垢だよ!」
僕がそうツッコむと、紗英はムッとした表情になりながら、
「垢なんてない! 綺麗にしているから! その垢を越えた向こう側から鰹節が出てきそうなんだよ!」
「垢を越えた向こう側は皮膚だよ! グロテスクな話になっちゃうから止めてよ!」
「じゃあもう必殺技! 必殺技的に鰹節手裏剣が手と手を重ねた隙間から出るんだ!」
「また必殺技になった! 何で紗英の必殺技は体から食べ物が最多なんだ!」
「やっぱり食べ物っていいよね、という想いが強いです」
と言いながら、頭をぺこりと下げた紗英。
「いや別に頭は下げなくていいよ、というかもうこっちが頭下げるからオオバキボウシにする理由を話させてよ」
「いいよ、そんなことしなくて、普通に理由を話してくれよ、気になってはいるんだ」
「じゃあ必殺技がどうとか言わないでよ……」
「教えて、教えてっ」
やっと言える流れになったので、僕は一息ついて、ちゃんと覚えたことを言えるようにしてから話し出した。
「オオバキボウシは健胃(けんい)や整腸(せいちょう)などに効く、漢方薬のような一面があるんだ」
「なるほど、偉くなれるわけだ」
「いや権威じゃないよ、権利に威力の権威じゃなくて、健やかな胃で健胃だよ」
「胃が健康になるってこと?」
「そうそう」
紗英は分かったらしく、ニコニコしながら頷くと、こう言った。
「伊賀、健康になるか……伊賀、忍者か! 鰹節手裏剣!」
そう言って手のひらを手のひらで、すごい速度でこすり合わせたので、全然分かっていないと思った。
「伊賀って、伊賀忍者の伊賀じゃなくて、胃! 内臓の胃! が! 健康になるってこと!」
「じゃあ鰹節手裏剣は関係無いということか?」
「いやまあ伊賀忍者の時点で鰹節手裏剣は関係無いよ!」
「まあまあ、本当はちゃんと分かっているよ、大丈夫大丈夫、胃が健康になるってことか……それ! ノエルにうってつけじゃん!」
「いや今そのテンション! やっぱり分かっていなかったんじゃないのっ!」
「そんな野草があるなんて、すごいな野草! もうお医者さんじゃん!」
「いやまあ本当はちゃんとお医者さんに見てもらったほうがいいんだけども、そういう効能がある野草もあるということで」
「サバイバルって食えればいいと思っていたけども、そういうのもあるってのは勉強になるなぁ」
そう言ってどこからともなくメモ帳を取り出して、書き始めた紗英。
そういう目指すべき方向に対して勤勉なところは、本当に尊敬できるなぁ。
というわけで。
「今日はこのオオバキボウシを採取します」
メモを書き終えた紗英は、
「俺もちゃんと手伝うぜ! 忍者並の素早さでな!」
と言って明るく笑った。
そして僕たちはオオバキボウシを採取していった。
・
・【健胃の権威】
・
「オオバキボウシは健胃の権威~♪」
やけにゴキゲンで調理室にいる紗英。
今日も朝早く登校して調理室で下処理を行っている。
もう朝早く起きることにも慣れて、二人でこうやって下処理することが日課になった。
僕はこの時間が割と好きだ。
何故なら紗英と一緒にいると楽しいので、こうやって早く登校すれば長く紗英と一緒にいれるから。
「さて、今日はどういう料理を作るんだ?」
「料理も胃に優しい、おひたしでも作ろうかなって思っているんだ」
「そうだね、ここで揚げ物作ったら、とんでもない悪魔だもんな」
僕は鍋を取り出して、水を張り、火にかけた。
そんな僕の肩にトンと手を置いて、紗英はこう言った。
「おひたしは普通に茹でるだけで完成だから簡単じゃん」
僕は振り返って、
「そうだね」
と相槌を打つと、紗英はニッコリと微笑んでこう言った。
「いつも優しいな、誠一は」
「いや急にどうしたの? というか別に普通だよ、何も優しいわけでもないよ」
「でもノエルの胃のこと考えたりさっ」
「それはでもそうだよ、料理の基本はホスピタリティ、献身性だからね。食べてくれる人のことを思いながら作るんだよ」
そう言うと少し面持ちを曇らせながら紗英は、
「思うって、何?」
と機嫌悪そうに言い放った。
何で少し機嫌が悪そうになったのか分からないけども、僕は普通に答えることにした。
「その食べてくれる人のために頑張るというか、うん、そんなところかな?」
「じゃあさ、もし俺に料理作ってくれることがあったら、誠一は俺のこと思ってくれるのか?」
「それは勿論そうだよ。食べる人によって考えることは変わるよ」
「俺ならどんなこと考える?」
急にそんなことを言ってきたので、う~ん、と悩んでいると、
「そっか、俺のことはあんまり考えないかっ」
と、何故か少しやるせない感じの表情を浮かべながら笑ったので、僕は
「いやいやいや! いつも紗英のことは考えているよ!」
と本心をそのまま述べると、
「いつも……考えている……?」
と、紗英が首をかしげながらも、少し嬉しそうにした時、僕は言葉が出た。
「そうそう、それ。僕は紗英がいつも笑顔でいてくれるようなことを考えているから、笑顔になってもらえるような料理を作ると思うよ。たとえば紗英が好きな味の料理とか」
ちゃんと言葉が出て良かったぁ、と胸をなで下ろしていると、紗英が
「じゃあ俺も! 俺もいつも誠一の笑顔を祈っているから!」
と明るい声で叫んだ。
「良かった、じゃあ相思相愛だね」
と、他意無く僕はいつもの感じで普通に言ったら、急に紗英が小声で、
「相思……相愛……?」
と何だか不思議な雰囲気で言ったので、もしかすると相思相愛の意味を理解していないのかなと思って、
「二人共、幸せを思い合っているという意味だよ」
と言うと、紗英は
「そっかぁ……」
と言って、ホッコリと微笑んだので、良かった。
紗英とはずっと仲良く友達でいたいからなぁ。
鍋のお湯も沸騰し、オオバキボウシをサッと茹でて、茹で終えたら流水で締めてから冷蔵庫に片づけた。
二人で調理室をあとにして、教室に戻り、一限目・二限目の授業を終えて、間の長めの休みに僕と紗英とノエルちゃんで調理室にやって来た。
相変わらずノエルちゃんは、やや調子が悪そうにしていた。
「大丈夫? ノエルちゃん、食べられる?」
「いや食べたいことは食べたいんだけど、うん、食べる食べる」
調子が悪くなってからどうも歯切れが悪いノエルちゃん。
このオオバキボウシのおひたしで、少しでも良い方向に向かってくれるといいんだけども。
「今日はオオバキボウシのおひたしで、健胃の効能があるんだ。健胃というのは、胃が健やかに強くなるという意味だよ」
僕は最後の仕上げに、オオバキボウシに鰹節と醤油をかけて、ノエルちゃんの前に出した。
ノエルちゃんはすごく嬉しそうな表情を浮かべながら、
「胃のこと! 分かってくれていたんだ! すごい嬉しい! いただきます!」
と言って、オオバキボウシのおひたしをガツガツと食べ始めた。
「葉っぱが甘い! とろりとしたぬめりが舌に広がって、口の中いっぱいに味が広がる!」
今日もおいしそうに食べてくれて、僕も一安心。
その様子をうんうん頷きながら、満足そうに見ている紗英。
このまま紗英とノエルちゃんの言い合いが無いといいんだけども。
そう思った直後、ノエルちゃんが紗英に話し掛けた。
「今日も勿論一緒なんだね、やっぱり誠一のこと大好きなんだ」
また何でそんなこと言うのかなぁ、と、ちょっとこわごわしていると、紗英が
「そうだね! 大好きだね!」
と少しツンツンしながらも、完全に言い放ったのでビックリした。
そんな言い方したら、またノエルちゃんからネチネチ付き合ってるとか言われちゃうよ、と、あわあわしていると案の定、ノエルちゃんが
「へぇー! じゃあ付き合いたいんだ!」
とこれまた直球で言うと、紗英は
「知らん! でもよく分かんない感情が最近出てきているのは事実!」
と言ったので、僕はさらにビックリしてしまった。
いや紗英は思ったこと全て口に出すことは知っているけども、まさかこんなことを思っているなんて。
というか、えっ? よく分かんない感情ってどういうこと?
僕は訳も分からず、紗英をじっと見ていると、紗英がこっちを向いて、優しく微笑んだ。
その表情に何だか僕は胸がドキドキし始めた。
このままじっと見ているのは何だか恥ずかしいと思い、ノエルちゃんのほうを見ると、ノエルちゃんはやけにうろたえていた。
「へっ、へっ、へぇっ……い、言うねぇ……じゃ、じゃあっ、そのっ、紗英は、あの、誠一のこと好きなんだ……」
「うん! 好きは好きだ! いつも通り!」
「じゃ、じゃっ、それはきっとっ……友達として、だねぇっ……」
「まあな! かもな! でも! 何か! 誠一と! とにかくずっと一緒にいたいんだ!」
紗英がそう言うと、ノエルちゃんはまだ少し皿に残っていたオオバキボウシのおひたしをかっ込んで、皿をダンと強くテーブルに置いて、パンと手を叩き、やたら大きな声で
「ごちそうさまでした!」
と言ってから、立ち上がって、紗英に寄っていって、紗英の腕を引っ張り、
「じゃ! じゃあ! 帰ろうか!」
と叫んだ。
何でこんなにノエルちゃんが慌てているのかな、と思った。
それに対して紗英は、
「いや俺は誠一の片付け手伝っていくからいいよ、ノエルだけ帰ればいいじゃん」
と正論を言うと、ノエルちゃんは
「じゃあアタシも残るし、アタシが誠一の片付けの手伝いする!」
と言って、自分が使った皿と箸を水出し口のところに持って来た。
でも僕は、
「ノエルちゃん、まだ胃の調子悪いでしょ? 僕と紗英でやっておくから大丈夫だよ」
と言うと、ノエルちゃんは『うぅ~』とちょっと唸ったので、
「ほら、まだ胃がきしむんでしょ? そんな即効性は無いからね」
とさらに言うと、ノエルちゃんはすごすごと言った感じに引き下がり、その場をあとにした。
何だか肩を落としているような後ろ姿で、やっぱりまだ胃の調子が良くないんだな、と思った。
残った僕と紗英で、片付けをしてから調理室をあとにしようとしたその時、紗英が
「好きって言ってもいつも通りよろしくな! なんせ俺は誠一と一緒にいたいだけだから!」
と言って笑った。
確かにそうなんだろうけども、何か、何か、僕はどうすればいいか、ちょっと分からなくなってしまった。
まさか紗英がそんなことを言い出すとは思わなかったから。
そして、じゃあ僕は一体何なんだろうか。
どう考えているのだろうか、紗英のことを。
いやでもただの友達、そして何なら師匠ぐらいに思っていたので、何だか紗英の変化に追いついていかない自分がいた。
・【健胃の権威】
・
「オオバキボウシは健胃の権威~♪」
やけにゴキゲンで調理室にいる紗英。
今日も朝早く登校して調理室で下処理を行っている。
もう朝早く起きることにも慣れて、二人でこうやって下処理することが日課になった。
僕はこの時間が割と好きだ。
何故なら紗英と一緒にいると楽しいので、こうやって早く登校すれば長く紗英と一緒にいれるから。
「さて、今日はどういう料理を作るんだ?」
「料理も胃に優しい、おひたしでも作ろうかなって思っているんだ」
「そうだね、ここで揚げ物作ったら、とんでもない悪魔だもんな」
僕は鍋を取り出して、水を張り、火にかけた。
そんな僕の肩にトンと手を置いて、紗英はこう言った。
「おひたしは普通に茹でるだけで完成だから簡単じゃん」
僕は振り返って、
「そうだね」
と相槌を打つと、紗英はニッコリと微笑んでこう言った。
「いつも優しいな、誠一は」
「いや急にどうしたの? というか別に普通だよ、何も優しいわけでもないよ」
「でもノエルの胃のこと考えたりさっ」
「それはでもそうだよ、料理の基本はホスピタリティ、献身性だからね。食べてくれる人のことを思いながら作るんだよ」
そう言うと少し面持ちを曇らせながら紗英は、
「思うって、何?」
と機嫌悪そうに言い放った。
何で少し機嫌が悪そうになったのか分からないけども、僕は普通に答えることにした。
「その食べてくれる人のために頑張るというか、うん、そんなところかな?」
「じゃあさ、もし俺に料理作ってくれることがあったら、誠一は俺のこと思ってくれるのか?」
「それは勿論そうだよ。食べる人によって考えることは変わるよ」
「俺ならどんなこと考える?」
急にそんなことを言ってきたので、う~ん、と悩んでいると、
「そっか、俺のことはあんまり考えないかっ」
と、何故か少しやるせない感じの表情を浮かべながら笑ったので、僕は
「いやいやいや! いつも紗英のことは考えているよ!」
と本心をそのまま述べると、
「いつも……考えている……?」
と、紗英が首をかしげながらも、少し嬉しそうにした時、僕は言葉が出た。
「そうそう、それ。僕は紗英がいつも笑顔でいてくれるようなことを考えているから、笑顔になってもらえるような料理を作ると思うよ。たとえば紗英が好きな味の料理とか」
ちゃんと言葉が出て良かったぁ、と胸をなで下ろしていると、紗英が
「じゃあ俺も! 俺もいつも誠一の笑顔を祈っているから!」
と明るい声で叫んだ。
「良かった、じゃあ相思相愛だね」
と、他意無く僕はいつもの感じで普通に言ったら、急に紗英が小声で、
「相思……相愛……?」
と何だか不思議な雰囲気で言ったので、もしかすると相思相愛の意味を理解していないのかなと思って、
「二人共、幸せを思い合っているという意味だよ」
と言うと、紗英は
「そっかぁ……」
と言って、ホッコリと微笑んだので、良かった。
紗英とはずっと仲良く友達でいたいからなぁ。
鍋のお湯も沸騰し、オオバキボウシをサッと茹でて、茹で終えたら流水で締めてから冷蔵庫に片づけた。
二人で調理室をあとにして、教室に戻り、一限目・二限目の授業を終えて、間の長めの休みに僕と紗英とノエルちゃんで調理室にやって来た。
相変わらずノエルちゃんは、やや調子が悪そうにしていた。
「大丈夫? ノエルちゃん、食べられる?」
「いや食べたいことは食べたいんだけど、うん、食べる食べる」
調子が悪くなってからどうも歯切れが悪いノエルちゃん。
このオオバキボウシのおひたしで、少しでも良い方向に向かってくれるといいんだけども。
「今日はオオバキボウシのおひたしで、健胃の効能があるんだ。健胃というのは、胃が健やかに強くなるという意味だよ」
僕は最後の仕上げに、オオバキボウシに鰹節と醤油をかけて、ノエルちゃんの前に出した。
ノエルちゃんはすごく嬉しそうな表情を浮かべながら、
「胃のこと! 分かってくれていたんだ! すごい嬉しい! いただきます!」
と言って、オオバキボウシのおひたしをガツガツと食べ始めた。
「葉っぱが甘い! とろりとしたぬめりが舌に広がって、口の中いっぱいに味が広がる!」
今日もおいしそうに食べてくれて、僕も一安心。
その様子をうんうん頷きながら、満足そうに見ている紗英。
このまま紗英とノエルちゃんの言い合いが無いといいんだけども。
そう思った直後、ノエルちゃんが紗英に話し掛けた。
「今日も勿論一緒なんだね、やっぱり誠一のこと大好きなんだ」
また何でそんなこと言うのかなぁ、と、ちょっとこわごわしていると、紗英が
「そうだね! 大好きだね!」
と少しツンツンしながらも、完全に言い放ったのでビックリした。
そんな言い方したら、またノエルちゃんからネチネチ付き合ってるとか言われちゃうよ、と、あわあわしていると案の定、ノエルちゃんが
「へぇー! じゃあ付き合いたいんだ!」
とこれまた直球で言うと、紗英は
「知らん! でもよく分かんない感情が最近出てきているのは事実!」
と言ったので、僕はさらにビックリしてしまった。
いや紗英は思ったこと全て口に出すことは知っているけども、まさかこんなことを思っているなんて。
というか、えっ? よく分かんない感情ってどういうこと?
僕は訳も分からず、紗英をじっと見ていると、紗英がこっちを向いて、優しく微笑んだ。
その表情に何だか僕は胸がドキドキし始めた。
このままじっと見ているのは何だか恥ずかしいと思い、ノエルちゃんのほうを見ると、ノエルちゃんはやけにうろたえていた。
「へっ、へっ、へぇっ……い、言うねぇ……じゃ、じゃあっ、そのっ、紗英は、あの、誠一のこと好きなんだ……」
「うん! 好きは好きだ! いつも通り!」
「じゃ、じゃっ、それはきっとっ……友達として、だねぇっ……」
「まあな! かもな! でも! 何か! 誠一と! とにかくずっと一緒にいたいんだ!」
紗英がそう言うと、ノエルちゃんはまだ少し皿に残っていたオオバキボウシのおひたしをかっ込んで、皿をダンと強くテーブルに置いて、パンと手を叩き、やたら大きな声で
「ごちそうさまでした!」
と言ってから、立ち上がって、紗英に寄っていって、紗英の腕を引っ張り、
「じゃ! じゃあ! 帰ろうか!」
と叫んだ。
何でこんなにノエルちゃんが慌てているのかな、と思った。
それに対して紗英は、
「いや俺は誠一の片付け手伝っていくからいいよ、ノエルだけ帰ればいいじゃん」
と正論を言うと、ノエルちゃんは
「じゃあアタシも残るし、アタシが誠一の片付けの手伝いする!」
と言って、自分が使った皿と箸を水出し口のところに持って来た。
でも僕は、
「ノエルちゃん、まだ胃の調子悪いでしょ? 僕と紗英でやっておくから大丈夫だよ」
と言うと、ノエルちゃんは『うぅ~』とちょっと唸ったので、
「ほら、まだ胃がきしむんでしょ? そんな即効性は無いからね」
とさらに言うと、ノエルちゃんはすごすごと言った感じに引き下がり、その場をあとにした。
何だか肩を落としているような後ろ姿で、やっぱりまだ胃の調子が良くないんだな、と思った。
残った僕と紗英で、片付けをしてから調理室をあとにしようとしたその時、紗英が
「好きって言ってもいつも通りよろしくな! なんせ俺は誠一と一緒にいたいだけだから!」
と言って笑った。
確かにそうなんだろうけども、何か、何か、僕はどうすればいいか、ちょっと分からなくなってしまった。
まさか紗英がそんなことを言い出すとは思わなかったから。
そして、じゃあ僕は一体何なんだろうか。
どう考えているのだろうか、紗英のことを。
いやでもただの友達、そして何なら師匠ぐらいに思っていたので、何だか紗英の変化に追いついていかない自分がいた。
・
・【サラサラと食べたい】
・
季節は7月。
どんどん熱くなっていく太陽。
僕は家に帰っても、ノエルちゃんの料理の準備をする日があって、ついに、満を持して、その日がやって来たといった感じだった。
給食が終わって、昼休みの時間にノエルちゃんが元気に僕のところへやって来た。
ちなみに胃はあれから良くなったみたいで、もう変に唸ることは……いや、あることはある。
でも胃が痛そうな感じではないので、どうやら別の理由みたいだ。
それが分かれば、またその部位に効能がある料理を作れるのにな。
聞いてもあんまり答えてくれない。
まだノエルちゃんの信頼を完全に勝ち取っていないって感じかな。
結構料理作っているのに、少し寂しい。
まあそんなことは置いといて、ノエルちゃんが話し掛けてきた。
「最近夏バテ! サラサラと食べられる料理が食べたい!」
相変わらずノエルちゃんのワガママ声はデカい。
基本僕に対してはモジモジしているところもあるんだけども、ワガママの時はやけにデカく、ハッキリしている。
その声に反応した紗英が僕の元にやって来た。
「じゃあまたそういった食材を採りに行こうぜ!」
すると、ノエルちゃんが今度はモジモジしながら、
「その食材採り、大変なのっ?」
と聞いてきたので、僕は普通に、
「サラサラと食べられる料理はそうだなぁ、アマチャヅルにしようと思うから、今回はちょっと大変かもしれないなぁ。地面がぬかるんでいるところにある野草だし、ツルは根を張っているから採りづらいし」
と答えると、ノエルちゃんはう~んと何かを考えてから、
「じゃっ、じゃあっ、大変ならいいけども……」
と少し小さな声でそう言った。
”大変がいい”ってどういう意味だろうと思った。
でも少し考えたら答えが出た。
「もしかするとノエルちゃんも一緒に採取したかったの?」
そう言うと、図星といった感じにノエルちゃんの体が揺れたので、まさしくそうらしい。
「ノエルちゃんも一緒に採取行く?」
と僕は聞くと、ノエルちゃんは
「いや……大変ならいいかな……服とか汚したくないし……」
それに対して、紗英は
「やっぱり都会っ子はぬかるんだところ苦手だろうし、いつも通りノエルは休んでいるといいぞ!」
と言ってノエルの背中を優しく叩いた。
「う、うん……」
そう言ってノエルちゃんは席に戻った。
紗英はそのまま僕の隣にいて、
「というかアマチャヅルって何?」
と言ってきたので、僕は驚いてしまった。
「いやぬかるんだところとか言っていたじゃないか!」
「それは先に誠一が言ったじゃないか」
「そうだけども! ……まあじゃあ、また放課後ねっ」
そう言うと紗英は大きく頷いて、そしていつも通り校庭へ遊びに行った。
さて僕は図書室に行って、料理の勉強でもしようっと。
昼休みも終わり、授業も終わり、放課後になって、早速紗英と合流した。
紗英が大声で叫ぶ。
「アマチャヅル! 何か甘そうだな! でもそんなことない! 何故なら砂糖はサトウキビしかとれないから!」
「いや砂糖は他の野菜からも採れるし、あとアマチャヅルは実際甘いよ」
「甘いのか! すごいな! それ!」
「まあとにかく採取しながら説明するよ」
僕は校庭の裏手の、比較的いつも湿っているような場所へ入っていき、アマチャヅルを指差した。
それを見た紗英が、
「これがアマチャヅルね、もろツルじゃん」
「そりゃツル植物だからね!」
「妙に毛が生えている……熊?」
「毛が生えているイコール熊って! これはどう見てもツルじゃないか! ほっそい緑じゃないか!」
僕がそうツッコむと、紗英は全くもうと言った感じに笑いながらこう言った。
「熊も産まれたてはホソホソの緑だろ」
「全然そんなことないよ! 確実に緑ではないよ! こんな鮮やかな緑色ではないよ!」
「緑のシャツ着ていたら?」
「そんなキャラクターみたいなことはないよ! シャツとか着ないよ!」
そうツッコむと、ハァと溜息をついてから紗英が
「夢無さ過ぎるだろ」
と、呆れるように言ったので、
「熊がシャツ着てて何の夢があるんだ!」
と今日一の声でツッコんだ。
しかし紗英のボケまくりは止まらない。
「熊がシャツ着てたら、いよいよ進化かって思うでしょ」
「だとしたら怖いよ! 熊が進化したら人間太刀打ちできないよ!」
「いやもう友好関係結ぶから。もう森を荒らさないって」
「いや多分一方的な契約! 熊は人間に何してくれるのっ?」
というツッコミには自信満々の顔で、
「シャツ買う」
「いやちょっとした貿易のみ!」
「安ければ買う」
「かなりシビアな消費者なだけ! 案の定、熊が知恵つけたら一方的な展開になっている!」
とツッコむと、紗英はその場に急にしゃがみ込み、
「で、アマチャヅル採取するの? しないの?」
「いやするよ! 紗英が変なこと言うから、それへの対処でいっぱいいっぱいだっただけだよ!」
「じゃあもっと変なこと言おうかっ」
と言って何だか怪しく笑ったので、何を言い出すのかと思ったら、
「やっぱり誠一と一緒に喋るの楽しい! ずっと一緒にいたい!」
といつものことだったので、ホッとしていると、
「何か誠一のこと独占したいぜ!」
と大笑いした。
いや、独占したいって、どういう意味?
紗英は思ったことをそのまま口にする。
だからそのまま独占したいという意味なんだろうけども、いやでも独占するってどういうこと、とか、いろいろ考えていると、紗英が口角を上げながら
「何かノエルのために料理作るとか、ちょっと嫌かもしんないなぁ。もっと俺だけ見てほしいって感じだ!」
と言ったので、僕は『えっ?』と思った。
というか、それって、まさしく、恋とか、そういった感じのヤツじゃ……。
いや僕もよくは知らないから、全然詳しくないから分からないけども。
でも、でも、マンガとかでよくそういう描写があるから……。
「えっと、そ、そっか……うん、ありがとう……」
とよく分からない相槌を打った僕は、紗英の言葉をかき消すようにアマチャヅルの採取を始めた。
「できるだけ若い葉を採る感じでっ」
何だか会話を最小限にしないと気が持ってかれそうで。
そこから僕と紗英は無言でアマチャヅルの採取をした。
そしてその静かな間を切り裂いたのは、紗英だった。
「……迷惑か?」
明らかに不安そうにそう言った紗英。
僕は、どう思っているのか。
紗英のことは友達で、師匠で、それ以上に思うことなんて、あるのかな、ないのかな。
いやでも。
「迷惑ではないよ、というかそう思ってくれることってすごく有り難いことだと思う」
「ゴメンな、俺もよく分かんないんだ。でもノエルと誠一が仲良さげに喋っているの見ていたら、何か、気になっちゃって」
何を言おう。
いや考えても何も出てこない。
こういった時は考えずに出てきた言葉が正解だ。
「分かんないでいいと思うよ。僕も分からないから。きっと分からないまま変わっていくんだと思う。気付いた時、ふと振り返った時、そうだったと後付けのように言葉が出てくるだけだと思うから」
そう僕が言うと、紗英は少し息を整えてから
「やっぱり優しいな、誠一は」
と言って満面の笑みを浮かべた。
いや優しいことは言っていないような気もしたけども、とりあえず頷いた。
そしてアマチャヅルの採取を終えて、それとまた少し別の野草を採取して、僕と紗英はそれぞれ家路に着いた。
・【サラサラと食べたい】
・
季節は7月。
どんどん熱くなっていく太陽。
僕は家に帰っても、ノエルちゃんの料理の準備をする日があって、ついに、満を持して、その日がやって来たといった感じだった。
給食が終わって、昼休みの時間にノエルちゃんが元気に僕のところへやって来た。
ちなみに胃はあれから良くなったみたいで、もう変に唸ることは……いや、あることはある。
でも胃が痛そうな感じではないので、どうやら別の理由みたいだ。
それが分かれば、またその部位に効能がある料理を作れるのにな。
聞いてもあんまり答えてくれない。
まだノエルちゃんの信頼を完全に勝ち取っていないって感じかな。
結構料理作っているのに、少し寂しい。
まあそんなことは置いといて、ノエルちゃんが話し掛けてきた。
「最近夏バテ! サラサラと食べられる料理が食べたい!」
相変わらずノエルちゃんのワガママ声はデカい。
基本僕に対してはモジモジしているところもあるんだけども、ワガママの時はやけにデカく、ハッキリしている。
その声に反応した紗英が僕の元にやって来た。
「じゃあまたそういった食材を採りに行こうぜ!」
すると、ノエルちゃんが今度はモジモジしながら、
「その食材採り、大変なのっ?」
と聞いてきたので、僕は普通に、
「サラサラと食べられる料理はそうだなぁ、アマチャヅルにしようと思うから、今回はちょっと大変かもしれないなぁ。地面がぬかるんでいるところにある野草だし、ツルは根を張っているから採りづらいし」
と答えると、ノエルちゃんはう~んと何かを考えてから、
「じゃっ、じゃあっ、大変ならいいけども……」
と少し小さな声でそう言った。
”大変がいい”ってどういう意味だろうと思った。
でも少し考えたら答えが出た。
「もしかするとノエルちゃんも一緒に採取したかったの?」
そう言うと、図星といった感じにノエルちゃんの体が揺れたので、まさしくそうらしい。
「ノエルちゃんも一緒に採取行く?」
と僕は聞くと、ノエルちゃんは
「いや……大変ならいいかな……服とか汚したくないし……」
それに対して、紗英は
「やっぱり都会っ子はぬかるんだところ苦手だろうし、いつも通りノエルは休んでいるといいぞ!」
と言ってノエルの背中を優しく叩いた。
「う、うん……」
そう言ってノエルちゃんは席に戻った。
紗英はそのまま僕の隣にいて、
「というかアマチャヅルって何?」
と言ってきたので、僕は驚いてしまった。
「いやぬかるんだところとか言っていたじゃないか!」
「それは先に誠一が言ったじゃないか」
「そうだけども! ……まあじゃあ、また放課後ねっ」
そう言うと紗英は大きく頷いて、そしていつも通り校庭へ遊びに行った。
さて僕は図書室に行って、料理の勉強でもしようっと。
昼休みも終わり、授業も終わり、放課後になって、早速紗英と合流した。
紗英が大声で叫ぶ。
「アマチャヅル! 何か甘そうだな! でもそんなことない! 何故なら砂糖はサトウキビしかとれないから!」
「いや砂糖は他の野菜からも採れるし、あとアマチャヅルは実際甘いよ」
「甘いのか! すごいな! それ!」
「まあとにかく採取しながら説明するよ」
僕は校庭の裏手の、比較的いつも湿っているような場所へ入っていき、アマチャヅルを指差した。
それを見た紗英が、
「これがアマチャヅルね、もろツルじゃん」
「そりゃツル植物だからね!」
「妙に毛が生えている……熊?」
「毛が生えているイコール熊って! これはどう見てもツルじゃないか! ほっそい緑じゃないか!」
僕がそうツッコむと、紗英は全くもうと言った感じに笑いながらこう言った。
「熊も産まれたてはホソホソの緑だろ」
「全然そんなことないよ! 確実に緑ではないよ! こんな鮮やかな緑色ではないよ!」
「緑のシャツ着ていたら?」
「そんなキャラクターみたいなことはないよ! シャツとか着ないよ!」
そうツッコむと、ハァと溜息をついてから紗英が
「夢無さ過ぎるだろ」
と、呆れるように言ったので、
「熊がシャツ着てて何の夢があるんだ!」
と今日一の声でツッコんだ。
しかし紗英のボケまくりは止まらない。
「熊がシャツ着てたら、いよいよ進化かって思うでしょ」
「だとしたら怖いよ! 熊が進化したら人間太刀打ちできないよ!」
「いやもう友好関係結ぶから。もう森を荒らさないって」
「いや多分一方的な契約! 熊は人間に何してくれるのっ?」
というツッコミには自信満々の顔で、
「シャツ買う」
「いやちょっとした貿易のみ!」
「安ければ買う」
「かなりシビアな消費者なだけ! 案の定、熊が知恵つけたら一方的な展開になっている!」
とツッコむと、紗英はその場に急にしゃがみ込み、
「で、アマチャヅル採取するの? しないの?」
「いやするよ! 紗英が変なこと言うから、それへの対処でいっぱいいっぱいだっただけだよ!」
「じゃあもっと変なこと言おうかっ」
と言って何だか怪しく笑ったので、何を言い出すのかと思ったら、
「やっぱり誠一と一緒に喋るの楽しい! ずっと一緒にいたい!」
といつものことだったので、ホッとしていると、
「何か誠一のこと独占したいぜ!」
と大笑いした。
いや、独占したいって、どういう意味?
紗英は思ったことをそのまま口にする。
だからそのまま独占したいという意味なんだろうけども、いやでも独占するってどういうこと、とか、いろいろ考えていると、紗英が口角を上げながら
「何かノエルのために料理作るとか、ちょっと嫌かもしんないなぁ。もっと俺だけ見てほしいって感じだ!」
と言ったので、僕は『えっ?』と思った。
というか、それって、まさしく、恋とか、そういった感じのヤツじゃ……。
いや僕もよくは知らないから、全然詳しくないから分からないけども。
でも、でも、マンガとかでよくそういう描写があるから……。
「えっと、そ、そっか……うん、ありがとう……」
とよく分からない相槌を打った僕は、紗英の言葉をかき消すようにアマチャヅルの採取を始めた。
「できるだけ若い葉を採る感じでっ」
何だか会話を最小限にしないと気が持ってかれそうで。
そこから僕と紗英は無言でアマチャヅルの採取をした。
そしてその静かな間を切り裂いたのは、紗英だった。
「……迷惑か?」
明らかに不安そうにそう言った紗英。
僕は、どう思っているのか。
紗英のことは友達で、師匠で、それ以上に思うことなんて、あるのかな、ないのかな。
いやでも。
「迷惑ではないよ、というかそう思ってくれることってすごく有り難いことだと思う」
「ゴメンな、俺もよく分かんないんだ。でもノエルと誠一が仲良さげに喋っているの見ていたら、何か、気になっちゃって」
何を言おう。
いや考えても何も出てこない。
こういった時は考えずに出てきた言葉が正解だ。
「分かんないでいいと思うよ。僕も分からないから。きっと分からないまま変わっていくんだと思う。気付いた時、ふと振り返った時、そうだったと後付けのように言葉が出てくるだけだと思うから」
そう僕が言うと、紗英は少し息を整えてから
「やっぱり優しいな、誠一は」
と言って満面の笑みを浮かべた。
いや優しいことは言っていないような気もしたけども、とりあえず頷いた。
そしてアマチャヅルの採取を終えて、それとまた少し別の野草を採取して、僕と紗英はそれぞれ家路に着いた。
・
・【二つのアマチャヅル】
・
僕は今日、大きな水筒を持って学校へ行った。
そして教室で紗英と会って、二,三言葉を交わして二人で調理室へ行った。
水筒を持って。
その姿を見た紗英は調理室に入ってから、こう言った。
「何だ誠一、朝からノド渇いているのか?」
「ううん、これはアマチャヅルのお茶が入っているんだ」
「アマチャヅルのお茶? アマチャヅルってお茶になるのか!」
そう言って驚いてくれた紗英。
そうそう。
「アマチャヅルは名前の通り、甘いお茶になるんだ。ちなみにこのお茶は僕が家で作っていたお茶なんだ。お茶にするには葉っぱを乾燥させないといけないからね」
「じゃあそのお茶で完成かよ! 調理室来た意味無い!」
「いやいや、これから料理を作るよ。天つゆのお茶割りというモノがあるんだけども、それで天つゆを作って今日はスベリヒユの麺とアマチャヅルの天ぷらを作るんだ」
「そう言えば、誠一、何だかんだでスベリヒユも収穫していたなぁ」
また鍋に水を入れて、火をかけた。
「スベリヒユは少し長めに茹でて、天つゆに味が馴染みやすいようにして、天ぷらはまあ油の準備だけして、ノエルちゃんが来た時に一気に揚げる感じかな」
「すごい豪華だなぁ、そうだ、アマチャヅルのお茶、少し飲んでいいか?」
「うん、いいよ」
僕はコップにアマチャヅルのお茶を入れて、紗英に渡すと、紗英はそれをゴクゴク飲んで、こう言った。
「うん! なかなか甘さを感じるなぁ! ちょっとした苦みがまたスッキリしていい感じだ!」
「良かったぁ、アマチャヅルって個体差があって、甘いヤツとあまり甘くないヤツがあって、甘いヤツで良かったぁ」
「そっちのほうがノエルは好きそうだよな!」
そう言って笑った紗英。
やっぱり笑っている紗英はいいなぁ、と、ふと思った僕。
……いや、何をふと思っているんだろう。
いやでも、そう考えてしまうし……とか、いろんな言葉が脳内に浮かんでは消えしていると、紗英が急に
「誠一はさ、ノエルのこと好き?」
と真面目なトーンで聞いてきた。
僕は一瞬ドキッとしてから、バッと紗英のほうを見ると、紗英はすごく不安そうな顔をしながらこっちを見ていた。
だから僕は真面目に答えた。
「普通の友達といった感じかな、最初は嫌な感じもあったけども、今は本当に普通」
これで合っていたかどうか何か考えてしまう。
いや自分の答えに合っているも合っていないもないんだけども。
それに対して紗英は、一安心したような顔をして、
「お湯! 沸いたよ!」
と言った。
僕は無言でスベリヒユを茹でて、また天ぷらの下準備だけして、油の入った鍋に蓋をして教室に戻った。
そして二限目と三限目の長めの休みになり、僕と紗英とノエルちゃんで調理師に入った。
僕はすぐさま油の入った鍋を熱して、またアマチャヅルのお茶と天つゆを割って、スベリヒユを皿に盛り付け始めた。
そんな時にノエルちゃんはハッキリと、突然、こう言った。
「アタシは誠一のことが好き!」
あまりの突然のことに、僕は一体どんな顔をしていたのだろうか。
でも紗英の顔は分かる。
紗英の顔を見ていたから。
紗英は震えだして、みるみる青ざめていった。
ノエルちゃんは続ける。
「アタシのために毎日料理を作ってくれて、すごく嬉しい! これからもお願いします! いやっ! これから一生よろしくお願いします!」
紗英は口から泡を吐きそうなほど、ぶるぶると小刻みに震えていた。
「アタシ! このままじゃ負けると思ってハッキリ言う! 全部言う! だから聞いてほしいのっ!」
ノエルちゃんはツインテールを激しく揺らしながら、大声で叫んだ。
負けるって何が、とか思う暇も無く、ノエルちゃんはまくしたてる。
「アタシが転校してきた理由ってアタシが前の学校に馴染めなくてなのっ! この見た目で除け者にされて! 多分嫉妬だったと思う! うん! でも! この学校は皆、アタシのことを全然気にしていなくて!」
それはきっと皆、紗英の男っぽい感じに慣れていて、今さらワガママや見た目程度じゃ誰も気にしなかったということだと思う。
「でもきっとちょっとでも嫌なこと、たとえばイジワルなこと言ったらすぐボロが出ると思って、紗英のことイジっていたけども、ただそのことについて言い合いになるだけで、アタシのことを芯から除け者にするようなことはなくて!」
そう言うと紗英が、今まで震えていたのが嘘のようにキッパリこう言った。
「そりゃそうだろ、除け者とか面倒なことできないから」
「ありがとう! アタシね! 結構紗英のこと好きなんだよ! 実際! だから紗英の幸せを願ったほうがいいのかもと思ったけども! やっぱりアタシはワガママだから言う! 誠一のことが好き!」
僕はちょっと訳分からなくなりながら、
「幸せを願うとか、そもそもさっきの負けるとか、何言ってるの? ノエルちゃん……」
と言うと、ノエルちゃんはスゥと息を吸ってから大きな声でこう言った。
「鈍感! というか分かっているでしょ! 難しいことから逃げているだけ! 紗英もアタシも誠一のこと好きなんだから!」
難しいことから逃げている。
いやこんな料理を作るだなんて難しいことをしているのに、逃げているなんて言われるとは。
言われるだろうな。
だって、もう、さすがに、全部分かっているから。
紗英が震えていた理由さえも分かるから。
ノエルちゃんがもっと大きな声で言う。
「きっと誠一は紗英を選ぶの! でもいいの! この想いを伝えずにグダグダしているのは嫌なのっ! アタシはもう逃げないの! 前は転校という形で嫌なことから逃げてきたけども、これだけは逃げない! ハッキリ言う! 誠一が好きぃっ!」
そうだ、だから、僕も、逃げずに言わなきゃ。
「……僕は、僕は……紗英が好き、かもしれない。いや分からないけども。でも僕も、紗英と、ずっと一緒にいたいんだ……」
そう言うと、紗英は一言呟いた。
「好き」
僕もだ。
鍋に入った揚げ油がパチパチと音を立て始めた。
そろそろ、アマチャヅルの葉を揚げないと。
そろそろ、ちゃんとした言葉をあげないと。
「紗英、僕は紗英と一緒にずっといたい。好きだよ、紗英」
そう言って僕はアマチャヅルの葉を揚げ始めた。
アマチャヅルに衣の華が咲いて。
「ありがとう、誠一! 俺も誠一のことが大好きだ!」
紗英の面持ちが満開になった。
と思った時に、僕は紗英しか見ていないことに気付いた。
僕はゆっくりノエルちゃんのほうを見ると、ビシッとこっちを指差しながらこう言った。
「だからって諦めるアタシでもないから! アタシはワガママだから! 絶対手に入れるから!」
何だかドキッとしてしまった。
このまま調理できるのかとか考えていると、
「まずは……誠一の天ぷらを手に入れます! 料理よろしく!」
と言ったノエルちゃん。
そのマイペースぶりに、つい笑ってしまい、何だか周りの空気が和んだ。
そして料理を完成させ、ノエルちゃんの前に差し出した。
「いただきます!」
ノエルちゃんはスベリヒユをズルズルとすすり、さらに天ぷらをサクサク食べ始めた。
「おいしい! スベリヒユのぬめりでノド越しがとても良くて、天ぷらも歯ごたえバッチリで食感が違って面白い!」
ノエルちゃんが食べている姿を見て、ふと、紗英は言った。
「じゃあ次は俺が誠一から料理を作ってもらうかな」
その言葉に、先に反応したのが、ノエルちゃんだった。
「うん! それがいいと思う! 何故なら誠一の料理はおいしいから!」
そう言って、屈託の無い笑顔を浮かべたノエルちゃん。
そう言ってもらえることは、とても嬉しい。
ノエルちゃんは続ける。
「じゃあ明日はアタシ食べないよ! 誠一は紗英のための料理作るといいよ!」
そう言うと、紗英は
「敵に塩を送っていいの?」
と何故か自信満々にそう言うと、
「いいよ! アタシはそこまで野暮じゃないし! 盛り返す作戦もあるからね!」
「じゃあいいんだけどな!」
と何だか妙に仲良さげに話している紗英とノエルちゃん。
でもこれって僕を取り合う話なんだよな、と思うと、急に体が熱くなってきた。
あまり意識しないように、まずは揚げ油の片付けをして、別のことに集中することにした。
あとはそうだ、紗英に何を作ろうか考えよう。
まずはその人のことを思って、いや想って作る。
それが全ての基本だから。
紗英のことを想って、想って、その先に、また新しい何かが見つかればいいな。
(了)
・【二つのアマチャヅル】
・
僕は今日、大きな水筒を持って学校へ行った。
そして教室で紗英と会って、二,三言葉を交わして二人で調理室へ行った。
水筒を持って。
その姿を見た紗英は調理室に入ってから、こう言った。
「何だ誠一、朝からノド渇いているのか?」
「ううん、これはアマチャヅルのお茶が入っているんだ」
「アマチャヅルのお茶? アマチャヅルってお茶になるのか!」
そう言って驚いてくれた紗英。
そうそう。
「アマチャヅルは名前の通り、甘いお茶になるんだ。ちなみにこのお茶は僕が家で作っていたお茶なんだ。お茶にするには葉っぱを乾燥させないといけないからね」
「じゃあそのお茶で完成かよ! 調理室来た意味無い!」
「いやいや、これから料理を作るよ。天つゆのお茶割りというモノがあるんだけども、それで天つゆを作って今日はスベリヒユの麺とアマチャヅルの天ぷらを作るんだ」
「そう言えば、誠一、何だかんだでスベリヒユも収穫していたなぁ」
また鍋に水を入れて、火をかけた。
「スベリヒユは少し長めに茹でて、天つゆに味が馴染みやすいようにして、天ぷらはまあ油の準備だけして、ノエルちゃんが来た時に一気に揚げる感じかな」
「すごい豪華だなぁ、そうだ、アマチャヅルのお茶、少し飲んでいいか?」
「うん、いいよ」
僕はコップにアマチャヅルのお茶を入れて、紗英に渡すと、紗英はそれをゴクゴク飲んで、こう言った。
「うん! なかなか甘さを感じるなぁ! ちょっとした苦みがまたスッキリしていい感じだ!」
「良かったぁ、アマチャヅルって個体差があって、甘いヤツとあまり甘くないヤツがあって、甘いヤツで良かったぁ」
「そっちのほうがノエルは好きそうだよな!」
そう言って笑った紗英。
やっぱり笑っている紗英はいいなぁ、と、ふと思った僕。
……いや、何をふと思っているんだろう。
いやでも、そう考えてしまうし……とか、いろんな言葉が脳内に浮かんでは消えしていると、紗英が急に
「誠一はさ、ノエルのこと好き?」
と真面目なトーンで聞いてきた。
僕は一瞬ドキッとしてから、バッと紗英のほうを見ると、紗英はすごく不安そうな顔をしながらこっちを見ていた。
だから僕は真面目に答えた。
「普通の友達といった感じかな、最初は嫌な感じもあったけども、今は本当に普通」
これで合っていたかどうか何か考えてしまう。
いや自分の答えに合っているも合っていないもないんだけども。
それに対して紗英は、一安心したような顔をして、
「お湯! 沸いたよ!」
と言った。
僕は無言でスベリヒユを茹でて、また天ぷらの下準備だけして、油の入った鍋に蓋をして教室に戻った。
そして二限目と三限目の長めの休みになり、僕と紗英とノエルちゃんで調理師に入った。
僕はすぐさま油の入った鍋を熱して、またアマチャヅルのお茶と天つゆを割って、スベリヒユを皿に盛り付け始めた。
そんな時にノエルちゃんはハッキリと、突然、こう言った。
「アタシは誠一のことが好き!」
あまりの突然のことに、僕は一体どんな顔をしていたのだろうか。
でも紗英の顔は分かる。
紗英の顔を見ていたから。
紗英は震えだして、みるみる青ざめていった。
ノエルちゃんは続ける。
「アタシのために毎日料理を作ってくれて、すごく嬉しい! これからもお願いします! いやっ! これから一生よろしくお願いします!」
紗英は口から泡を吐きそうなほど、ぶるぶると小刻みに震えていた。
「アタシ! このままじゃ負けると思ってハッキリ言う! 全部言う! だから聞いてほしいのっ!」
ノエルちゃんはツインテールを激しく揺らしながら、大声で叫んだ。
負けるって何が、とか思う暇も無く、ノエルちゃんはまくしたてる。
「アタシが転校してきた理由ってアタシが前の学校に馴染めなくてなのっ! この見た目で除け者にされて! 多分嫉妬だったと思う! うん! でも! この学校は皆、アタシのことを全然気にしていなくて!」
それはきっと皆、紗英の男っぽい感じに慣れていて、今さらワガママや見た目程度じゃ誰も気にしなかったということだと思う。
「でもきっとちょっとでも嫌なこと、たとえばイジワルなこと言ったらすぐボロが出ると思って、紗英のことイジっていたけども、ただそのことについて言い合いになるだけで、アタシのことを芯から除け者にするようなことはなくて!」
そう言うと紗英が、今まで震えていたのが嘘のようにキッパリこう言った。
「そりゃそうだろ、除け者とか面倒なことできないから」
「ありがとう! アタシね! 結構紗英のこと好きなんだよ! 実際! だから紗英の幸せを願ったほうがいいのかもと思ったけども! やっぱりアタシはワガママだから言う! 誠一のことが好き!」
僕はちょっと訳分からなくなりながら、
「幸せを願うとか、そもそもさっきの負けるとか、何言ってるの? ノエルちゃん……」
と言うと、ノエルちゃんはスゥと息を吸ってから大きな声でこう言った。
「鈍感! というか分かっているでしょ! 難しいことから逃げているだけ! 紗英もアタシも誠一のこと好きなんだから!」
難しいことから逃げている。
いやこんな料理を作るだなんて難しいことをしているのに、逃げているなんて言われるとは。
言われるだろうな。
だって、もう、さすがに、全部分かっているから。
紗英が震えていた理由さえも分かるから。
ノエルちゃんがもっと大きな声で言う。
「きっと誠一は紗英を選ぶの! でもいいの! この想いを伝えずにグダグダしているのは嫌なのっ! アタシはもう逃げないの! 前は転校という形で嫌なことから逃げてきたけども、これだけは逃げない! ハッキリ言う! 誠一が好きぃっ!」
そうだ、だから、僕も、逃げずに言わなきゃ。
「……僕は、僕は……紗英が好き、かもしれない。いや分からないけども。でも僕も、紗英と、ずっと一緒にいたいんだ……」
そう言うと、紗英は一言呟いた。
「好き」
僕もだ。
鍋に入った揚げ油がパチパチと音を立て始めた。
そろそろ、アマチャヅルの葉を揚げないと。
そろそろ、ちゃんとした言葉をあげないと。
「紗英、僕は紗英と一緒にずっといたい。好きだよ、紗英」
そう言って僕はアマチャヅルの葉を揚げ始めた。
アマチャヅルに衣の華が咲いて。
「ありがとう、誠一! 俺も誠一のことが大好きだ!」
紗英の面持ちが満開になった。
と思った時に、僕は紗英しか見ていないことに気付いた。
僕はゆっくりノエルちゃんのほうを見ると、ビシッとこっちを指差しながらこう言った。
「だからって諦めるアタシでもないから! アタシはワガママだから! 絶対手に入れるから!」
何だかドキッとしてしまった。
このまま調理できるのかとか考えていると、
「まずは……誠一の天ぷらを手に入れます! 料理よろしく!」
と言ったノエルちゃん。
そのマイペースぶりに、つい笑ってしまい、何だか周りの空気が和んだ。
そして料理を完成させ、ノエルちゃんの前に差し出した。
「いただきます!」
ノエルちゃんはスベリヒユをズルズルとすすり、さらに天ぷらをサクサク食べ始めた。
「おいしい! スベリヒユのぬめりでノド越しがとても良くて、天ぷらも歯ごたえバッチリで食感が違って面白い!」
ノエルちゃんが食べている姿を見て、ふと、紗英は言った。
「じゃあ次は俺が誠一から料理を作ってもらうかな」
その言葉に、先に反応したのが、ノエルちゃんだった。
「うん! それがいいと思う! 何故なら誠一の料理はおいしいから!」
そう言って、屈託の無い笑顔を浮かべたノエルちゃん。
そう言ってもらえることは、とても嬉しい。
ノエルちゃんは続ける。
「じゃあ明日はアタシ食べないよ! 誠一は紗英のための料理作るといいよ!」
そう言うと、紗英は
「敵に塩を送っていいの?」
と何故か自信満々にそう言うと、
「いいよ! アタシはそこまで野暮じゃないし! 盛り返す作戦もあるからね!」
「じゃあいいんだけどな!」
と何だか妙に仲良さげに話している紗英とノエルちゃん。
でもこれって僕を取り合う話なんだよな、と思うと、急に体が熱くなってきた。
あまり意識しないように、まずは揚げ油の片付けをして、別のことに集中することにした。
あとはそうだ、紗英に何を作ろうか考えよう。
まずはその人のことを思って、いや想って作る。
それが全ての基本だから。
紗英のことを想って、想って、その先に、また新しい何かが見つかればいいな。
(了)
【400字のあらすじ】
都会から転校してきたノエルちゃんはいつもお腹がすいていた。
この村にはスーパーはおろか、コンビニも無く、食べ物が少ないらしい。
そこで僕は、友達の紗英の力も借りて、ノエルちゃんにとある申し出をした。
「僕が野草で料理を作ってあげるよ」
それから僕は二限目と三限目の間に、スベリヒユやオオバキボウシやアマチャヅルで野草料理を作ることに。
そんな中、徐々に紗英が僕を異性として意識していっているようで、僕はドギマギしてしまう。
また紗英は思ったことを全て言うほうなので、そこに際限は無く。
僕と紗英は仲良くボケたりツッコんだりして会話しながら、仲を深めていく。
ある日、僕はノエルちゃんから告白されてしまう。
そこで僕は逃げずに考え、紗英を選んだのであった。
都会から転校してきたノエルちゃんはいつもお腹がすいていた。
この村にはスーパーはおろか、コンビニも無く、食べ物が少ないらしい。
そこで僕は、友達の紗英の力も借りて、ノエルちゃんにとある申し出をした。
「僕が野草で料理を作ってあげるよ」
それから僕は二限目と三限目の間に、スベリヒユやオオバキボウシやアマチャヅルで野草料理を作ることに。
そんな中、徐々に紗英が僕を異性として意識していっているようで、僕はドギマギしてしまう。
また紗英は思ったことを全て言うほうなので、そこに際限は無く。
僕と紗英は仲良くボケたりツッコんだりして会話しながら、仲を深めていく。
ある日、僕はノエルちゃんから告白されてしまう。
そこで僕は逃げずに考え、紗英を選んだのであった。
この作家の他の作品
表紙を見る
学校が定めるテストで最下位の生徒は、自殺室で自殺をしなければならない。
最下位を”わざと”とって死ぬ道を選んだ主人公・田中信太の物語。
その自殺室は死にたいと死ねなくて、生きたい人が死ぬ部屋だった。
そこで信太はずっと死にたくて死ねない人間・溝渕弥勒と出会い、そこで自殺室にやって来る生徒を安らかに自殺へ導く案内人をすることになった。
きちんと自殺に導かなければ、目の前で惨い死に方をされてしまい、なおさら死にたくなるので、案内人をやる。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…