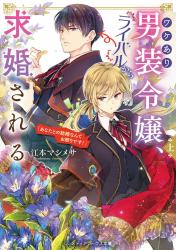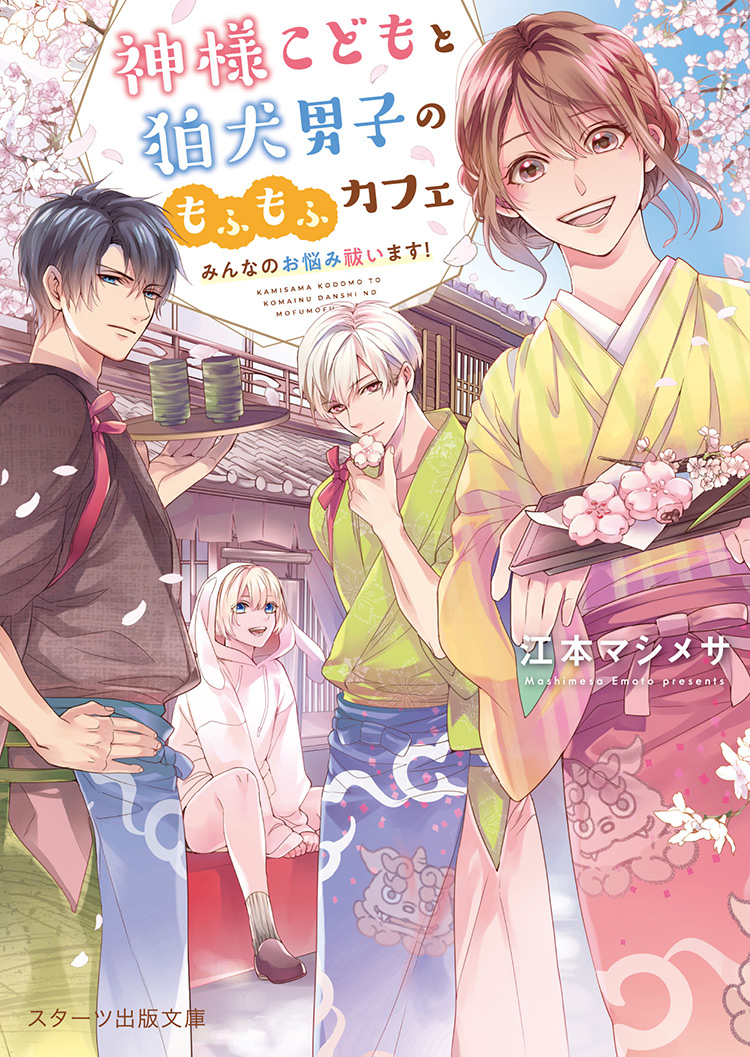実際にできるかは謎だが、世界にはいろいろな言葉の返し方があるものだと、しみじみ感心してしまった。
「また来るからな!」
鷹司さんは高々と宣言し、帰っていった。なんというか、嵐が過ぎ去った感がある。
つごもりさんと良夜さんは、ため息をついていた。
「まあ、悪い人ではない、ということだけはわかりました」
「同じく」
「ですね」
鷹司さんには“嵐”ではなく、町を変える“風”になってほしい。
そう、思ってしまった。
「また来るからな!」
鷹司さんは高々と宣言し、帰っていった。なんというか、嵐が過ぎ去った感がある。
つごもりさんと良夜さんは、ため息をついていた。
「まあ、悪い人ではない、ということだけはわかりました」
「同じく」
「ですね」
鷹司さんには“嵐”ではなく、町を変える“風”になってほしい。
そう、思ってしまった。