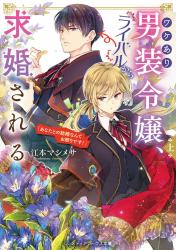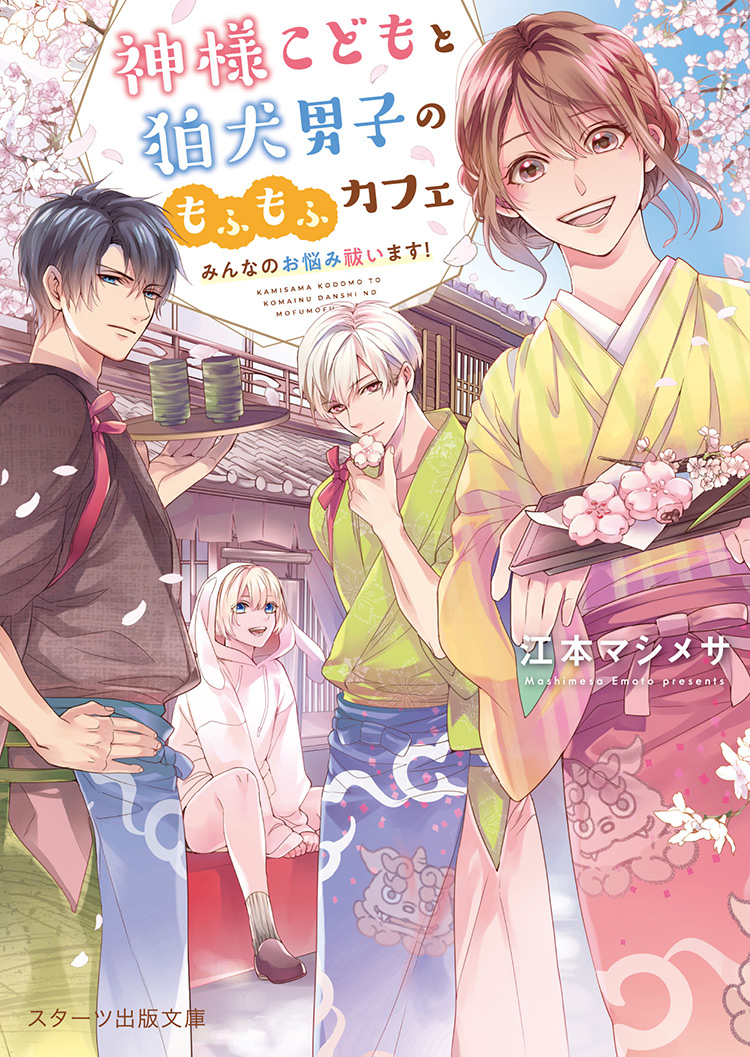現在の父は眉間に皺ばかり寄っている気難しい中年親父だが、可愛い時代が確かにあったのだ。
一冊だけ、本が収められていた。ゲーテの詩集である。まさか、祖母にゲーテを嗜む趣味があったとは意外だ。
パラパラとページを捲っていたら、古びた一枚の写真も出てきた。よくよく見たら、つごもりさんそっくりだったので驚く。
「それは、幸代の初恋の人ですよ。戦争に行って、そのまま帰らぬ人となってしまったようで」
「は、はあ……」
初恋の人の姿をもう一度――その希望を叶えたのが、現在のつごもりさんの姿らしい。
「幸代は毎日毎日、飽きもせずにつごもりの顔をうっとり眺めていましたよ」
物静かなつごもりさんと違い、明るいけれどいじわるな一面もある青年だったらしい。
「幸代は、初恋の彼の顔が、猛烈に好きだった、と思い出を語っていました」
そうなのだ。祖母は大変な面食いで、イケメンアイドルにハマっているという話を聞いた覚えがある。
「ちなみに、良夜さんは……?」
恐る恐る質問してみる。もちづき君は父の幼少期。満月大神は祖父の姿。つごもりさんは初恋の人。
他に、祖母の愛する男がいたというのか。
祖父を亡くしたのは、祖母が二十歳のときだったと聞いていた。それから、恋のひとつやふたつしていても、なんら不思議ではないが……。
ただ、銀髪に赤目の人とは、いったい何関係の人なのだろうか。漫画のキャラクターとか?
「私は最近祖母が熱を上げていた、韓流スターから姿を拝借したものです」
「ああ、韓流スター!」
言われてみたら、良夜さんは背が高くて、細身で、シュッとしている。確かに韓流スターっぽい。
ふたりとも、雰囲気が異なるわけだ。
雰囲気が異なるといえば、名前もそうだ。つごもりさんはどこか古めかしくて、良夜さんは現代風だ。聞いてみたところ、ふたりの神使の誕生は、神社に作られた神使像がきっかけだったらしい。
つごもりさんの神使像が神社に作られたのは、約千年前の鎌倉時代。月が隠れて見えなくなる、月隠りの晩に奉納されたので、“つごもり”と名付けたのだとか。
一方で、良夜さんがやってきたのは、二百年前の江戸時代。中秋の名月の、月明かりが眩しい晩に奉納されたために、月が明るくて良い夜という意味の“良夜”と命名したようだ。
ともに、名付け親は満月大神である。
一冊だけ、本が収められていた。ゲーテの詩集である。まさか、祖母にゲーテを嗜む趣味があったとは意外だ。
パラパラとページを捲っていたら、古びた一枚の写真も出てきた。よくよく見たら、つごもりさんそっくりだったので驚く。
「それは、幸代の初恋の人ですよ。戦争に行って、そのまま帰らぬ人となってしまったようで」
「は、はあ……」
初恋の人の姿をもう一度――その希望を叶えたのが、現在のつごもりさんの姿らしい。
「幸代は毎日毎日、飽きもせずにつごもりの顔をうっとり眺めていましたよ」
物静かなつごもりさんと違い、明るいけれどいじわるな一面もある青年だったらしい。
「幸代は、初恋の彼の顔が、猛烈に好きだった、と思い出を語っていました」
そうなのだ。祖母は大変な面食いで、イケメンアイドルにハマっているという話を聞いた覚えがある。
「ちなみに、良夜さんは……?」
恐る恐る質問してみる。もちづき君は父の幼少期。満月大神は祖父の姿。つごもりさんは初恋の人。
他に、祖母の愛する男がいたというのか。
祖父を亡くしたのは、祖母が二十歳のときだったと聞いていた。それから、恋のひとつやふたつしていても、なんら不思議ではないが……。
ただ、銀髪に赤目の人とは、いったい何関係の人なのだろうか。漫画のキャラクターとか?
「私は最近祖母が熱を上げていた、韓流スターから姿を拝借したものです」
「ああ、韓流スター!」
言われてみたら、良夜さんは背が高くて、細身で、シュッとしている。確かに韓流スターっぽい。
ふたりとも、雰囲気が異なるわけだ。
雰囲気が異なるといえば、名前もそうだ。つごもりさんはどこか古めかしくて、良夜さんは現代風だ。聞いてみたところ、ふたりの神使の誕生は、神社に作られた神使像がきっかけだったらしい。
つごもりさんの神使像が神社に作られたのは、約千年前の鎌倉時代。月が隠れて見えなくなる、月隠りの晩に奉納されたので、“つごもり”と名付けたのだとか。
一方で、良夜さんがやってきたのは、二百年前の江戸時代。中秋の名月の、月明かりが眩しい晩に奉納されたために、月が明るくて良い夜という意味の“良夜”と命名したようだ。
ともに、名付け親は満月大神である。