Fool という名のBar
ここは、愚か者が静かに酔い潰れるための店
今宵もまた一人、愚か者が紛れ込んで来る。
「おかしな街ですね、ここは」
その男はあたしの顔を見てホッとしたような顔をした。
「何かありましたか?」
あたしはおしぼりを渡しながら男を観察した。
記憶の隅に引っ掛かる。あたしはこの男に会ったことがあると感じた。
「いきなりね、若い頃のシルベスター・スタローンのような男にボディ・ガードを雇えよと押し売りされたのですよ」
この男は愚か者達が騒いでいた、あたしを探す男だった。
この街に異物が混入されると愚か者達が騒ぎだす。この店の常連客達だ。
特にこの男は、あたしの顔らしき絵が描かれた写真を持ってこの街を歩いた。
『命がいくつあっても足りない奴だ』
と愚か者達が動き出した。
「あんたかい?あたしに似た女の絵を写真に撮って街を歩いていたのは?」
男はブレザーのポケットから写真を出してカウンターに置いた。
写真の女の顔、確かにあたしだ。でも着ている服はとんでもない、あたしなどではない。
「聖母マリアですよ、これは。でも顔はあなただ、あなたをモデルにした」
あたしは笑うしかなかった。
「私は桐生という者です。昔、一度だけここに来たことがあります。冬木さんに呼ばれてね」
あたしの記憶の中に桐生の顔が浮上して来る。
「でも、あの時のあんたは若い、とても若かったね」
「ええ、まだ駆け出しの彫り物師でしたからね。この写真は冬木さんの背中です。私が彫りました」
あたしは動揺を必死に押さえた。
「知らない?抱かれたことがない?これを見たことがないってことは」
冬木の背中にあたしがいた。
「闇の中にしか居なかったからね、あの頃は」
そこまで言うのが限界だった。あたしは喉がカラカラに渇いていた。
♪ ピアノ
救いのようにマリアのピアノ。
♪ I'm A Fool To Want You
「やれやれですよ。どこからどう見ても刑事にしか見えない暗い顔をした男には、職質だと言われ引っ張られそうになりましたよ」
「岸村という刑事さ。人殺しになった友を追い駆けるために悪徳刑事になった男。裏社会と癒着して友の足取りを調べていると噂された男だよ」
「坊主のような探偵に依頼しに行くと、助手らしい可愛い女の子が写真を視るなり知っているぞと目を蘭々と輝かしているのに、坊主探偵はしゃあしゃあと調査しますと、うすらボケる」
「探偵エンジェルは純粋なんだよ。そんな真っ直ぐなところが気に入って元坊主の探偵七尾は彼女の面倒を見ている」
「胡散臭い爺さんには尾け回されました。そこへボディ・ガードはいらないか?ですから。結託しているに違いないと思いましたよ」
「純爺はね。表は古本屋、この街の生き字引でね、エンジェルは情報屋と呼んでいる。ボディ・ガード屋は通称ソルジャー、元傭兵だ。エンジェルにそそのかされて純爺と組んであんたに近づいたのだろう」
「挙句の果てには怖い顔したやくざ者に囲まれ黒塗りの車から黒いシャツに黒スーツ、黒地のネクタイに赤い薔薇を刺繍した親分が現れた時にはボディ・ガードを雇うべきだったと後悔しました」
「陣野かい?酷い目にあったのかい?」
「いや、かろうじて陣野さんが私の顔を知っていてくれたので助かりました」
「ふうん、ここに辿り着けたということは、桐生さんあんたは危険ではないと判断されたってことだね」
「ここに案内してくれたのは薄汚れた白衣の男と、弁護士だと名乗る男でしたよ」
「愚か者達のオンパレードだね。“ヤブ医者 ”とふざけた看板を上げているけど藪医者は腕のいい外科医だよ。一緒にいたのは藪の親友で正義がない限り弁護を引き受けないという沢村弁護士だ」
あたしは笑った。愚か者達が桐生は安全だと判断したということだ。
桐生は苦笑いを浮かべながら軽く頭を振っている。
「みんな、ママやこの店が大事だってことなんでしょうね」
「何を飲む?」
「実は下戸なのですよ」
と言って桐生は財布の中から一枚のメモを出した。かなり傷んでいる。
広げられたメモを受け取って視た。
「ミラノの恋・・・」
カクテル名とレシピが書かれていた。そうだ、この字は冬木が書いたものだろう。
「私が下戸だと知っていた冬木さんがこれなら飲めると言って作ってくれたカクテルです。分かりますか?」
「分かるさ、あたしが考えたカクテルだから」

ディサローノ・アマレット、レモンジュース、ソーダ水をカウンターに並べた。
グラスに氷を詰めて、ディサローノ・アマレットを四五ml、レモンジュースを二〇mlを入れてソーダでグラスアップ。軽くステア。
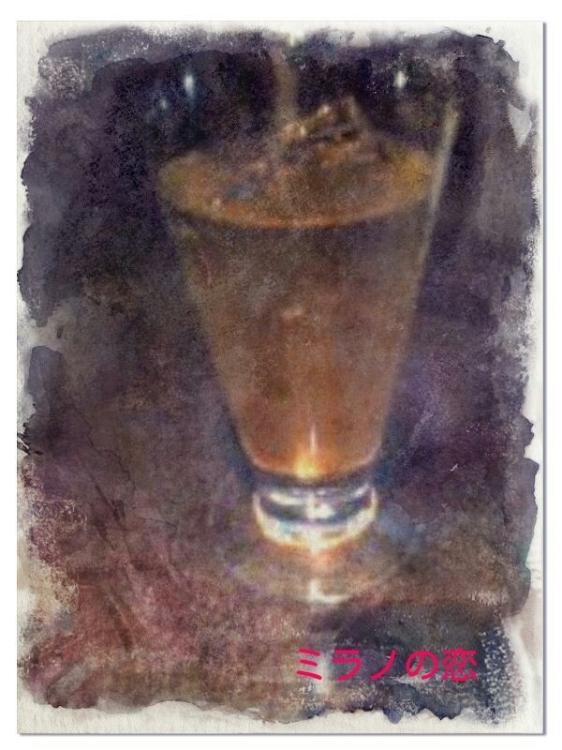
桐生が一口飲んだ。
「ああこれだ。甘味をレモンの酸味が押さえてまるでジュースを飲んでいる様な感じ。これなら下戸の私でも飲める」
桐生は満足気に頷いた。
懐かしい。このカクテルを冬木に教えたことをあたしは想い出した。まだ冬木がここに居た時だった。
「ミラノの恋、このカクテルの名前の謂れはママに聴けと言われました。恥ずかしくて語れないと冬木さんは言っていましたよ」
「だろうねえ。こんな恋愛伝説を冬木が語ったら見ている方が噴き出してしまうよ」
一五二五年、ルネッサンス時代のイタリア、ミラノ北部のサローノ村にあるサンタマリア・デレ・グラツィエ教会の聖堂にキリスト降誕の壁画(フラスコ画)を書くためにベルナディノ・ルイーニという画家が赴いた。ルイーニはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子だと言われている。
「ミラノの北、サローノ町の聖堂で壁画を描く画家ルイーニ。壁画を描く間、ルイーニが滞在した民宿の女主人は、若く美しい未亡人だったそうだ。
『壁画は順調なご様子ですね』
『はい、今夜、聖母マリアを描いて完成です』
精魂込めて壁画を描くルイーニ、それをそっと見つめる女主人
朝、聖母マリアの壁画の前で眠るルイーニ。
そっと完成された壁画を見つめる女主人。
『あぁなんてことでしょう。なんて素敵なマリア』
そこに描かれた聖母マリアは、女主人その人だった・・・」

♪ ピアノの曲が変わった。今夜の最後はボサ・ノヴァ。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
ボサ・ノヴァの創始者ジョアン・ジルベルトの代表作。
「お礼にと彼女が贈ったリキュールが杏子の核を原料したディサローノ・アマレットだった。繊細な優しさに秘密の成分を混ぜて作った琥珀色のリキュール」
桐生は目を閉じてピアノを聴いている。
カシャ と氷が溶けてグラスが鳴った。
「あの日、冬木さんが私をここに呼んだのはママを見せるためだった。あの頃の私はまだ駆け出しの彫り物師でね。師匠は名の知れた人で陣野さんも知っていた。だから、すんなり私はここに来られたのでしょう」
「冬木はあんたの腕を見込んだのだろう」
「精魂込めて彫らせて頂きましたよ。あの絵がなけりゃ、今の私もなかったと思います。彫り物師として自信を持つことが出来た出世作でした」
桐生はグラスを飲み干した。
あたしは同じものを作って桐生の前に置いた。
「なぜ今になって訪ねてくれたのだい?」
「彫り物っていうのは未成年者には彫ってはいけない決まりなんですよ。まあ、あれです。それで捕まってしまった。初犯ではなかったし・・・ちょいとお務めに行くことになりましてね・・・そこで十数年振りに冬木さんの背中を視てしまったんでさあ」
桐生は写真に目を移した。
あたしは桐生を凝視した。“冬木 ”に会った桐生に何か聞かなきゃいけない、でも、何を聞けばいいか分からない。
「元気でしたよ。ママに会ったら伝えてくれと言われました」
桐生が真っ直ぐにあたしの目を視る。
「生きています・・・」
「えっ?」
「生きています・・・と伝えてくれと」
あたしの頬を涙が走った。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
いやらしいくらいマリアの選曲はその瞬間の心を映す。
「生きています・・・」
「はい、それだけ伝えてくれたらいいと」
「生きていりゃあ、それだけでいいさ」
あたしの頬を走る涙は止まらない。生きていれば・・・
「模範囚だそうですよ・・・慰めにもならないかも知れませんが・・・」
無期懲役。帰れるあてなどあるのだろうか・・・
そんなことを考えてはいけないことは知っている。
生きていれば・・・冬木もきっとあたしと同じことを考えている。
『ぶれない愛を貫くママだから、愚か者達を引き寄せるの』
いつだったか、マリアのピアノが言った言葉。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
真夏の夕暮れに風が吹き、昼間の熱い陽射しを思い出すような感覚、それをブラジルでSAUDADE(サウダージ)という。
ブラジルのピンガと呼ばれるカサーシャ51はラムと同じようにサトウキビから作る蒸留酒だが、ラムほど精錬されてなくて雑味が残っていて人間くさい。あたしはそんなカサーシャ51とライムジュースに真っ赤なグレナデンシロップを少々、それを氷ごとジューサーでミキシング。まるで大人のかき氷だ。これなら桐生にも飲めるだろう。
私はオールド・ファッションド・グラスを二つ用意してジューサーの中身を注いだ。一つを桐生の前にスプーンを添えて出した。
「SAUDADE(サウダージ)、あたしは、失くした時間、と訳してみた」
「あぁ美味しい。妙に懐かしい味がします」
カウンターに置かれた一枚の写真。
冬木の背中に彫られた絵。
あたしの顔をした聖母マリア。
冬木の背中にあたしがいると想った瞬間、あたしはあたしの中の “女 ”が疼くのがわかった。
冬木は灯りの下であたしに背中を見せたことはなかった。二度と戻らない覚悟であたしを抱いたあの日の最後の夜も。
あたしはSAUDADEをスプーンですくった。口に含んだ。氷が溶けるように懐かしい想いが溢れて来た。
火照った体を静めるのに外に出たいと思った。
渇いた心が真夜中に吹く風を求めていた。
ここは、Foolという名のBar
愚か者が静かに酔い潰れるための店。
Chega de Sudade (想いあふれて)
JOAO GILBERTO(ジョアン・ジルベルト)
悲しみさん
彼女に言ってやってくれないか
おまえなしでは駄目なんだと
お願いだから 戻って来てくれと
僕は生きられないよ
思い出はもうたくさん
彼女なしでは 心の平和はあり得ない
この世にどんな美もあり得ない
それにしても 終わりがないのは
僕の中に巣くっている
この悲しみ この憂欝
でも 彼女が帰ってきてくれるなら
ああ こんなすばらしいことはない
海に泳ぐ魚の数よりも
もっとたくさんのキスをして
この両腕にしっかりと 彼女を抱きしめて
なにも言わずに その身体の温もりを
深く深く 吸い込むだろうに
あきるほど抱擁し キスをして
愛撫の雨を降らせてやれるのに
そんな生き方はさせないよ
僕と離れて生きるなんて
独りになど させておいたりしないのに
そんな生き方はやめるんだ
僕と離れて生きるなんて
ここは、愚か者が静かに酔い潰れるための店
今宵もまた一人、愚か者が紛れ込んで来る。
「おかしな街ですね、ここは」
その男はあたしの顔を見てホッとしたような顔をした。
「何かありましたか?」
あたしはおしぼりを渡しながら男を観察した。
記憶の隅に引っ掛かる。あたしはこの男に会ったことがあると感じた。
「いきなりね、若い頃のシルベスター・スタローンのような男にボディ・ガードを雇えよと押し売りされたのですよ」
この男は愚か者達が騒いでいた、あたしを探す男だった。
この街に異物が混入されると愚か者達が騒ぎだす。この店の常連客達だ。
特にこの男は、あたしの顔らしき絵が描かれた写真を持ってこの街を歩いた。
『命がいくつあっても足りない奴だ』
と愚か者達が動き出した。
「あんたかい?あたしに似た女の絵を写真に撮って街を歩いていたのは?」
男はブレザーのポケットから写真を出してカウンターに置いた。
写真の女の顔、確かにあたしだ。でも着ている服はとんでもない、あたしなどではない。
「聖母マリアですよ、これは。でも顔はあなただ、あなたをモデルにした」
あたしは笑うしかなかった。
「私は桐生という者です。昔、一度だけここに来たことがあります。冬木さんに呼ばれてね」
あたしの記憶の中に桐生の顔が浮上して来る。
「でも、あの時のあんたは若い、とても若かったね」
「ええ、まだ駆け出しの彫り物師でしたからね。この写真は冬木さんの背中です。私が彫りました」
あたしは動揺を必死に押さえた。
「知らない?抱かれたことがない?これを見たことがないってことは」
冬木の背中にあたしがいた。
「闇の中にしか居なかったからね、あの頃は」
そこまで言うのが限界だった。あたしは喉がカラカラに渇いていた。
♪ ピアノ
救いのようにマリアのピアノ。
♪ I'm A Fool To Want You
「やれやれですよ。どこからどう見ても刑事にしか見えない暗い顔をした男には、職質だと言われ引っ張られそうになりましたよ」
「岸村という刑事さ。人殺しになった友を追い駆けるために悪徳刑事になった男。裏社会と癒着して友の足取りを調べていると噂された男だよ」
「坊主のような探偵に依頼しに行くと、助手らしい可愛い女の子が写真を視るなり知っているぞと目を蘭々と輝かしているのに、坊主探偵はしゃあしゃあと調査しますと、うすらボケる」
「探偵エンジェルは純粋なんだよ。そんな真っ直ぐなところが気に入って元坊主の探偵七尾は彼女の面倒を見ている」
「胡散臭い爺さんには尾け回されました。そこへボディ・ガードはいらないか?ですから。結託しているに違いないと思いましたよ」
「純爺はね。表は古本屋、この街の生き字引でね、エンジェルは情報屋と呼んでいる。ボディ・ガード屋は通称ソルジャー、元傭兵だ。エンジェルにそそのかされて純爺と組んであんたに近づいたのだろう」
「挙句の果てには怖い顔したやくざ者に囲まれ黒塗りの車から黒いシャツに黒スーツ、黒地のネクタイに赤い薔薇を刺繍した親分が現れた時にはボディ・ガードを雇うべきだったと後悔しました」
「陣野かい?酷い目にあったのかい?」
「いや、かろうじて陣野さんが私の顔を知っていてくれたので助かりました」
「ふうん、ここに辿り着けたということは、桐生さんあんたは危険ではないと判断されたってことだね」
「ここに案内してくれたのは薄汚れた白衣の男と、弁護士だと名乗る男でしたよ」
「愚か者達のオンパレードだね。“ヤブ医者 ”とふざけた看板を上げているけど藪医者は腕のいい外科医だよ。一緒にいたのは藪の親友で正義がない限り弁護を引き受けないという沢村弁護士だ」
あたしは笑った。愚か者達が桐生は安全だと判断したということだ。
桐生は苦笑いを浮かべながら軽く頭を振っている。
「みんな、ママやこの店が大事だってことなんでしょうね」
「何を飲む?」
「実は下戸なのですよ」
と言って桐生は財布の中から一枚のメモを出した。かなり傷んでいる。
広げられたメモを受け取って視た。
「ミラノの恋・・・」
カクテル名とレシピが書かれていた。そうだ、この字は冬木が書いたものだろう。
「私が下戸だと知っていた冬木さんがこれなら飲めると言って作ってくれたカクテルです。分かりますか?」
「分かるさ、あたしが考えたカクテルだから」

ディサローノ・アマレット、レモンジュース、ソーダ水をカウンターに並べた。
グラスに氷を詰めて、ディサローノ・アマレットを四五ml、レモンジュースを二〇mlを入れてソーダでグラスアップ。軽くステア。
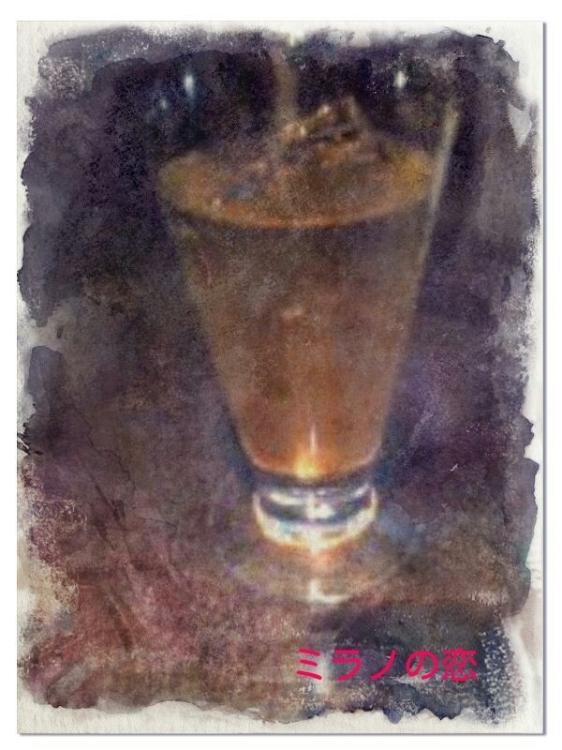
桐生が一口飲んだ。
「ああこれだ。甘味をレモンの酸味が押さえてまるでジュースを飲んでいる様な感じ。これなら下戸の私でも飲める」
桐生は満足気に頷いた。
懐かしい。このカクテルを冬木に教えたことをあたしは想い出した。まだ冬木がここに居た時だった。
「ミラノの恋、このカクテルの名前の謂れはママに聴けと言われました。恥ずかしくて語れないと冬木さんは言っていましたよ」
「だろうねえ。こんな恋愛伝説を冬木が語ったら見ている方が噴き出してしまうよ」
一五二五年、ルネッサンス時代のイタリア、ミラノ北部のサローノ村にあるサンタマリア・デレ・グラツィエ教会の聖堂にキリスト降誕の壁画(フラスコ画)を書くためにベルナディノ・ルイーニという画家が赴いた。ルイーニはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子だと言われている。
「ミラノの北、サローノ町の聖堂で壁画を描く画家ルイーニ。壁画を描く間、ルイーニが滞在した民宿の女主人は、若く美しい未亡人だったそうだ。
『壁画は順調なご様子ですね』
『はい、今夜、聖母マリアを描いて完成です』
精魂込めて壁画を描くルイーニ、それをそっと見つめる女主人
朝、聖母マリアの壁画の前で眠るルイーニ。
そっと完成された壁画を見つめる女主人。
『あぁなんてことでしょう。なんて素敵なマリア』
そこに描かれた聖母マリアは、女主人その人だった・・・」

♪ ピアノの曲が変わった。今夜の最後はボサ・ノヴァ。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
ボサ・ノヴァの創始者ジョアン・ジルベルトの代表作。
「お礼にと彼女が贈ったリキュールが杏子の核を原料したディサローノ・アマレットだった。繊細な優しさに秘密の成分を混ぜて作った琥珀色のリキュール」
桐生は目を閉じてピアノを聴いている。
カシャ と氷が溶けてグラスが鳴った。
「あの日、冬木さんが私をここに呼んだのはママを見せるためだった。あの頃の私はまだ駆け出しの彫り物師でね。師匠は名の知れた人で陣野さんも知っていた。だから、すんなり私はここに来られたのでしょう」
「冬木はあんたの腕を見込んだのだろう」
「精魂込めて彫らせて頂きましたよ。あの絵がなけりゃ、今の私もなかったと思います。彫り物師として自信を持つことが出来た出世作でした」
桐生はグラスを飲み干した。
あたしは同じものを作って桐生の前に置いた。
「なぜ今になって訪ねてくれたのだい?」
「彫り物っていうのは未成年者には彫ってはいけない決まりなんですよ。まあ、あれです。それで捕まってしまった。初犯ではなかったし・・・ちょいとお務めに行くことになりましてね・・・そこで十数年振りに冬木さんの背中を視てしまったんでさあ」
桐生は写真に目を移した。
あたしは桐生を凝視した。“冬木 ”に会った桐生に何か聞かなきゃいけない、でも、何を聞けばいいか分からない。
「元気でしたよ。ママに会ったら伝えてくれと言われました」
桐生が真っ直ぐにあたしの目を視る。
「生きています・・・」
「えっ?」
「生きています・・・と伝えてくれと」
あたしの頬を涙が走った。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
いやらしいくらいマリアの選曲はその瞬間の心を映す。
「生きています・・・」
「はい、それだけ伝えてくれたらいいと」
「生きていりゃあ、それだけでいいさ」
あたしの頬を走る涙は止まらない。生きていれば・・・
「模範囚だそうですよ・・・慰めにもならないかも知れませんが・・・」
無期懲役。帰れるあてなどあるのだろうか・・・
そんなことを考えてはいけないことは知っている。
生きていれば・・・冬木もきっとあたしと同じことを考えている。
『ぶれない愛を貫くママだから、愚か者達を引き寄せるの』
いつだったか、マリアのピアノが言った言葉。
♪ Chega de Saudade(想いあふれて)
真夏の夕暮れに風が吹き、昼間の熱い陽射しを思い出すような感覚、それをブラジルでSAUDADE(サウダージ)という。
ブラジルのピンガと呼ばれるカサーシャ51はラムと同じようにサトウキビから作る蒸留酒だが、ラムほど精錬されてなくて雑味が残っていて人間くさい。あたしはそんなカサーシャ51とライムジュースに真っ赤なグレナデンシロップを少々、それを氷ごとジューサーでミキシング。まるで大人のかき氷だ。これなら桐生にも飲めるだろう。
私はオールド・ファッションド・グラスを二つ用意してジューサーの中身を注いだ。一つを桐生の前にスプーンを添えて出した。
「SAUDADE(サウダージ)、あたしは、失くした時間、と訳してみた」
「あぁ美味しい。妙に懐かしい味がします」
カウンターに置かれた一枚の写真。
冬木の背中に彫られた絵。
あたしの顔をした聖母マリア。
冬木の背中にあたしがいると想った瞬間、あたしはあたしの中の “女 ”が疼くのがわかった。
冬木は灯りの下であたしに背中を見せたことはなかった。二度と戻らない覚悟であたしを抱いたあの日の最後の夜も。
あたしはSAUDADEをスプーンですくった。口に含んだ。氷が溶けるように懐かしい想いが溢れて来た。
火照った体を静めるのに外に出たいと思った。
渇いた心が真夜中に吹く風を求めていた。
ここは、Foolという名のBar
愚か者が静かに酔い潰れるための店。
Chega de Sudade (想いあふれて)
JOAO GILBERTO(ジョアン・ジルベルト)
悲しみさん
彼女に言ってやってくれないか
おまえなしでは駄目なんだと
お願いだから 戻って来てくれと
僕は生きられないよ
思い出はもうたくさん
彼女なしでは 心の平和はあり得ない
この世にどんな美もあり得ない
それにしても 終わりがないのは
僕の中に巣くっている
この悲しみ この憂欝
でも 彼女が帰ってきてくれるなら
ああ こんなすばらしいことはない
海に泳ぐ魚の数よりも
もっとたくさんのキスをして
この両腕にしっかりと 彼女を抱きしめて
なにも言わずに その身体の温もりを
深く深く 吸い込むだろうに
あきるほど抱擁し キスをして
愛撫の雨を降らせてやれるのに
そんな生き方はさせないよ
僕と離れて生きるなんて
独りになど させておいたりしないのに
そんな生き方はやめるんだ
僕と離れて生きるなんて

