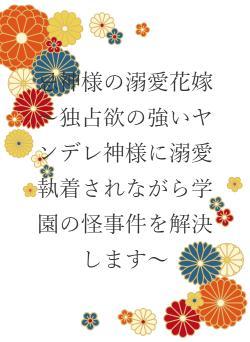「だから……だからその可愛い顔をこっちに向けるな!」
「はいぃッ?」
男は顔を真っ赤にしながらキレていた。
女も顔を真っ赤にしながら驚いていた。
初対面、今から離婚する二人は、どちらも照れた顔で向き合っていた。
◆◇◆
桜の花びらが舞い始めた春の頃。
そんな季節に相応しい縁談が、斎賀家を賑わせていた。
斎賀家といえば、政治家から財閥、華族までが御用達の料亭であり、その由緒は江戸時代までさかのぼると言われている。
更に国があやかしとの交流を解禁した昨今では、名立たるあやかしたちが舌鼓を打っているほど、斎賀家は上流階級に好まれる料亭であった。
現在の斎賀家本家の構成は、当主となる父と、一男三女の子供たち。
跡取りとなる長男と、長女、次女は非常に才能豊かで、大人でも難しいとされる料亭の品々を難なく仕上げられるほどである。
だが、唯一末の三女だけは違った。
料理の基礎ぐらいはできるが、際立ったセンスがあるわけでもなければ、器量が良いわけでもない。レシピを見ながらならば家庭料理をこなせるぐらいで、場合によってはその辺りの主婦の方がずっと手際が良いぐらいであった。
そんな三女――蜜夏のことを、斎賀家の誰もが出来損ないとして扱っていた。
何の期待も持たず、家の邪魔だけはするなと言わんばかりの無関心さで、蜜夏は十六年間ずっと放っておかれ続けた。
だから蜜夏も、自分は斎賀家のお荷物だと思いながら、ただひそやかに暮らしていた。
突然の縁談がやって来るまでは。
***
「どういうことですのお父様!」
普段はおしとやかな令嬢として社交界を我が物顔にしている長女の愛華が、らしくもなく声を上げていた。
隣に座る次女の姫香も、納得がいかないといった顔で不貞腐れている。
その向かい側に座る長男の桃火は腕を組み、上座に座る父にして当主――峰近は顎髭を撫でていた。
「どうして私と姫香を飛ばして、蜜夏が結婚って話になるのよ!」
愛華はすでに十八を迎えており、姫香も十七になった。
斎賀家で手塩に掛けて育てられた麗しの令嬢たちに、これまでもそれなりに縁談の話は来ていた。
だがどれも当主の峰近が弾いており、こうして家族会議に挙げられるような縁談は初めてのことだった。
しかもその縁談の相手……いやそれどころか結婚の相手が、出来損ないのみそっかすである蜜夏なのだから、愛華が声を上げるのも無理はない。
一人だけ部屋の端で立ったままの蜜夏は、予想外の結婚話に驚きつつ、愛華を刺激しないよう顔を伏せていた。
「まあ待て愛華。落ち着け」
「でもお父様……」
「相手は人間ではない。あやかしだ」
その瞬間、室内の空気が一変した。
これまで殺気立っていた愛華たちが気の抜けたような表情を浮かべ、代わりに蜜夏は目を見開き口元に手を当てる。
峰近は、蜜夏の方を真っ直ぐ向きながら話し始めた。
「竜宮童子を知っているか? こちらが『捧げもの』をすれば巨万の富と家の繁栄を与えてくれる一方で、竜宮童子自体は醜い姿になっていくというあやかしだ」
「社交界で懇意にしているあやかしからそんな話は聞いたことがありますわ。確か、富と繁栄の代わりに、竜宮童子自身は醜くなっていくのだとか」
「ああその通りだ。言い伝えでは、この醜くなった竜宮童子を家から追い出してしまった所為で元の貧乏になる……という話らしい」
そこまで峰近が言い、愛華は何かを思いついた表情になる。
「けれど醜くなった竜宮童子と未来永劫添い遂げれば……」
「……斎賀家の繁栄は約束されたものになるな」
長男の桃火が、ポツリと呟いた。
途端に次女の姫香が愛らしい表情で言葉を続ける。
「なぁるほど。醜いあやかしの旦那様は、蜜夏に担当してもらって、斎賀家の繁栄を永遠にもたらしてもらうってことですわね」
あまりにも身勝手なことを、何てことはないように彼らは話している。
蜜夏は、その内容に耳を塞ぎたい気持ちであった。
「それにどうも、先方は蜜夏を指名してきたんだ。これ以上無い流れだと思わないか」
「あらぁ、蜜夏も隅に置けないわね。竜宮家の御曹司さんからご指名だなんて」
クスクスと愛華の嘲笑う声が聞こえ、蜜夏はますます顔を伏せた。
何故、向こうから指名してきたのかは知らないが、そもそも蜜夏は十六歳を迎えた今、家を出ようと考えていたのだ。
この家にいても自分の居場所は無いし、お荷物になるだけ。
だったら家を出て自立してしまった方が、斎賀家のためにも自分のためにもなる。
そう思っていたのに。
「ま、待ってください。私そんな……会ったこともない人と結婚だなんて……」
「蜜夏」
圧のある峰近の声音に、蜜夏は体を縮こませる。
「これはもう決まった結婚話だ」
「そんな……だって、顔も知らない相手なんて……」
「先方はお忙しい身なんだろ。今はおまえに会えないと言っていたが、その時はいずれ来るんだ。それまでおまえは良き妻として黙って待っていればいい」
「富をもたらす代わりに醜くなるあやかしなんでしょ? 会う時はあまり顔の期待はされない方がいいんじゃないかしら」
姫香の笑い声も、どこか遠いところから聞こえてくるようだった。
(こんな勝手に……なんで、どうして……)
せっかくコツコツとお金も貯めていたのに、これでは計画が全て水の泡だった。
自分の意思など何一つ尊重してくれていないこの結婚に、蜜夏は強い憎しみを抱いた。
(そもそも、お父様は家の繁栄を目的としていて、先方に対しても失礼だわ。だったら……)
蜜夏は、一人決意する。
(竜宮童子さんにそのことをお話して、離婚してしまおう!)
それが自分を虐げてきた斎賀家への、最初で最後の反抗だと、蜜夏は密かに心に誓うのだった。
◆◇◆
そうして、変わらぬ日々が過ぎ去りながらも、裏では着々と結婚話が進行していった。
蜜夏にとって謎だったのは、自分を指名してきたことと、その割に一度も挨拶に来ないことである。
話によると、蜜夏のことを以前見かけたことがあるらしく、それをきっかけに結婚の申し入れへと至ったらしい。
だが蜜夏からすれば相手のことなど全く知らないため、本当に一方的な結婚でしかない。
更に色々と話を聞いたところ、昔話の言い伝えで出てくる竜宮童子の末裔となる男が結婚相手らしく、彼もまた有名な高級レストランを運営する竜宮グループの会長をしているのだとか。
そのため、すでに一部の紙面では『料理界を賑わせる大物カップル登場か!』などという文字が一面を飾っていた。
(すぐに離婚するんだから、あんまり騒がないでほしいなぁ……)
新聞を広げながら、蜜夏はため息を吐く。
(竜宮童子さんだって、自分の力目当てだって知れば離婚したくなるだろうし。世間が盛り上がってくれても、肩透かしに終わるだろうけどね)
「蜜夏。こんなところで何をしている」
突如、背後から長男の桃火に声をかけられ、蜜夏は弾かれるように立ち上がった。
同じ斎賀家の子供でありながら、蜜夏は使用人のように背筋を伸ばし、桃火の方を向く。
「お兄様……」
「おまえ、話を聞いていなかったのか?」
「え?」
「今日これから、竜宮童子と会う話だっただろうが」
「えっ!」
正直言って初耳であったが、実はこういったことが何度もあった。
というのも、使用人の中にも蜜夏を虐げたり、雑な扱いをしたりする連中が一部いるのだ。
その所為で、こういったいやがらせにより、連絡や報告が行き届いていない場面がこれまでも起こっていた。
だからきっと今回も、どこぞの使用人がわざと伝えてくれなかったのだろう。
「斎賀家の恥さらしが。とっとと支度しろ」
「は、はい。申し訳ありません」
蜜夏は急いで部屋を出た。
自室に帰ったら、子供の時から良くしてくれている使用人が、改めて今日の予定のことを教えてくれた。どうやら彼女もそのことをさっき知ったらしく、慌てて駆け付けてくれたというわけだ。
なので彼女の手を借り、急いで着物を着つけ、ヘアメイクをセットする。
「本日が初体面となるのでしょう? しっかり気合いを入れませんとね」
「う、うん」
使用人に髪をとかされながら、蜜夏は頷く。
しかし胸中にあるのは、初対面の挨拶と共に離婚を申し立ててやるという覚悟だった。
***
支度を終えて家を出ようとした蜜夏は、先方が迎えに寄越してくれたリムジンに乗せられ、竜宮グループの経営するレストランが入ったホテルへと案内された。
都市部でもとくに選ばれた人しか泊まることのできないハイクラスなそのホテルへ到着すると、今度は竜宮家の使用人と思われる人たちが数人、蜜夏を丁寧にもてなし、エスコートしてくれる。
斎賀側の使用人とは入り口で分かれたため、蜜夏は単身でホテルへと足を運ぶこととなった。
「こちらのお部屋でお待ち下さい」
普段はお偉いさんが会議などで使うのであろう談話室に通された蜜夏は、居心地の悪さを感じながらソファに腰をかけた。
斎賀家ではこんなにも丁寧に扱われたことがないため、どう対応すればいいのかわからないところがある。
今日だって出来得る限りのおめかしはしてきたが、こんなにも立派な部屋に通されるとは思っておらず、今にも気後れしてしまいそうだった。
(えぇい、弱気になっちゃ駄目よ。離婚よ、離婚。はじめましてこんにちは離婚しましょう。これぐらいスムーズに離婚を切り出さなきゃいけないんだから)
蜜夏はギュッと拳を握る。
(だいたい勝手に結婚を取り付けておいて、一回も顔を合わせに来なかったんだから、それだけでも離婚の理由になると思うのよね。会う暇も無いほど忙しいなら、なんで結婚なんてしたのかしら)
そうこうしている内に、ノック音と共に扉の開く音が聞こえ、蜜夏は顔を上げる。
「失礼いたします。竜宮永礼様がお着きになりました」
側近と思われるお年を召した使用人が頭を下げてそう告げると共に、後ろから一人の男が入室してくる。
後ろで一つに結われた青黒く輝く髪の毛。肌は透き通るほどに白く、その切れ長の瞳は深海のような濃い青色を見せている。
竜宮童子は富や繁栄をもたらす代わりに醜い姿になるらしいが……彼はまだその力を使っていないからなのか、とてつもない美男子がそこに居た。
和装をキッチリと着こなした長身のその美男子――永礼は、一度だけ蜜夏の方を見るとすぐに目を反らした。
「榊、下がっていいぞ」
「……ですが坊ちゃま」
「下がれと言っている」
「失礼いたしました」
榊と呼ばれた使用人は、すぐに引き下がり、音も無く部屋から退室していった。
残された永礼と蜜夏の間に、何とも言えない沈黙が漂う。
「………」
「………」
蜜夏は目の前に座る永礼の方を見ているが、永礼は蜜夏の方を見ず、やはり明らかに視線を反らしている。
(顔も見たくないってこと? そんな人となんで結婚したのかしら……)
この永礼という男のことがまるでわからないが、とにかくこのまま沈黙が続いても困るだけなので、度胸のまま蜜夏は口を開いた。
「あの、初めまして。斎賀蜜夏と申します」
「……竜宮永礼だ」
「えっと……私と結婚された永礼様で、お間違い無いですか?」
「ああ」
ぶっきらぼう、という言葉が実に相応しいほど、永礼からの返答は最低限だった。
話を広げる気も感じられず、言葉のキャッチボールがまるでできない。
「お伺いしたいのですが、どうして私と結婚をされたのですか?」
「………」
「こう言うのもなんですが、私は斎賀家ではお荷物のような存在です。料理の腕も無ければ器量も良くありません。ですから……」
ですから離婚はどうでしょう、と、そう提案してみようとした矢先。
「……向けるな」
「え?」
突然、永礼が割って入ってきた。
だが肝心な部分が聞き取れず、蜜夏は思わず首を傾げる。
「今なんと仰って……」
「だから……だからその可愛い顔をこっちに向けるな!」
「はいぃッ?」
永礼の真っ白な肌はわかりやすいほど真っ赤に染まっていた。
一方、予想外のことを言われた蜜夏もまた、顔を赤く染めていた。
一体全体、いきなりなんなんだ、と。
蜜夏がパニックになる前に、扉が勢いよく開かれた。
「斎賀様、大変失礼いたしました!」
先程退出したはずの榊が、扉を開けた勢いのまま入室し、流れるような所作で永礼の隣に立ち頭を下げる。
「え、え、えーと」
「やはり駄目じゃないですか坊ちゃま」
「うるさい榊」
永礼は榊の方を見てバツが悪そうにそう告げる。途中、一度だけ蜜夏と目が合ったが、やはりすぐに顔を背けてしまう。
困惑するしかない蜜夏の心境を察しているように、榊は一歩前へ出て説明し始めた。
「斎賀様、誤解を招いてしまいましたら大変失礼いたしました。坊ちゃま……永礼様は極度の恥ずかしがり屋ゆえ、このような態度を取ってしまわれるのです」
「榊!」
永礼から声が上がったが、榊は華麗にスルーして言葉を続ける。
「永礼様はそれはもう斎賀様のことを好いております。忙しさと恥ずかしさでなかなか会いに行くことすらできないにも関わらず、斎賀様が他の馬の骨に盗られてしまわぬよう、何が何でもという意気込みで結婚だけを先に済ませてしまうほど、永礼様は斎賀様が好きでたまらないのです」
「榊もうやめろ!」
真っ赤な顔を手で押さえつつ、永礼は悲鳴に近い声を上げた。
一方、蜜夏はただただ呆気に取られるばかりだった。
とはいえわかったことは、本当に永礼は照れ屋で、そしてこの結婚に対して本気だということだ。
政略結婚、または料理界の発展のため、それとも長女や次女と相手を間違えた……それぐらいまで考えていたのに、永礼のその態度と榊の弁明を前にしたら、そんな考えも馬鹿らしいほど真っ直ぐな気持ちを向けられてしまった。
つられるように、蜜夏もまた顔が赤くなっていることに気が付いた。
「あの、その……一つ、お伺いしたいのですが……」
「なんだ」
ぶっきらぼうな態度は変わらず、ただし顔を真っ赤にしたまま永礼は腕を組んでチラチラと蜜夏の方を見る。
「どうして私なんですか? お会いしたこと、ありましたでしょうか……」
一番の疑問がそこだった。
この結婚が本気のものだとすると、むしろそこがわからない。
しばらく黙って永礼の方を見ていると、永礼はその綺麗な顔を苦悩するように歪ませつつ、渋々と口を開いた。
「数年前に、料理人同士の交流会が、あっただろ」
言われて真っ先に思い出したのは、十歳ぐらいの時に行われた斎賀家主催の交流会だ。
料理界の重鎮から新進気鋭の若者たちまでが集まり、その場で料理を振る舞ったり意見を交換したりする会が過去にあった。
「あの時……み、蜜夏は……俺ににぎりめし、くれただろッ?」
「え……」
言われて蜜夏は必死に記憶をたどる。
確かあの会でも、斎賀家の邪魔にならないよう会場の隅っこに追いやられていて。
ただ、みんなが料理を披露する日だと聞いていたから、頑張っておにぎりを作っていて。
だけどそんなもの斎賀家の恥になるから捨てろと言われて。
それで泣く泣く捨てようとした時に……
「あ!」
そこで蜜夏は思い出す。
ゴミ箱の前で泣いていた蜜夏に、男の子が声をかけてきたのだ。
何を話したかまでは覚えていないが、男の子はお腹が空いているとかで、持って来たおにぎりを全部食べてくれたことは覚えている。
「まさか……あの時の?」
「………」
真っ赤な顔のまま一つ頷く永礼を見て、蜜夏は口を開けたまま固まってしまう。
だって、十年も前の……お互い子供の時のことだ。
あの出会いをきっかけに、永礼は結婚まで考えたということになると……その思いは相当のものである。
そんな蜜夏の驚きをフォローするように、永礼は顔を背けながら話し始めた。
「あの時のにぎりめしは、俺にとってあの会場のどのご馳走よりも美味かった。俺たち竜宮童子の一族にとって、『捧げられたモノ』の価値はでかいんだ。だからあの時、蜜夏がくれたにぎりめしは俺にとって最上級の『捧げもの』だったし、何より……」
「……何より?」
「す……」
「す?」
「凄く可愛かったんだよ、蜜夏が!」
逆ギレでもするかのような馬鹿でかい声で、そんな恥ずかしいことを永礼は言ってくる。
黙っていればクールな美男子だというのに、蜜夏にはもうそんな印象を永礼には持てないぐらいだった。
「えーと……あ、ありがとうございます」
照れながらも、蜜夏はお礼を言う。
思えば、こんなにも褒められたり好意を持たれたりするのは初めてかもしれない。
亡き母も、他の兄姉たちばかり可愛がっていたのだから。
しかしこうなってくると、当初予定していた離婚の話が切り出しにくくなってきた。
まさかこんなにも強く真っ直ぐな好意を抱かれているとは……予想外すぎた。
「永礼さん、あの……お気持ちは凄く嬉しいんですけど……」
「そうか」
「でも私、離婚しようと思っていて……」
「な、なんだとッ?」
勢いよく永礼が立ち上がり、テーブルがガタンッと揺れた。
傍にいた榊がすぐに卓上のものを元の位置に戻す早わざを見せていたが、それよりも圧のある永礼から目が離せなかった。
「離婚……離婚だとッ? な、何が不満だ? 俺のことが嫌いかッ?」
「いえ、嫌いとかそういうことではないんですけど……」
「だったらどうして……。お、俺は嫌だ! 離婚なんて絶対したくない!」
普段、絶対他の人には見せないであろう子供のようなその姿に、蜜夏はちょっとばかり母性本能が疼いてしまった。
とんでもない美男子が、ある意味カッコ悪いほどに取り乱しながら、真っ直ぐに好意を向けてくる。それを何とも思わないほど蜜夏もひねくれてはいない。
ただ、彼と結婚してしまうと、ますます家族から離れにくくなってしまう。
だからきちんと理由を説明しなければと、蜜夏は口を開いた。
「あの……」
そこまで言いかけ、言葉が出なくなってしまう。
いざ家のことを口にしようとしたら、なんだか上手く話せない。
長いこと自分の境遇を必死に受け入れてきた所為か、そのことを本当は辛かったことだと客観的に説明しようとすればするほど、どんどん言葉が詰まってしまった。
「……蜜夏?」
様子がおかしいからか、永礼がそれまで見せていた態度とは一変し、心配した様子で蜜夏を見ている。
しばらく沈黙が続いた。
何か話さなければと焦れば焦るほど言葉が出ない。
すると、永礼が立ち上がり、蜜夏の隣に腰掛けた。
さっきまでの照れた様子が嘘のように、真剣な眼差しで蜜夏を見ている。
「無理に話す必要は無い。ただ、もし離婚の原因が俺にあるなら……絶対に直すから」
優しい声音だった。
誠実で、信頼を感じられるその物言いに、蜜夏は思わず泣きそうになってしまう。
「ち、違うんです……永礼さんには何の非も無くて……」
「本当に?」
「はい」
「そうか。蜜夏がそう言うなら信じよう」
「……っ」
そんなこと、今まで家族からも言われたことが無かった。
何を言っても聞いてもらえず、時には兄姉たちの嘘の方を信じられてしまうことも多々あった。
なのに彼は話を聞き、そして信じてくれた。
「永礼さん、私……」
顔を上げ、永礼の方を向いた瞬間、蜜夏の瞳からポロリと涙が零れる。
途端に慌てたのは、蜜夏ではなく永礼の方だった。
「なっ、なんだッ? ど、どうした! どこか痛いのか? それとも何か嫌だったのかッ?」
「ち、違います違います」
「違うものか、泣いているじゃないか! な、泣いている顔も可愛いが……いや違う! なんで泣いてるんだ! 平気か?」
とてつもなく慌てふためく永礼の姿がおかしくて、蜜夏は涙に続いて笑顔も零した。
「永礼さん、あの……ありがとうございます」
「えぇ……?」
何が何だかわからないといった様子の永礼は、しかし微笑を浮かべる蜜夏を真正面から見て、すぐに真っ赤になっていた。
「その……私が離婚を考えている理由とは別なのですが」
「な、なんだ?」
「斎賀家が今回の結婚を承諾した理由は、竜宮童子の力を狙ってのものなんです」
「ああ」
思ったよりも永礼の反応は小さく、むしろそんなことかと言った感じの気の抜けた声だった。
蜜夏は一人、首を傾げる。
「とても失礼なことだと思ったんですけど……」
「そうか? その代わり俺は蜜夏という最上級の『捧げもの』をもらえるのだから、むしろお釣りが来るぐらいだな」
あまりにも熱烈なことをさらっと言われ、蜜夏は顔に熱がこもるのを感じた。
「ああ、そういえば」
そこで永礼は思い出したように話し始める。
「富や繁栄の代わりに俺が……竜宮童子が醜くなるというのは、あくまで欲深き者を戒めるための言い伝えに過ぎない」
「そうだったんですか」
「だからもし蜜夏がそこを気にしているなら……」
「全然気にしていませんでしたよ。それにもしそうなったとしても私は……」
そこまで言いかけ、蜜夏はハッと我に返る。
続きは、一体何と言うつもりだったのだろうか。
知らず知らずのうちに、永礼に対し好意を抱いていることに気が付いた蜜夏は、自分自身の感情に慌てふためいた。
一方、蜜夏からの反応が良かったことが嬉しかったのか、永礼はこっそりと小さくガッツポーズを決めていた。
「蜜夏。良ければ、今日はこのまま……で、デートとかしないか?」
「えっ」
思いがけぬ提案に、蜜夏は目を丸くしてしまう。
離婚を考えている相手と、デート。
なんだかあまりにも矛盾している気がしたが……しかし目の前の永礼が、顔を赤くしながら真っ直ぐとこちらを見つめてくるものだから……
「し……しましょう、デート」
蜜夏は小さく頷いた。
そんな蜜夏の返答を受けた永礼は、明らかに嬉しそうな満面の笑みを浮かべる。
「良かったですね坊ちゃま。ではデートコースの手配をさせて頂きます」
突如、割って入った冷静な榊の声。
そこで二人は、榊がずっとこの部屋にいたことを思い出し、色々な意味でお互いに顔を真っ赤にするのだった。
***
デートコースは、今いるホテルの中を巡ることになった。
この竜宮グループの経営するホテルの目玉は、何といっても当人たちが腕によりをかけた一流レストランであるが、その他にもショッピングモールやカフェラウンジ、更には水族館といった施設が設けられていた。
まず二人が向かったのは女性向けのファッションブランド店だった。しかも、どちらかといえば、蜜夏よりも永礼の方が乗り気で先頭に立って中に入っていく。
「こ、こんな立派なところで洋服なんて買ったことないですよ。それに私には到底似合うと思いませんし……」
永礼を引き留め、慌てて店を出ようとする蜜夏だったが、永礼はビクともしなかった。
「蜜夏ならどんな服でも似合うし、この店はそこらの店とは違うハイブランド店だ。客である蜜夏に似合わない服を選んできたら、速攻このホテルから追い出してやる」
「なんて物騒な」
なんとも横暴な永礼に呆れつつ、気付けば複数の店員が近付いていたことに気が付く。
どの店員さんも、スマートに従業員服を着こなしている。
「永礼様、お越しいただきありがとうございます。今回はどういったご用件でしょうか」
「こちらの……俺の……俺の妻の、蜜夏の服を……み、見立ててやってくれ」
恥ずかしさからか所々つかえながら、永礼は咳払いと共にそう言い切った。
途端に、従業員たちは笑顔で蜜夏の方を向く。
「承知いたしました。さ、こちらへどうぞ」
「え、え?」
「まずは採寸から失礼いたします。そのあと好きなお色、パーソナルカラーのチェックなどをして、お洋服をお選びさせて頂きますね」
「え、え、えぇ?」
説明を受けながら蜜夏は、あれよあれよという間にフィッティングルームへと連れて行かれていた。
「永礼様が女性をお連れするのは初めてで御座います」
「しかも永礼さんの奥様だなんて……これは腕によりをかけなければいけませんね」
従業員たちはそんなことを言いながら、物凄い素早さでメジャーを使って蜜夏の採寸を終えていく。
そのまま他の従業員は、束になったカラーチャートを取り出し、蜜夏の顔の近くに何回かそれを並べ、似合う色を探しているようだった。
「あの、私そんなスタイル良くないし、顔もパッとしませんし……」
気弱にそう言う蜜夏に向かって、従業員たちはハッキリと告げる。
「そういったお客様のお悩みを考慮した上で、よりお客様を美しく魅せるのがお洋服で御座います」
「蜜夏様が自信を持って、何度でも鏡を見たくなるようなお洋服を選ばせて頂きますからね」
そんなことありませんよ、とっても可愛いです……などという気休めの言葉より何倍も嬉しい言葉だった。
もはや、その言葉だけで自信が付くレベルである。
さすがはハイブランドのお店。従業員の対応も一流なのだと蜜夏は知った。
そうこうしている内に、いつの間にか何着もの洋服がかかったハンガーラックが目の前に置かれている。
「さあ蜜夏様。順番に試着いたしましょうね」
「こ、これ全部ですか?」
「もちろんです。お気に召さないもの以外は、全て試着なさいましょう」
「ひえぇ」
どことなく圧を感じながら、蜜夏は従業員の言う通り端から端まで、全ての洋服に袖を通すことになった。
驚いたのは、どの服も本当に似合うということ。
まだ会ったばかりだというのに、まるで十年以上付き合いのある友人のように、蜜夏の好みを知り尽くしている服ばかりだった。
「素晴らしい。よくお似合いですよ」
「蜜夏様、とても良い着こなしですわ」
しかも試着する度に、従業員たちは蜜夏を褒めた。
そのお陰か、不思議と背筋がピンと伸び、姿勢良く服を着こなしていく。
そうして数十分ほどかけて試着を終えた蜜夏に、従業員は一着を差し出した。
「どれもお似合いでしたが、蜜夏様の反応的にこちらの一着をとくにお気に召していたと思われます」
言われて見たその服はまさにその通りで、本当に優秀な従業員だと感心してしまった。
「ぜひこの服をもう一度着て、永礼様にお見せしてみませんか?」
一瞬恥ずかしさが浮かんだが、よく考えれば彼はこの試着中、ずっと店内で待ってくれたことになる。
せっかく気に入った服ができたのだ。着て見せることがこの場では一番感謝の表れだと思った。
「わかりました。着ます」
蜜夏が気に入ったのは、フロントボタンが可愛らしいサロペットドレスタイプのワンピースだった。
カーキ色のワンピースとアイボリー色のブラウスがほどよくマッチしていて、派手過ぎず地味過ぎず、とてもいいバランスの服だと思ったのだ。
「本当にお似合いですよ」
従業員に背中を押されながら、蜜夏はそっとフィッティングルームから出る。
出た途端、近くのソファに座っていた永礼と目が合った。
「なっ……」
永礼は目を見開き固まった。
まるでお化けでも見たかのような驚き具合に、逆に心配になる。
「一番似合っていると思った服を着てみたんですけど……」
「……っ」
永礼は漏れ出そうな声を抑えるためか、自身の口元を必死に手で押さえていた。
最初は似合っていなくて笑いでも込み上げているのかと思ったが、その陶器のように白い肌が見る見る内に真っ赤になっていくのがわかり、どうやら違う感想を抱いているのだということがわかった。
「な、永礼さん……?」
「かっ……」
「か?」
「可愛すぎる……だろっ!」
何とか必死に声を抑えながらも、今にも叫び出しそうな声をギリギリ絞り、そうして出した言葉がそれだった。
もしここが個室だったならば、叫び出していたかもしれないほど、永礼は全力の思いを込めてそう告げた。
「こ、こっちを向くな。駄目だ。可愛すぎておまえの顔を見ることができない。さっきまでの着物姿ももちろん可愛かったが……それは反則だ。駄目だ。本当に駄目だ。いや、蜜夏が駄目なわけじゃないんだ。俺が駄目なんだ……っ!」
「永礼さん、落ち着いて下さい……」
「落ち着けるか! なんで蜜夏はそんなに可愛いんだ……ッ!」
黙ってそこに居るだけで、絵になるほど美しい男だというのに。
むしろそのポンコツ具合を自分にだけ見せてくれているところが、逆に安心できるとさえ思えた。
(本当に、本心からそう思ってくれているって伝わるから……なんか、凄く嬉しい)
蜜夏は、心に火が灯るような感覚になった。
こんな気持ちは今まで感じたことが無い。
だから少し戸惑いもしたが、不思議と嫌な感じは無かった。
「永礼様がお気に召したようで良かったです」
「ああ、よくやった。後で従業員にボーナスをやるよう店長にかけ合っておく」
まだ赤みのある顔のまま、それでもキリリとした表情で永礼はそう言った。
そして、永礼は自然な動作で蜜夏をエスコートし、店を出ようとする。
「ちょ、ちょっと待って! この洋服どうするの……っ」
「安心しろ。うちに請求が来るようにしてある。あと、着てきた服は斎賀家に届けるよう手配しておく」
「そんな……」
「自分の妻に服を買うのはそんなにおかしいことか?」
離婚する気でいたはずなのに、こんなことをされたらますます意思が揺らいでしまう。
だけど永礼の目は、むしろ買わせてほしいとねだるような眼差しで……
「わ、わかりました。ありがとうございます」
そう感謝を述べる蜜夏に、永礼は嬉しそうな笑顔を浮かべた。
こうして二人はそれぞれ思いを抱えながら、次のデートコースである水族館へと向かうのだった。
平日の午後ということもあり、水族館の中は混雑し過ぎていない丁度良い客入り具合である。
入場券を購入する際、永礼がお金を出そうとしていたが、蜜夏は服のお礼として永礼の分も支払った。
その際にも、どうしてそんなに可愛いことをしてくれるんだ、と永礼は顔を真っ赤にしながら、蜜夏の顔を立てて嬉しそうに入場券を受け取っていた。
「うわー、凄い!」
館内に入ってまず出迎えてくれたのが、プロジェクションマッピングとコラボしたクラゲのゾーンだった。
色とりどりのクラゲが入った各水槽と、プロジェクションマッピングによって美しくライトアップされた空間。
本当に水の中にいるかのような感覚に、蜜夏は心が躍った。
「蜜夏はクラゲが好きなのか?」
「そうですね……割と好きな方だと思います。見てると癒されるっていうか」
「欲しければ二、三匹持ち帰れるようにするが?」
「もう! 買ってほしいとは違うんですよ!」
この調子だと、永礼は蜜夏が興味を持ったもの全てを買い始めてしまいそうだと思った。
「そういえば、永礼さんは竜宮童子なのですから、海の生き物と仲が良かったりするのですか?」
「ああ。仲が良いというか、それなりにシンパシーを送り合うことはできる」
そう言って永礼は、長細い人差し指を水槽にそっと当てた。
すると一匹のクラゲが近付いて来て、ガラス越しに永礼の指に触れようと動く。
少し経つと、吸い寄せられるようにクラゲが群衆を成し、永礼の指先の前でフワフワと泳ぎ始めていた。
そして永礼が指を離すと、名残惜しそうにクラゲたちはユラユラと動きながら、水槽の奥の方へとそれぞれ戻っていった。
「す、凄い……!」
「そうか?」
「永礼さん、魔法使いみたいでした」
キラキラと目を輝かせてこちらを見上げてくる蜜夏を前に、永礼は咄嗟に口元を抑える。
でないとまた、可愛い蜜夏への思いが爆発しそうだったからだ。
「み、蜜夏が気に入ったなら、良かった」
怒っているのかと勘違いしてしまうほど顔をプイと背けながら、しかし安堵した様子で永礼はそう言った。
だんだん永礼の、その照れ屋なところに蜜夏も慣れてきた。
(むしろいつも本心で言ってくれるから、こっちも変に疑わずに済むんだよね)
世の中には、ニコニコと笑顔を浮かべながら嘘をつく人間がたくさんいる。
表では褒めてくれていた子が、裏では悪口といっしょにけなしていたり。
だけど永礼は違う。
本心からの言葉をくれて、本気の姿を見せてくれる。
そんな永礼だからこそ、本当にそう思ってくれているのだと、安心して一緒にいられるのだった。
「永礼さん、次はトンネルゾーンですって。通路がトンネル状になっているから、海の中にいるみたいな……きゃっ」
「蜜夏!」
人とぶつかってしまった蜜夏は、思いのほか相手との体格差があったためそれなりに突き飛ばされてしまう。
大きくよろけた蜜夏は転ぶことを予期したが……しかし体ごと誰かに抱きとめられていた。
「永礼さん……」
「平気か、蜜夏?」
「だ、大丈夫です」
至近距離に永礼を感じてドキドキしながらも、後ろからすみませんという謝罪の声が聞こえ振り返った。そこには今ぶつかり合ってしまった相手が、申し訳無さそうに頭を下げていた。
「いえ、こちらこそすみません。前を向いてなかった私が悪いんです」
そう伝え、相手は何度かぺこぺこと頭を下げながら、進路とは逆の方を歩いていった。
「永礼さん、受け止めてくれてありがとうございます」
もしあの時永礼が受け止めてくれなければ、倒れ込むように転んでいたはずだ。
せっかく買ってもらった洋服も汚していたかもしれない。
「……永礼さん?」
ふと、いつまで経っても永礼から何の応答も無いことに気が付いた。
そっと顔を見上げてみれば、そこには真っ赤な顔をして天を仰いでる永礼の姿があった。
どうやら反射的に蜜夏を抱きしめたはいいものの、冷静になってきてから、この密着した状態に照れを感じ始めてしまったらしい。
「くっ……永遠にこうしていたい」
「え?」
「半分冗談だ。蜜夏が無事で良かった」
永礼はそう言いながら、名残惜しそうにではあるが蜜夏から離れた。
離れるまでドクドクと響いていた胸の鼓動は、果たしてどちらのものだったのだろうか。
「……蜜夏」
「は、はい」
「その……手を繋ぐのはアリだろうか?」
スッと差し出された、白く美しい永礼の手。
それはまるでダンスのお誘いをする貴公子のように優雅な姿で、ドキリと蜜夏の心臓が跳ねる。
「て、手を……?」
「嫌か?」
少しだけ永礼の表情が悲しみに曇る。
それを見て蜜夏は、慌てて首を横に振った。
「嫌じゃないです。そうじゃなくて、初めてのことでちょっと恥ずかしかったから……」
「そうか。なら失礼して……」
永礼は鮮やかな動作で蜜夏の手を取り、優しく握る。
そこまでは優雅に決めていた永礼だったが、手を握った途端にやはり顔を真っ赤にさせていた。もちろん蜜夏の顔も負けないくらい真っ赤だった。
傍から見れば実に初々しいカップルである二人は、手を繋いだまま水族館側が用意した進路を進む。
先程、蜜夏が言っていた通り、次はトンネル状に作られた水槽のゾーンだった。
左右はもちろん、自分の真上にも魚たちが泳いでおり、海の中を散歩しているような気持ちだった。
「わぁ、凄い。海の中を歩いてるみたい」
そこまで言って、ふと蜜夏は気になることができた。
「もしかして永礼さんも、こうやって海の中を歩いたりできるんですか?」
「ああ」
あっさりと返答され、蜜夏は改めて彼があやかしなのだと感じた。
「もう少し陽の光は少な目だが、実際にこういった感じだ。よく再現されていると思う」
言いながら、上空を泳ぐ魚たちを目で追う永礼の姿は、海の王子様のようだった。
何かと照れた様子を見せるから忘れがちだが、永礼の容姿や振る舞いは実に優雅で美しい。
現にこの水族館に入ってから、男女問わず一度は永礼を視界に入れて見惚れている人ばかりだ。中には露骨にキャッキャとはしゃぐ女子グループもいるぐらいである。
(そんな人が、あんなにも取り乱すぐらい私のことを可愛いって言ってくれるなんて……)
「どうした蜜夏。顔が赤いぞ」
「えっ」
「熱でもあるのか? デートは中止にするか?」
心配そうに顔を覗き込んでくる永礼に、蜜夏はますます顔を赤くさせてしまう。
(なんか、永礼さんの照れる癖がうつったみたい……っ!)
蜜夏は慌てながら弁明した。
「熱とかじゃないです! な、なんていうか……デートって初めてなので、永礼さんのこと意識してしまって、その……」
「……ッ!」
途端に、今度顔を赤くするのは永礼の方であった。
「んなっ、何を……み、蜜夏……だからなんでそんなに可愛いことを……っ」
「し、知りませんよ! それに永礼さんがすぐそうやって顔を赤くするから、私まですぐ顔が赤くなるようになっちゃったんですから」
傍から見てバカップルのようなやり取りをしていることに二人は気付いていない。
こんな調子で、水族館の各展示を二人はスムーズに進んでいった。
今日初めて会ったとは思えないほど話は弾み、時にはお互いに照れて顔を赤くしながら、ずっと笑顔の絶えない時間が続く。
そうして二人は、イルカショーのあるエリアに到達した。
見晴らしの良い、やや遠めの席に横並びになる。
「見るところが多くて、けっこう歩きましたね」
「そうだな。疲れていないか?」
「大丈夫です。むしろたくさん色んなお魚が見れて楽しいです」
「そうか」
蜜夏が笑顔になると、永礼もまた、嬉しそうに微笑する。
「水族館をデートコースに入れておいて良かった。榊にも後でボーナスをやらないとな」
「そういえば、榊さんはあやかしなんですか? それとも人間?」
「榊は俺の親父の代から側近をしてくれている人間だ。仕事で忙しい両親よりも俺に構ってくれていたから、もはや親のようなものだな、榊は」
「榊さん、凄く永礼さんを大切にしていますもんね」
デート前のやり取りだけで、榊がどれだけ永礼を可愛がっているかわかった。
きっと榊自身も、永礼に対しては主人としてだけでなく、我が子か孫でも見ているような気分なのだろう。
「蜜夏はどうなんだ?」
「え?」
不意に返ってきた質問に、蜜夏は永礼の方を向く。
「榊のような仲の良い使用人はいるのか? そういえば兄姉もいるんだったな。仲は良いのか?」
途端に、キィンと耳鳴りがした。
まるで今までのデートの時間が夢のように、一気に現実に戻される気分だった。
目を見開いて固まる蜜夏に、永礼は首を傾げる。
「蜜夏……?」
「あ、いえ、あの……」
これまで楽しく過ごしていたからか、家のことを考えると思いっ切り心が沈んだ。
そして思い出す。家での辛い日々を。
永礼が優しく誠実に扱ってくれるから、家で自分がどういった扱いを受けていたのか忘れてしまっていた。
(そうだ……私、家を出たいんだった……)
もうあの家と関わりたくない。家を出たい。
その気持ちが一気に溢れ出し、蜜夏は永礼に告げた。
「……永礼さん」
「どうした?」
「やっぱり私……離婚、しないと、です」
暗鬱な気持ちが背中からおぶさってくるようだった。
少し前までの楽しい気持ちが、おまえには過ぎたものだと言われているようで、とても苦しい。
「……どうして?」
しかし永礼の声音は落ち着いていた。
蜜夏の本気度を感じているからか、デート前のように駄々をこねたりはしていない。
代わりに真っ直ぐと蜜夏を見て、言葉の続きを待っている。
「私は、その……家から出たいんです」
「………」
「だけど永礼さんと結婚してしまったら、それは叶わなくなってしまうから……だから……」
しばらく、永礼は黙っていた。
周囲ではイルカショーを楽しみにする人たちの声でざわめいているが、それらがまるで耳に入ってこないぐらい、お互いに話に集中している。
そんな中で蜜夏は、離婚のことを言葉にしてしまった自身に後悔が生じていることに気が付いた。
(ああ……いつの間にか永礼さんと離婚したくないって思うようになっていたなんて……)
自分自身の感情に戸惑う蜜夏の前で、永礼はゆっくりと口を開く。
「家を出たいと思うぐらい、蜜夏にとっては何か重い感情があるのだと思う。それを話してくれてありがとう」
永礼から出た最初の言葉は、問い詰めではなく感謝だった。
予想していなかった永礼の態度に、蜜夏は呆気に取られた表情で話の続きを待つ。
「蜜夏が家を出たいという気持ちはわかった。だけど……俺はどうしても、蜜夏と離婚なんてしたくない。今日初めてこうして話をした間柄だが、俺は蜜夏と過ごした今日が、かけがえのないものとなっている。蜜夏は……どうだろう?」
「それはっ……私も、同じ気持ちです」
蜜夏自身も、永礼と過ごした今日一日が本当に楽しかった。
家で出来損ないとしてあまり外に出してもらえなかった日々と比べたら、こんなにも幸せな時間は無いだろう。
「蜜夏。これからはウチで暮らすというのはどうだろう?」
「え……?」
「蜜夏の家の者が許すなら、これから蜜夏は竜宮家の花嫁としてウチで暮らせばいい」
「それは……」
それは願ってもない提案だった。
竜宮家がどんなところかはまだわからないが、少なくとも斎賀家で過ごすあの重苦しい生活からは解放されるだろう。
「でも、私……私は……」
永礼への思いと、家への思いが、蜜夏の中でぶつかり合った。
ここが往来の場であることも忘れ、ボロボロと涙を流す。
「私は、出来損ないで……竜宮家の人にも、きっと……きっといっぱい迷惑を……っ」
そこまでを口にした瞬間、永礼が、優しく、そして力強く、蜜夏を抱き締めた。
「……もう言わなくていい。俺もそれ以上は詮索しない」
「永礼さん……」
「俺は蜜夏に幸せになってほしいし、幸せにしたいと思っている。だから、俺ができることならなんでもするから……どうか、離婚するだなんて言わないでくれ」
永礼が発する言葉の一つ一つが優しかった。
抱きしめている腕の温もりも、触れ合う箇所から聞こえてくる心臓の音も。
全てが優しくて、誠実だった。
だから蜜夏からも、永礼をギュッと抱き返していた。
「永礼さん……ごめんなさい。自分のことばかりで……っ」
「何を言っている。俺だって俺のことばかりだ。俺は蜜夏と離婚をしたくなくて必死なだけだ」
そんなわけはない。
もしそうだとしたら、こんなにも相手を思いやった言葉など出てこないものだ。
二人は抱き合った余韻を感じながら、ゆっくりと距離を戻す。
それでも心の距離は、さっきよりも近くなった気がした。
「これから永礼さんの妻として……永礼さんのおウチにお邪魔することになっても、いいですか?」
「もちろんだ」
ニコリ、と微笑した永礼に、蜜夏は頬を染める。
気付けば、イルカのショーがちょうど始まるところだった。
二人は手を繋ぎ合ったまま、ステージに立つ飼育員とイルカたちを眺める。
そんな二人のことを、近くの柱から黒服の男が観察していることに、当人たちは知る由も無かった。
***
「……カワイイ」
ベッドに横たわりながら、蜜夏はクラゲのぬいぐるみをツンと突いた。
先日のデートの際、水族館で永礼が買ってくれたものだ。
あの後、イルカショーで気持ちを打ち明けられたからか、より話が弾むデートになった。
水族館を出て、竜宮家が営むレストランで食事となったが、次から次へと出てくる料理と同じように、二人の話題も尽きることが無かった。
目の前に並ぶ料理を味わう蜜夏と、そんな蜜夏の可愛さを味わう永礼。
永礼に好きな料理は何かと問えば、蜜夏が握ったおにぎりと返ってくる。
そんな話の流れから、今度はピクニックにでも行こうかという話にまで発展した。
(ほとんど初めて会ったようなものなのに……凄く話が弾んで楽しかったな……)
デートのことを思い返しながら、自然と蜜夏の口元は緩んだ。
何気に嬉しかったのは、永礼だけでなく榊との連絡まで交換できたことだ。
永礼いわく、結婚しているのだから竜宮家の使用人は蜜夏の使用人でもあるとのこと。
そして榊いわく、自分は坊ちゃまと蜜夏お嬢様の行く末をどこまでも応援するということ。
永礼だけでなく、まさか榊まで味方になってくれるとは思っておらず、蜜夏は嬉しさのあまりその場で若干涙ぐんでしまった。
そんな楽しかった思い出から数日経った。
まだたった数日だというのに、また永礼に会いたいと蜜夏は感じている。
(離婚しようと思ってたのが嘘みたい……)
クラゲのぬいぐるみをギュッと抱きしめながら、ちょっとした切なさを覚える。
あのデートの日、永礼は最初から最後まで蜜夏のことを思いやり、時には大きく照れてみせ、そして誠実であった。
蜜夏からすれば、今まで誰からもそんな対応をされたことがなかった。だから永礼の一挙手一投足に驚きながらも、それでも最後には幸せな気持ちになっていた。
それに、榊が時折見せる永礼への態度を見ているだけで、永礼が実に信頼に足り得る男なのだということも伝わってきた。
(本当に離婚してしまわなくて良かった……)
思えば、自分の都合だけで離婚を考えてしまった。そのことを蜜夏は深く反省した。
そして今となっては、離婚の提案をきっかけに、永礼と色々なことがわかり合えて良かったとすら思っている。
(次はいつ会えるかな)
そんなことを思っていた矢先、突然着信音が鳴り響いた。
画面を見ると、そこには『榊さん』の文字。
一体どうしたのかと、蜜夏は慌てて応答する。
「も、もしもし?」
『蜜夏お嬢様。突然のご連絡大変失礼いたします。実は今……蜜夏様のご家族が竜宮家に来ておりまして……』
「えっ? わ、私は何も聞いていないです」
家族が、蜜夏だけを省いて何処かへ出かけることはしょっちゅうあった。
そんなことにはもう慣れているので、蜜夏もたいして気に留めることもなくなった。
しかし、その行き先が竜宮家であるなら話は別だ。
「家同士のご挨拶でしょうか? でしたら私も急いで行かないと……」
『いえ。どうにもそういったものではなく……どうやら蜜夏お嬢様の姉君の方が永礼様と結婚をしないか、という話になっておりまして』
「え……ッ?」
まったく予期していなかった話の内容に、頭から冷や水をかけられたかのような気分になった。
「わ、私そんな話、全然っ……」
焦るあまり、上手く言葉が出てこない。
それでも電話越しの榊は、とても冷静に、そして優しい口調で続けてくれた。
『やはりそうでしたか。斎賀様たちはアポイントも無く乗り込んできて、永礼様の花嫁を長女の方にするよう提案してきたのです』
「………」
『しかもその理由が、蜜夏様がご自身で、永礼様は自分にはもったいない方だからお姉さまに永礼様を譲りたい、と仰っていたと言うのです。本当でしょうか?』
「そんな……そんなこと言ってないです。確かに永礼様は自分にはもったいないほど素敵な方ですが……それでも私は……私は永礼さんと別れたくないです!」
『その言葉が聞けて安心しました』
蜜夏自身も、自分の中に離婚の意思がもうこれっぽっちも無いことに気付かされた。
『蜜夏様。榊は先日のお二人のご様子を見て、それはもう素敵なご夫婦であると感じました。末永く、お二人で手を取り合っていってほしいと、心からそう思ったのです』
「榊さん……」
『ですから、もし蜜夏様が坊ちゃまとの離婚を考えていないのであれば……今からウチの送迎車を向かわせますので、こちらにお越しになりませんか?』
榊の言葉に、蜜夏は一度口を閉じる。
今まで、家族に逆らうようなことはしてこなかった。
そして永礼とは始め、離婚をするために出会った。
だけど今は違う。
永礼と離婚なんてしたくないし、何より、永礼が他の女性のものになってしまうなんて、そんなの嫌でたまらなかった。
たとえそれが自分の家族であろうとも……蜜夏は、断固としてお断りだった。
「送迎車を、お願いします。永礼さんの妻は私ですから」
『ええ、奥様。ただちに向かわせます』
電話の向こうで、榊が嬉しそうに微笑むのがわかった。
そうして蜜夏は、覚悟を決め、急いで出掛ける準備をするのだった。
***
「それで、話と言うのは?」
時は少しさかのぼる。
多忙な身である永礼が、先約であった会食をキャンセルし、こうして応接間にいるのは、相手が蜜夏の家族であるからだ。
斎賀家の当主であり蜜夏の父親の峰近、そして長女の愛華が、今目の前にいる。
榊が丁寧な所作でテーブルにお茶を出し、退席したところで話が始まった。
「この度は、ウチの出来損ないと婚約して下さり、大変に有難く思っております」
「出来損ない……?」
おそらく峰近は、謙遜と真実を混ぜた上で、本心からそう言っている。
だが永礼からしたら、愛しくて大好きな自身の妻を馬鹿にされたようにしか聞こえなかった。
もちろんこんなことで声を荒げる気はないが、相手によってはとっくに手が出ていただろう。
「蜜夏さんは出来損ないなんかじゃないですよ。先日顔を合わせた時も、より結婚して良かったと思ったぐらいです」
「ハハハ。竜宮童子どのは気遣いのできるお方で助かります」
どこまでも蜜夏を出来損ない扱いしたい峰近に嫌気が差し、永礼は峰近の隣に座る愛華の方へ視線を移した。
途端に愛華は頬を染め、一目で高価だとわかる豪華な着物の袖で上品に口元を隠した。永礼でなければ、その所作にドキリとしたことだろう。
そのことがわかっていない峰近は、二人が良い雰囲気を作っていると思い込んだまま話を続けた。
「いや今回はですね、その蜜夏との結婚のことでお話がありまして」
「なんですか?」
「良ければ愛華と結婚いたしませんか?」
「は……?」
寝耳に水なほど、まるで予想していなかった話の内容に、思わず永礼はそう返してしまった。
だが峰近からすると、永礼の反応はとてもいい話に驚いているように見えたらしく、意気揚々と笑った。
「竜宮童子どのはおそらく、ウチの愛華のことを知らずに結婚を申し込まれたのかと思いましてな。蜜夏は料理の腕も無ければ器量も良くない娘でして。それに比べ、長女の愛華は親の自分が言うのもなんですが実によくできた娘でして。料理界の今後の発展を考えれば、愛華との結婚の方がずっとプラスになることでしょう」
「やだ、お父様ったら」
豪快に笑う峰近に、しおらしく笑う愛華。
その二人を前に、永礼は眉根を寄せることしかできなかった。
どうにも話が噛み合わない。
それというのも、峰近は永礼が料理界を盛り上げるために結婚を申し込んできたと思っているからだ。
さらに先日の蜜夏とのデートには、愛華専属の黒服が、デートの様子を事細かに愛華へとリークしていた。
そこで知ったのが、永礼の見た目が予想していた以上に美しいことと、富と繁栄の代わりに醜くならないということだった。
そうなると尚更、愛華は自分より先に蜜夏が、しかもあんなにも格好いい殿方と結婚することが気に食わなくてたまらなかった。
だから愛華はいつも以上に父親におねだりをし、こうして永礼の花嫁を自分にしてしまおうと画策したのだった。
「永礼様」
愛らしい声音で、愛華は永礼の名を呼ぶ。
「永礼様にとって『捧げもの』というのはとても重要なものなのでしょう? 私でしたら、永礼様にとって大事な『捧げもの』になると思うのです。その覚悟も御座います」
「………」
「永礼様が斎賀家に富と繫栄をもたらして下さる代わりに、私が永礼様と永遠に添い遂げます。蜜夏とは違って、私には料理の才能もありますし、華道や茶道もしっかり嗜んでおります。私たちなら、竜宮家と斎賀家を結ぶのに相応しい結婚となるでしょう」
愛華は乙女が祈るように両手の指を絡め、その大きな目をパチパチと瞬きさせながら、永礼の方を見た。
そしてその隣に座る峰近は、自分の娘の言葉に、うんうんと満足そうに頷くばかりだった。
「………」
永礼は何も言えなかった。何から話せばいいかわからなくて。
永礼にとって蜜夏以外の者との結婚なんて、まるで考えられない。
愛華は自身を立派な『捧げもの』だと自負しているようだが、永礼からすれば蜜夏ほどの『捧げもの』はこの世に無いのだ。
果たしてどこから否定し、訂正し、言い聞かせればいいのか。
永礼の端正な顔に疲れが見え始めた、その時。
「失礼します!」
勢いよく扉が開き、三者が何事かとそちらを見る。
峰近と愛華は顔を歪め、そして永礼は目を見開き固まった。
「お話中すみません。でも、言わせて下さい。永礼さんの妻は、私です!」
そこにいたのは蜜夏だった。
急いで来たからか上気した頬を赤く染めながら、蜜夏はハッキリとそう告げた。
「蜜夏……っ」
思わぬ蜜夏からの宣言に、永礼は真っ赤になって口元を抑える。
一方、峰近と愛華は一瞬だけ呆気に取られ、そしてすぐに怒りの表情を浮かべた。
「蜜夏……おまえ! 会談中に入ってくるなどふざけるな。わきまえろ!」
「……っ」
峰近の怒鳴り声に、蜜夏はビクリと体を揺らす。
それでも蜜夏はその場から動かなかった。
「蜜夏さん、何を考えているの? こんな失態を永礼様に見せるだなんて……本当にあなたって斎賀家の恥さらしだわ」
「でも……でも私は、永礼さんの妻です」
「残念ね。妻になるのはこの私よ。あなたに永礼様はもったいなさ過ぎるでしょ?」
それは確かにそうかもしれない。
もったいないぐらい、永礼は素敵な人である。
だけど……それでも蜜夏は退かなかった。
「確かに永礼さんは自分にはもったいないかもしれません。だからこそ、これから……これから私は、永礼さんに相応しい妻になっていこうと思うのです」
「蜜夏……」
永礼は思わず蜜夏の名を呟いていた。
そうして立ち上がり、蜜夏の傍に立つ。
「永礼さん……」
「蜜夏。君がそう思うように、俺だって蜜夏に相応しい夫になれるよう、これから切磋琢磨するつもりだ」
「そんな……永礼さんは今でもう充分なのに」
「ならば蜜夏だってそうだ。今の蜜夏のことが、俺は愛しくてたまらないのだから」
二人は静かに見詰め合う。
そのまま口付けしてしまってもいいほどに、愛に満ちた雰囲気が漂っていた。
ただしこの場には、峰近と愛華、そして蜜夏と共に駆け付けた榊の姿がある。
良いムードは一旦おあずけだった。
「斎賀さん」
永礼は蜜夏から視線を外すと、鋭い目つきで峰近を貫いた。
「俺にとって『捧げもの』は蜜夏以外にあり得ない。その蜜夏を……俺の『捧げもの』を奪うということは、富と繁栄が無くなっても構わないということですが……それで良いのですか?」
瞬間、峰近の顔が歪んだ。
「『捧げもの』が無いならば、俺が富と繁栄をもたらす道理など無い。むしろ、俺から『捧げもの』である蜜夏を奪うという罰当たりなことをするならば、末代までの不幸が訪れても文句は言えまい」
「んなっ……なんだとッ?」
「そうなりたくなければ、蜜夏との結婚を認め、今後は蜜夏に関わらないと誓って下さい。そうすれば斎賀家にそれなりの富と繁栄をもたらしましょう。もちろんこの約束を破って蜜夏に接触しようものなら……言わなくてもわかりますよね?」
「う、ぐ……」
ついに峰近は黙り込んでしまった。
元々、竜宮童子の力に目がくらんでの結婚だった。
峰近にとって最も大事なのは、娘の幸せよりも家の繁栄なのだ。
「あ……愛華、帰るぞ」
「そんな!」
「竜宮童子は蜜夏と結婚した。今日はそれを認めに来た。それだけだ」
「お父様ッ!」
これ以上、永礼の不興を買うまいと、峰近はそう言って部屋を出て行く。
愛華は一度だけ蜜夏を睨みつけたが、すぐに峰近の後を追って退出していった。
「………」
嵐が過ぎ去った後のように、部屋にしばし沈黙が続く。
先に口を開いたのは永礼の方だった。
「……蜜夏」
「は、はい」
蜜夏がゆっくりと顔を上げると、そこには顔を真っ赤にしながらも、喜びでとろけそうな優しい表情を浮かべる永礼の姿があった。
「蜜夏が俺の妻だと言って現れた時……幸せで心臓が止まるかと思ったぞ」
「そ、そんな大袈裟な」
「大袈裟なものか。本当に嬉しかった」
「永礼さん……」
永礼の言葉はいつだって本心で、そして誠実だ。
蜜夏自身、永礼の妻だと宣言するのは勇気のいる行為だった。
けれど永礼が他の女性の……しかも姉のものになってしまうことを考えただけで、居ても立っても居られなかったのだ。
だからほぼ勢い任せで言ってしまったのであるが……
永礼がそれを心から嬉しく思っていることが、蜜夏にとっても幸せなことであった。
「それにしてもどうして蜜夏が此処に……?」
「榊さんが教えてくれたの」
言われて永礼は、今更ながらドアの近くで待機している榊のことを思い出した。
榊はいつものように姿勢よくその場に立っている。
「私はお二人の幸せを願っておりますので。それに坊ちゃまが、蜜夏お嬢様以外を嫁にするとは到底考えられませんでしたので」
「なるほど。よくやってくれたな榊」
「身に余る光栄です」
榊は胸に手を当て一礼する。
そうして部屋を出て行こうとする前に、永礼の方を向いて告げた。
「坊ちゃま。榊は退出しますからね」
「わ……わかっている」
「……?」
何でもお見通しだと言わんばかりの榊と、見通されていたことを恥ずかしがる永礼と、まるでわかっていない蜜夏。
永礼は何を恥ずかしがっているのだろうと蜜夏は思ったが、榊が退出したのを確認し、再び永礼から名を呼ばれた。
「……蜜夏」
「はい」
「さっきの斎賀家とのやり取りで、蜜夏が家のことで悩む必要はもう無くなった。今日からは竜宮家で暮らしていいし、そのことで家族が何か言ってくることも無いだろう」
「永礼さん……なんてお礼を言ったらいいか……」
「俺の妻なのだから、これぐらいして当然だ」
「……っ」
力強い永礼の言葉に、じんわりと涙が浮かんでしまう。
それを、優しい手付きで永礼が拭う。
「泣かないでくれ。俺は……笑っている蜜夏が一番好きだ」
恥ずかしさから一度視線を反らしつつ、もう一度改めて蜜夏を見つめ、永礼はそう告げた。
永礼は何度も蜜夏のことを可愛いと言ってきたが、蜜夏からすれば永礼だって本当に可愛いと思う。
だから、蜜夏は言った。
「あの、永礼さん」
「なんだ?」
「キス……してもいいですか?」
「なっ、なななんっ?」
貴公子のように整った顔が台無しなぐらい、永礼は大きく慌てふためいた。
「なんだか、自然とそう思ったんです。駄目ですか?」
「そ、それ、それはっ……」
何故か悔しそうな顔をする永礼に、蜜夏は少しずつ自信を無くしかけた。
やはり女性からそんなことを言うのははしたなかっただろうか。
だが、蜜夏のそんな不安を吹き飛ばすように、永礼は言う。
「それは、俺が先に、言いたかった……っ!」
「へ?」
「榊が退出したから、俺から蜜夏に口付けていいか言おうと思っていたのに……なのに……っ!」
そこでようやく、部屋から退出する際の榊と永礼のやり取りの意味がわかった。
榊は言葉にせずとも、永礼の背中を押していたのだ。
「ぷっ……あははっ、はははは」
思わず蜜夏は笑う。
こんなふうに笑うのは一体いつぶりだろうかと思った。
斎賀家でずっと姿を隠すように生きてきたのに、永礼のお陰でこんなにも生きていることが嬉しくて幸せだと感じることができた。
榊という素敵な人とも知り合うことができた。
何より、永礼という最高の夫が傍にいてくれる。
「……蜜夏」
「あはは、あ、はい?」
笑いながら永礼の方を向く。
そうして感じた、唇に当たる柔らかい感触。
気付けば、永礼に優しく口付けられていた。
「……へ?」
永礼の唇が離れ、その美しい顔を間近で見ながら、蜜夏は気の抜けた声を上げる。
「あの、今……」
「もう一度、してもいいか?」
顔を赤くしながらも、真剣にそう訊ねてくる永礼の表情は王子様そのもので。
蜜夏は一つ、静かに頷いた。
「んっ……」
ゆっくりと唇が触れ、それだけで脳が痺れるような感覚に陥る。
触れるだけの口付けなのに、体の芯が温まり、幸福感が確かにあった。
「蜜夏ほどの『捧げもの』は他に無いんだ。だから……もう二度と、離婚だなんて言わないでくれ」
「……はい」
そうして二人は、再び口付けを交わした。
離婚から始まった関係を、心から祝福するように。
【完】
「はいぃッ?」
男は顔を真っ赤にしながらキレていた。
女も顔を真っ赤にしながら驚いていた。
初対面、今から離婚する二人は、どちらも照れた顔で向き合っていた。
◆◇◆
桜の花びらが舞い始めた春の頃。
そんな季節に相応しい縁談が、斎賀家を賑わせていた。
斎賀家といえば、政治家から財閥、華族までが御用達の料亭であり、その由緒は江戸時代までさかのぼると言われている。
更に国があやかしとの交流を解禁した昨今では、名立たるあやかしたちが舌鼓を打っているほど、斎賀家は上流階級に好まれる料亭であった。
現在の斎賀家本家の構成は、当主となる父と、一男三女の子供たち。
跡取りとなる長男と、長女、次女は非常に才能豊かで、大人でも難しいとされる料亭の品々を難なく仕上げられるほどである。
だが、唯一末の三女だけは違った。
料理の基礎ぐらいはできるが、際立ったセンスがあるわけでもなければ、器量が良いわけでもない。レシピを見ながらならば家庭料理をこなせるぐらいで、場合によってはその辺りの主婦の方がずっと手際が良いぐらいであった。
そんな三女――蜜夏のことを、斎賀家の誰もが出来損ないとして扱っていた。
何の期待も持たず、家の邪魔だけはするなと言わんばかりの無関心さで、蜜夏は十六年間ずっと放っておかれ続けた。
だから蜜夏も、自分は斎賀家のお荷物だと思いながら、ただひそやかに暮らしていた。
突然の縁談がやって来るまでは。
***
「どういうことですのお父様!」
普段はおしとやかな令嬢として社交界を我が物顔にしている長女の愛華が、らしくもなく声を上げていた。
隣に座る次女の姫香も、納得がいかないといった顔で不貞腐れている。
その向かい側に座る長男の桃火は腕を組み、上座に座る父にして当主――峰近は顎髭を撫でていた。
「どうして私と姫香を飛ばして、蜜夏が結婚って話になるのよ!」
愛華はすでに十八を迎えており、姫香も十七になった。
斎賀家で手塩に掛けて育てられた麗しの令嬢たちに、これまでもそれなりに縁談の話は来ていた。
だがどれも当主の峰近が弾いており、こうして家族会議に挙げられるような縁談は初めてのことだった。
しかもその縁談の相手……いやそれどころか結婚の相手が、出来損ないのみそっかすである蜜夏なのだから、愛華が声を上げるのも無理はない。
一人だけ部屋の端で立ったままの蜜夏は、予想外の結婚話に驚きつつ、愛華を刺激しないよう顔を伏せていた。
「まあ待て愛華。落ち着け」
「でもお父様……」
「相手は人間ではない。あやかしだ」
その瞬間、室内の空気が一変した。
これまで殺気立っていた愛華たちが気の抜けたような表情を浮かべ、代わりに蜜夏は目を見開き口元に手を当てる。
峰近は、蜜夏の方を真っ直ぐ向きながら話し始めた。
「竜宮童子を知っているか? こちらが『捧げもの』をすれば巨万の富と家の繁栄を与えてくれる一方で、竜宮童子自体は醜い姿になっていくというあやかしだ」
「社交界で懇意にしているあやかしからそんな話は聞いたことがありますわ。確か、富と繁栄の代わりに、竜宮童子自身は醜くなっていくのだとか」
「ああその通りだ。言い伝えでは、この醜くなった竜宮童子を家から追い出してしまった所為で元の貧乏になる……という話らしい」
そこまで峰近が言い、愛華は何かを思いついた表情になる。
「けれど醜くなった竜宮童子と未来永劫添い遂げれば……」
「……斎賀家の繁栄は約束されたものになるな」
長男の桃火が、ポツリと呟いた。
途端に次女の姫香が愛らしい表情で言葉を続ける。
「なぁるほど。醜いあやかしの旦那様は、蜜夏に担当してもらって、斎賀家の繁栄を永遠にもたらしてもらうってことですわね」
あまりにも身勝手なことを、何てことはないように彼らは話している。
蜜夏は、その内容に耳を塞ぎたい気持ちであった。
「それにどうも、先方は蜜夏を指名してきたんだ。これ以上無い流れだと思わないか」
「あらぁ、蜜夏も隅に置けないわね。竜宮家の御曹司さんからご指名だなんて」
クスクスと愛華の嘲笑う声が聞こえ、蜜夏はますます顔を伏せた。
何故、向こうから指名してきたのかは知らないが、そもそも蜜夏は十六歳を迎えた今、家を出ようと考えていたのだ。
この家にいても自分の居場所は無いし、お荷物になるだけ。
だったら家を出て自立してしまった方が、斎賀家のためにも自分のためにもなる。
そう思っていたのに。
「ま、待ってください。私そんな……会ったこともない人と結婚だなんて……」
「蜜夏」
圧のある峰近の声音に、蜜夏は体を縮こませる。
「これはもう決まった結婚話だ」
「そんな……だって、顔も知らない相手なんて……」
「先方はお忙しい身なんだろ。今はおまえに会えないと言っていたが、その時はいずれ来るんだ。それまでおまえは良き妻として黙って待っていればいい」
「富をもたらす代わりに醜くなるあやかしなんでしょ? 会う時はあまり顔の期待はされない方がいいんじゃないかしら」
姫香の笑い声も、どこか遠いところから聞こえてくるようだった。
(こんな勝手に……なんで、どうして……)
せっかくコツコツとお金も貯めていたのに、これでは計画が全て水の泡だった。
自分の意思など何一つ尊重してくれていないこの結婚に、蜜夏は強い憎しみを抱いた。
(そもそも、お父様は家の繁栄を目的としていて、先方に対しても失礼だわ。だったら……)
蜜夏は、一人決意する。
(竜宮童子さんにそのことをお話して、離婚してしまおう!)
それが自分を虐げてきた斎賀家への、最初で最後の反抗だと、蜜夏は密かに心に誓うのだった。
◆◇◆
そうして、変わらぬ日々が過ぎ去りながらも、裏では着々と結婚話が進行していった。
蜜夏にとって謎だったのは、自分を指名してきたことと、その割に一度も挨拶に来ないことである。
話によると、蜜夏のことを以前見かけたことがあるらしく、それをきっかけに結婚の申し入れへと至ったらしい。
だが蜜夏からすれば相手のことなど全く知らないため、本当に一方的な結婚でしかない。
更に色々と話を聞いたところ、昔話の言い伝えで出てくる竜宮童子の末裔となる男が結婚相手らしく、彼もまた有名な高級レストランを運営する竜宮グループの会長をしているのだとか。
そのため、すでに一部の紙面では『料理界を賑わせる大物カップル登場か!』などという文字が一面を飾っていた。
(すぐに離婚するんだから、あんまり騒がないでほしいなぁ……)
新聞を広げながら、蜜夏はため息を吐く。
(竜宮童子さんだって、自分の力目当てだって知れば離婚したくなるだろうし。世間が盛り上がってくれても、肩透かしに終わるだろうけどね)
「蜜夏。こんなところで何をしている」
突如、背後から長男の桃火に声をかけられ、蜜夏は弾かれるように立ち上がった。
同じ斎賀家の子供でありながら、蜜夏は使用人のように背筋を伸ばし、桃火の方を向く。
「お兄様……」
「おまえ、話を聞いていなかったのか?」
「え?」
「今日これから、竜宮童子と会う話だっただろうが」
「えっ!」
正直言って初耳であったが、実はこういったことが何度もあった。
というのも、使用人の中にも蜜夏を虐げたり、雑な扱いをしたりする連中が一部いるのだ。
その所為で、こういったいやがらせにより、連絡や報告が行き届いていない場面がこれまでも起こっていた。
だからきっと今回も、どこぞの使用人がわざと伝えてくれなかったのだろう。
「斎賀家の恥さらしが。とっとと支度しろ」
「は、はい。申し訳ありません」
蜜夏は急いで部屋を出た。
自室に帰ったら、子供の時から良くしてくれている使用人が、改めて今日の予定のことを教えてくれた。どうやら彼女もそのことをさっき知ったらしく、慌てて駆け付けてくれたというわけだ。
なので彼女の手を借り、急いで着物を着つけ、ヘアメイクをセットする。
「本日が初体面となるのでしょう? しっかり気合いを入れませんとね」
「う、うん」
使用人に髪をとかされながら、蜜夏は頷く。
しかし胸中にあるのは、初対面の挨拶と共に離婚を申し立ててやるという覚悟だった。
***
支度を終えて家を出ようとした蜜夏は、先方が迎えに寄越してくれたリムジンに乗せられ、竜宮グループの経営するレストランが入ったホテルへと案内された。
都市部でもとくに選ばれた人しか泊まることのできないハイクラスなそのホテルへ到着すると、今度は竜宮家の使用人と思われる人たちが数人、蜜夏を丁寧にもてなし、エスコートしてくれる。
斎賀側の使用人とは入り口で分かれたため、蜜夏は単身でホテルへと足を運ぶこととなった。
「こちらのお部屋でお待ち下さい」
普段はお偉いさんが会議などで使うのであろう談話室に通された蜜夏は、居心地の悪さを感じながらソファに腰をかけた。
斎賀家ではこんなにも丁寧に扱われたことがないため、どう対応すればいいのかわからないところがある。
今日だって出来得る限りのおめかしはしてきたが、こんなにも立派な部屋に通されるとは思っておらず、今にも気後れしてしまいそうだった。
(えぇい、弱気になっちゃ駄目よ。離婚よ、離婚。はじめましてこんにちは離婚しましょう。これぐらいスムーズに離婚を切り出さなきゃいけないんだから)
蜜夏はギュッと拳を握る。
(だいたい勝手に結婚を取り付けておいて、一回も顔を合わせに来なかったんだから、それだけでも離婚の理由になると思うのよね。会う暇も無いほど忙しいなら、なんで結婚なんてしたのかしら)
そうこうしている内に、ノック音と共に扉の開く音が聞こえ、蜜夏は顔を上げる。
「失礼いたします。竜宮永礼様がお着きになりました」
側近と思われるお年を召した使用人が頭を下げてそう告げると共に、後ろから一人の男が入室してくる。
後ろで一つに結われた青黒く輝く髪の毛。肌は透き通るほどに白く、その切れ長の瞳は深海のような濃い青色を見せている。
竜宮童子は富や繁栄をもたらす代わりに醜い姿になるらしいが……彼はまだその力を使っていないからなのか、とてつもない美男子がそこに居た。
和装をキッチリと着こなした長身のその美男子――永礼は、一度だけ蜜夏の方を見るとすぐに目を反らした。
「榊、下がっていいぞ」
「……ですが坊ちゃま」
「下がれと言っている」
「失礼いたしました」
榊と呼ばれた使用人は、すぐに引き下がり、音も無く部屋から退室していった。
残された永礼と蜜夏の間に、何とも言えない沈黙が漂う。
「………」
「………」
蜜夏は目の前に座る永礼の方を見ているが、永礼は蜜夏の方を見ず、やはり明らかに視線を反らしている。
(顔も見たくないってこと? そんな人となんで結婚したのかしら……)
この永礼という男のことがまるでわからないが、とにかくこのまま沈黙が続いても困るだけなので、度胸のまま蜜夏は口を開いた。
「あの、初めまして。斎賀蜜夏と申します」
「……竜宮永礼だ」
「えっと……私と結婚された永礼様で、お間違い無いですか?」
「ああ」
ぶっきらぼう、という言葉が実に相応しいほど、永礼からの返答は最低限だった。
話を広げる気も感じられず、言葉のキャッチボールがまるでできない。
「お伺いしたいのですが、どうして私と結婚をされたのですか?」
「………」
「こう言うのもなんですが、私は斎賀家ではお荷物のような存在です。料理の腕も無ければ器量も良くありません。ですから……」
ですから離婚はどうでしょう、と、そう提案してみようとした矢先。
「……向けるな」
「え?」
突然、永礼が割って入ってきた。
だが肝心な部分が聞き取れず、蜜夏は思わず首を傾げる。
「今なんと仰って……」
「だから……だからその可愛い顔をこっちに向けるな!」
「はいぃッ?」
永礼の真っ白な肌はわかりやすいほど真っ赤に染まっていた。
一方、予想外のことを言われた蜜夏もまた、顔を赤く染めていた。
一体全体、いきなりなんなんだ、と。
蜜夏がパニックになる前に、扉が勢いよく開かれた。
「斎賀様、大変失礼いたしました!」
先程退出したはずの榊が、扉を開けた勢いのまま入室し、流れるような所作で永礼の隣に立ち頭を下げる。
「え、え、えーと」
「やはり駄目じゃないですか坊ちゃま」
「うるさい榊」
永礼は榊の方を見てバツが悪そうにそう告げる。途中、一度だけ蜜夏と目が合ったが、やはりすぐに顔を背けてしまう。
困惑するしかない蜜夏の心境を察しているように、榊は一歩前へ出て説明し始めた。
「斎賀様、誤解を招いてしまいましたら大変失礼いたしました。坊ちゃま……永礼様は極度の恥ずかしがり屋ゆえ、このような態度を取ってしまわれるのです」
「榊!」
永礼から声が上がったが、榊は華麗にスルーして言葉を続ける。
「永礼様はそれはもう斎賀様のことを好いております。忙しさと恥ずかしさでなかなか会いに行くことすらできないにも関わらず、斎賀様が他の馬の骨に盗られてしまわぬよう、何が何でもという意気込みで結婚だけを先に済ませてしまうほど、永礼様は斎賀様が好きでたまらないのです」
「榊もうやめろ!」
真っ赤な顔を手で押さえつつ、永礼は悲鳴に近い声を上げた。
一方、蜜夏はただただ呆気に取られるばかりだった。
とはいえわかったことは、本当に永礼は照れ屋で、そしてこの結婚に対して本気だということだ。
政略結婚、または料理界の発展のため、それとも長女や次女と相手を間違えた……それぐらいまで考えていたのに、永礼のその態度と榊の弁明を前にしたら、そんな考えも馬鹿らしいほど真っ直ぐな気持ちを向けられてしまった。
つられるように、蜜夏もまた顔が赤くなっていることに気が付いた。
「あの、その……一つ、お伺いしたいのですが……」
「なんだ」
ぶっきらぼうな態度は変わらず、ただし顔を真っ赤にしたまま永礼は腕を組んでチラチラと蜜夏の方を見る。
「どうして私なんですか? お会いしたこと、ありましたでしょうか……」
一番の疑問がそこだった。
この結婚が本気のものだとすると、むしろそこがわからない。
しばらく黙って永礼の方を見ていると、永礼はその綺麗な顔を苦悩するように歪ませつつ、渋々と口を開いた。
「数年前に、料理人同士の交流会が、あっただろ」
言われて真っ先に思い出したのは、十歳ぐらいの時に行われた斎賀家主催の交流会だ。
料理界の重鎮から新進気鋭の若者たちまでが集まり、その場で料理を振る舞ったり意見を交換したりする会が過去にあった。
「あの時……み、蜜夏は……俺ににぎりめし、くれただろッ?」
「え……」
言われて蜜夏は必死に記憶をたどる。
確かあの会でも、斎賀家の邪魔にならないよう会場の隅っこに追いやられていて。
ただ、みんなが料理を披露する日だと聞いていたから、頑張っておにぎりを作っていて。
だけどそんなもの斎賀家の恥になるから捨てろと言われて。
それで泣く泣く捨てようとした時に……
「あ!」
そこで蜜夏は思い出す。
ゴミ箱の前で泣いていた蜜夏に、男の子が声をかけてきたのだ。
何を話したかまでは覚えていないが、男の子はお腹が空いているとかで、持って来たおにぎりを全部食べてくれたことは覚えている。
「まさか……あの時の?」
「………」
真っ赤な顔のまま一つ頷く永礼を見て、蜜夏は口を開けたまま固まってしまう。
だって、十年も前の……お互い子供の時のことだ。
あの出会いをきっかけに、永礼は結婚まで考えたということになると……その思いは相当のものである。
そんな蜜夏の驚きをフォローするように、永礼は顔を背けながら話し始めた。
「あの時のにぎりめしは、俺にとってあの会場のどのご馳走よりも美味かった。俺たち竜宮童子の一族にとって、『捧げられたモノ』の価値はでかいんだ。だからあの時、蜜夏がくれたにぎりめしは俺にとって最上級の『捧げもの』だったし、何より……」
「……何より?」
「す……」
「す?」
「凄く可愛かったんだよ、蜜夏が!」
逆ギレでもするかのような馬鹿でかい声で、そんな恥ずかしいことを永礼は言ってくる。
黙っていればクールな美男子だというのに、蜜夏にはもうそんな印象を永礼には持てないぐらいだった。
「えーと……あ、ありがとうございます」
照れながらも、蜜夏はお礼を言う。
思えば、こんなにも褒められたり好意を持たれたりするのは初めてかもしれない。
亡き母も、他の兄姉たちばかり可愛がっていたのだから。
しかしこうなってくると、当初予定していた離婚の話が切り出しにくくなってきた。
まさかこんなにも強く真っ直ぐな好意を抱かれているとは……予想外すぎた。
「永礼さん、あの……お気持ちは凄く嬉しいんですけど……」
「そうか」
「でも私、離婚しようと思っていて……」
「な、なんだとッ?」
勢いよく永礼が立ち上がり、テーブルがガタンッと揺れた。
傍にいた榊がすぐに卓上のものを元の位置に戻す早わざを見せていたが、それよりも圧のある永礼から目が離せなかった。
「離婚……離婚だとッ? な、何が不満だ? 俺のことが嫌いかッ?」
「いえ、嫌いとかそういうことではないんですけど……」
「だったらどうして……。お、俺は嫌だ! 離婚なんて絶対したくない!」
普段、絶対他の人には見せないであろう子供のようなその姿に、蜜夏はちょっとばかり母性本能が疼いてしまった。
とんでもない美男子が、ある意味カッコ悪いほどに取り乱しながら、真っ直ぐに好意を向けてくる。それを何とも思わないほど蜜夏もひねくれてはいない。
ただ、彼と結婚してしまうと、ますます家族から離れにくくなってしまう。
だからきちんと理由を説明しなければと、蜜夏は口を開いた。
「あの……」
そこまで言いかけ、言葉が出なくなってしまう。
いざ家のことを口にしようとしたら、なんだか上手く話せない。
長いこと自分の境遇を必死に受け入れてきた所為か、そのことを本当は辛かったことだと客観的に説明しようとすればするほど、どんどん言葉が詰まってしまった。
「……蜜夏?」
様子がおかしいからか、永礼がそれまで見せていた態度とは一変し、心配した様子で蜜夏を見ている。
しばらく沈黙が続いた。
何か話さなければと焦れば焦るほど言葉が出ない。
すると、永礼が立ち上がり、蜜夏の隣に腰掛けた。
さっきまでの照れた様子が嘘のように、真剣な眼差しで蜜夏を見ている。
「無理に話す必要は無い。ただ、もし離婚の原因が俺にあるなら……絶対に直すから」
優しい声音だった。
誠実で、信頼を感じられるその物言いに、蜜夏は思わず泣きそうになってしまう。
「ち、違うんです……永礼さんには何の非も無くて……」
「本当に?」
「はい」
「そうか。蜜夏がそう言うなら信じよう」
「……っ」
そんなこと、今まで家族からも言われたことが無かった。
何を言っても聞いてもらえず、時には兄姉たちの嘘の方を信じられてしまうことも多々あった。
なのに彼は話を聞き、そして信じてくれた。
「永礼さん、私……」
顔を上げ、永礼の方を向いた瞬間、蜜夏の瞳からポロリと涙が零れる。
途端に慌てたのは、蜜夏ではなく永礼の方だった。
「なっ、なんだッ? ど、どうした! どこか痛いのか? それとも何か嫌だったのかッ?」
「ち、違います違います」
「違うものか、泣いているじゃないか! な、泣いている顔も可愛いが……いや違う! なんで泣いてるんだ! 平気か?」
とてつもなく慌てふためく永礼の姿がおかしくて、蜜夏は涙に続いて笑顔も零した。
「永礼さん、あの……ありがとうございます」
「えぇ……?」
何が何だかわからないといった様子の永礼は、しかし微笑を浮かべる蜜夏を真正面から見て、すぐに真っ赤になっていた。
「その……私が離婚を考えている理由とは別なのですが」
「な、なんだ?」
「斎賀家が今回の結婚を承諾した理由は、竜宮童子の力を狙ってのものなんです」
「ああ」
思ったよりも永礼の反応は小さく、むしろそんなことかと言った感じの気の抜けた声だった。
蜜夏は一人、首を傾げる。
「とても失礼なことだと思ったんですけど……」
「そうか? その代わり俺は蜜夏という最上級の『捧げもの』をもらえるのだから、むしろお釣りが来るぐらいだな」
あまりにも熱烈なことをさらっと言われ、蜜夏は顔に熱がこもるのを感じた。
「ああ、そういえば」
そこで永礼は思い出したように話し始める。
「富や繁栄の代わりに俺が……竜宮童子が醜くなるというのは、あくまで欲深き者を戒めるための言い伝えに過ぎない」
「そうだったんですか」
「だからもし蜜夏がそこを気にしているなら……」
「全然気にしていませんでしたよ。それにもしそうなったとしても私は……」
そこまで言いかけ、蜜夏はハッと我に返る。
続きは、一体何と言うつもりだったのだろうか。
知らず知らずのうちに、永礼に対し好意を抱いていることに気が付いた蜜夏は、自分自身の感情に慌てふためいた。
一方、蜜夏からの反応が良かったことが嬉しかったのか、永礼はこっそりと小さくガッツポーズを決めていた。
「蜜夏。良ければ、今日はこのまま……で、デートとかしないか?」
「えっ」
思いがけぬ提案に、蜜夏は目を丸くしてしまう。
離婚を考えている相手と、デート。
なんだかあまりにも矛盾している気がしたが……しかし目の前の永礼が、顔を赤くしながら真っ直ぐとこちらを見つめてくるものだから……
「し……しましょう、デート」
蜜夏は小さく頷いた。
そんな蜜夏の返答を受けた永礼は、明らかに嬉しそうな満面の笑みを浮かべる。
「良かったですね坊ちゃま。ではデートコースの手配をさせて頂きます」
突如、割って入った冷静な榊の声。
そこで二人は、榊がずっとこの部屋にいたことを思い出し、色々な意味でお互いに顔を真っ赤にするのだった。
***
デートコースは、今いるホテルの中を巡ることになった。
この竜宮グループの経営するホテルの目玉は、何といっても当人たちが腕によりをかけた一流レストランであるが、その他にもショッピングモールやカフェラウンジ、更には水族館といった施設が設けられていた。
まず二人が向かったのは女性向けのファッションブランド店だった。しかも、どちらかといえば、蜜夏よりも永礼の方が乗り気で先頭に立って中に入っていく。
「こ、こんな立派なところで洋服なんて買ったことないですよ。それに私には到底似合うと思いませんし……」
永礼を引き留め、慌てて店を出ようとする蜜夏だったが、永礼はビクともしなかった。
「蜜夏ならどんな服でも似合うし、この店はそこらの店とは違うハイブランド店だ。客である蜜夏に似合わない服を選んできたら、速攻このホテルから追い出してやる」
「なんて物騒な」
なんとも横暴な永礼に呆れつつ、気付けば複数の店員が近付いていたことに気が付く。
どの店員さんも、スマートに従業員服を着こなしている。
「永礼様、お越しいただきありがとうございます。今回はどういったご用件でしょうか」
「こちらの……俺の……俺の妻の、蜜夏の服を……み、見立ててやってくれ」
恥ずかしさからか所々つかえながら、永礼は咳払いと共にそう言い切った。
途端に、従業員たちは笑顔で蜜夏の方を向く。
「承知いたしました。さ、こちらへどうぞ」
「え、え?」
「まずは採寸から失礼いたします。そのあと好きなお色、パーソナルカラーのチェックなどをして、お洋服をお選びさせて頂きますね」
「え、え、えぇ?」
説明を受けながら蜜夏は、あれよあれよという間にフィッティングルームへと連れて行かれていた。
「永礼様が女性をお連れするのは初めてで御座います」
「しかも永礼さんの奥様だなんて……これは腕によりをかけなければいけませんね」
従業員たちはそんなことを言いながら、物凄い素早さでメジャーを使って蜜夏の採寸を終えていく。
そのまま他の従業員は、束になったカラーチャートを取り出し、蜜夏の顔の近くに何回かそれを並べ、似合う色を探しているようだった。
「あの、私そんなスタイル良くないし、顔もパッとしませんし……」
気弱にそう言う蜜夏に向かって、従業員たちはハッキリと告げる。
「そういったお客様のお悩みを考慮した上で、よりお客様を美しく魅せるのがお洋服で御座います」
「蜜夏様が自信を持って、何度でも鏡を見たくなるようなお洋服を選ばせて頂きますからね」
そんなことありませんよ、とっても可愛いです……などという気休めの言葉より何倍も嬉しい言葉だった。
もはや、その言葉だけで自信が付くレベルである。
さすがはハイブランドのお店。従業員の対応も一流なのだと蜜夏は知った。
そうこうしている内に、いつの間にか何着もの洋服がかかったハンガーラックが目の前に置かれている。
「さあ蜜夏様。順番に試着いたしましょうね」
「こ、これ全部ですか?」
「もちろんです。お気に召さないもの以外は、全て試着なさいましょう」
「ひえぇ」
どことなく圧を感じながら、蜜夏は従業員の言う通り端から端まで、全ての洋服に袖を通すことになった。
驚いたのは、どの服も本当に似合うということ。
まだ会ったばかりだというのに、まるで十年以上付き合いのある友人のように、蜜夏の好みを知り尽くしている服ばかりだった。
「素晴らしい。よくお似合いですよ」
「蜜夏様、とても良い着こなしですわ」
しかも試着する度に、従業員たちは蜜夏を褒めた。
そのお陰か、不思議と背筋がピンと伸び、姿勢良く服を着こなしていく。
そうして数十分ほどかけて試着を終えた蜜夏に、従業員は一着を差し出した。
「どれもお似合いでしたが、蜜夏様の反応的にこちらの一着をとくにお気に召していたと思われます」
言われて見たその服はまさにその通りで、本当に優秀な従業員だと感心してしまった。
「ぜひこの服をもう一度着て、永礼様にお見せしてみませんか?」
一瞬恥ずかしさが浮かんだが、よく考えれば彼はこの試着中、ずっと店内で待ってくれたことになる。
せっかく気に入った服ができたのだ。着て見せることがこの場では一番感謝の表れだと思った。
「わかりました。着ます」
蜜夏が気に入ったのは、フロントボタンが可愛らしいサロペットドレスタイプのワンピースだった。
カーキ色のワンピースとアイボリー色のブラウスがほどよくマッチしていて、派手過ぎず地味過ぎず、とてもいいバランスの服だと思ったのだ。
「本当にお似合いですよ」
従業員に背中を押されながら、蜜夏はそっとフィッティングルームから出る。
出た途端、近くのソファに座っていた永礼と目が合った。
「なっ……」
永礼は目を見開き固まった。
まるでお化けでも見たかのような驚き具合に、逆に心配になる。
「一番似合っていると思った服を着てみたんですけど……」
「……っ」
永礼は漏れ出そうな声を抑えるためか、自身の口元を必死に手で押さえていた。
最初は似合っていなくて笑いでも込み上げているのかと思ったが、その陶器のように白い肌が見る見る内に真っ赤になっていくのがわかり、どうやら違う感想を抱いているのだということがわかった。
「な、永礼さん……?」
「かっ……」
「か?」
「可愛すぎる……だろっ!」
何とか必死に声を抑えながらも、今にも叫び出しそうな声をギリギリ絞り、そうして出した言葉がそれだった。
もしここが個室だったならば、叫び出していたかもしれないほど、永礼は全力の思いを込めてそう告げた。
「こ、こっちを向くな。駄目だ。可愛すぎておまえの顔を見ることができない。さっきまでの着物姿ももちろん可愛かったが……それは反則だ。駄目だ。本当に駄目だ。いや、蜜夏が駄目なわけじゃないんだ。俺が駄目なんだ……っ!」
「永礼さん、落ち着いて下さい……」
「落ち着けるか! なんで蜜夏はそんなに可愛いんだ……ッ!」
黙ってそこに居るだけで、絵になるほど美しい男だというのに。
むしろそのポンコツ具合を自分にだけ見せてくれているところが、逆に安心できるとさえ思えた。
(本当に、本心からそう思ってくれているって伝わるから……なんか、凄く嬉しい)
蜜夏は、心に火が灯るような感覚になった。
こんな気持ちは今まで感じたことが無い。
だから少し戸惑いもしたが、不思議と嫌な感じは無かった。
「永礼様がお気に召したようで良かったです」
「ああ、よくやった。後で従業員にボーナスをやるよう店長にかけ合っておく」
まだ赤みのある顔のまま、それでもキリリとした表情で永礼はそう言った。
そして、永礼は自然な動作で蜜夏をエスコートし、店を出ようとする。
「ちょ、ちょっと待って! この洋服どうするの……っ」
「安心しろ。うちに請求が来るようにしてある。あと、着てきた服は斎賀家に届けるよう手配しておく」
「そんな……」
「自分の妻に服を買うのはそんなにおかしいことか?」
離婚する気でいたはずなのに、こんなことをされたらますます意思が揺らいでしまう。
だけど永礼の目は、むしろ買わせてほしいとねだるような眼差しで……
「わ、わかりました。ありがとうございます」
そう感謝を述べる蜜夏に、永礼は嬉しそうな笑顔を浮かべた。
こうして二人はそれぞれ思いを抱えながら、次のデートコースである水族館へと向かうのだった。
平日の午後ということもあり、水族館の中は混雑し過ぎていない丁度良い客入り具合である。
入場券を購入する際、永礼がお金を出そうとしていたが、蜜夏は服のお礼として永礼の分も支払った。
その際にも、どうしてそんなに可愛いことをしてくれるんだ、と永礼は顔を真っ赤にしながら、蜜夏の顔を立てて嬉しそうに入場券を受け取っていた。
「うわー、凄い!」
館内に入ってまず出迎えてくれたのが、プロジェクションマッピングとコラボしたクラゲのゾーンだった。
色とりどりのクラゲが入った各水槽と、プロジェクションマッピングによって美しくライトアップされた空間。
本当に水の中にいるかのような感覚に、蜜夏は心が躍った。
「蜜夏はクラゲが好きなのか?」
「そうですね……割と好きな方だと思います。見てると癒されるっていうか」
「欲しければ二、三匹持ち帰れるようにするが?」
「もう! 買ってほしいとは違うんですよ!」
この調子だと、永礼は蜜夏が興味を持ったもの全てを買い始めてしまいそうだと思った。
「そういえば、永礼さんは竜宮童子なのですから、海の生き物と仲が良かったりするのですか?」
「ああ。仲が良いというか、それなりにシンパシーを送り合うことはできる」
そう言って永礼は、長細い人差し指を水槽にそっと当てた。
すると一匹のクラゲが近付いて来て、ガラス越しに永礼の指に触れようと動く。
少し経つと、吸い寄せられるようにクラゲが群衆を成し、永礼の指先の前でフワフワと泳ぎ始めていた。
そして永礼が指を離すと、名残惜しそうにクラゲたちはユラユラと動きながら、水槽の奥の方へとそれぞれ戻っていった。
「す、凄い……!」
「そうか?」
「永礼さん、魔法使いみたいでした」
キラキラと目を輝かせてこちらを見上げてくる蜜夏を前に、永礼は咄嗟に口元を抑える。
でないとまた、可愛い蜜夏への思いが爆発しそうだったからだ。
「み、蜜夏が気に入ったなら、良かった」
怒っているのかと勘違いしてしまうほど顔をプイと背けながら、しかし安堵した様子で永礼はそう言った。
だんだん永礼の、その照れ屋なところに蜜夏も慣れてきた。
(むしろいつも本心で言ってくれるから、こっちも変に疑わずに済むんだよね)
世の中には、ニコニコと笑顔を浮かべながら嘘をつく人間がたくさんいる。
表では褒めてくれていた子が、裏では悪口といっしょにけなしていたり。
だけど永礼は違う。
本心からの言葉をくれて、本気の姿を見せてくれる。
そんな永礼だからこそ、本当にそう思ってくれているのだと、安心して一緒にいられるのだった。
「永礼さん、次はトンネルゾーンですって。通路がトンネル状になっているから、海の中にいるみたいな……きゃっ」
「蜜夏!」
人とぶつかってしまった蜜夏は、思いのほか相手との体格差があったためそれなりに突き飛ばされてしまう。
大きくよろけた蜜夏は転ぶことを予期したが……しかし体ごと誰かに抱きとめられていた。
「永礼さん……」
「平気か、蜜夏?」
「だ、大丈夫です」
至近距離に永礼を感じてドキドキしながらも、後ろからすみませんという謝罪の声が聞こえ振り返った。そこには今ぶつかり合ってしまった相手が、申し訳無さそうに頭を下げていた。
「いえ、こちらこそすみません。前を向いてなかった私が悪いんです」
そう伝え、相手は何度かぺこぺこと頭を下げながら、進路とは逆の方を歩いていった。
「永礼さん、受け止めてくれてありがとうございます」
もしあの時永礼が受け止めてくれなければ、倒れ込むように転んでいたはずだ。
せっかく買ってもらった洋服も汚していたかもしれない。
「……永礼さん?」
ふと、いつまで経っても永礼から何の応答も無いことに気が付いた。
そっと顔を見上げてみれば、そこには真っ赤な顔をして天を仰いでる永礼の姿があった。
どうやら反射的に蜜夏を抱きしめたはいいものの、冷静になってきてから、この密着した状態に照れを感じ始めてしまったらしい。
「くっ……永遠にこうしていたい」
「え?」
「半分冗談だ。蜜夏が無事で良かった」
永礼はそう言いながら、名残惜しそうにではあるが蜜夏から離れた。
離れるまでドクドクと響いていた胸の鼓動は、果たしてどちらのものだったのだろうか。
「……蜜夏」
「は、はい」
「その……手を繋ぐのはアリだろうか?」
スッと差し出された、白く美しい永礼の手。
それはまるでダンスのお誘いをする貴公子のように優雅な姿で、ドキリと蜜夏の心臓が跳ねる。
「て、手を……?」
「嫌か?」
少しだけ永礼の表情が悲しみに曇る。
それを見て蜜夏は、慌てて首を横に振った。
「嫌じゃないです。そうじゃなくて、初めてのことでちょっと恥ずかしかったから……」
「そうか。なら失礼して……」
永礼は鮮やかな動作で蜜夏の手を取り、優しく握る。
そこまでは優雅に決めていた永礼だったが、手を握った途端にやはり顔を真っ赤にさせていた。もちろん蜜夏の顔も負けないくらい真っ赤だった。
傍から見れば実に初々しいカップルである二人は、手を繋いだまま水族館側が用意した進路を進む。
先程、蜜夏が言っていた通り、次はトンネル状に作られた水槽のゾーンだった。
左右はもちろん、自分の真上にも魚たちが泳いでおり、海の中を散歩しているような気持ちだった。
「わぁ、凄い。海の中を歩いてるみたい」
そこまで言って、ふと蜜夏は気になることができた。
「もしかして永礼さんも、こうやって海の中を歩いたりできるんですか?」
「ああ」
あっさりと返答され、蜜夏は改めて彼があやかしなのだと感じた。
「もう少し陽の光は少な目だが、実際にこういった感じだ。よく再現されていると思う」
言いながら、上空を泳ぐ魚たちを目で追う永礼の姿は、海の王子様のようだった。
何かと照れた様子を見せるから忘れがちだが、永礼の容姿や振る舞いは実に優雅で美しい。
現にこの水族館に入ってから、男女問わず一度は永礼を視界に入れて見惚れている人ばかりだ。中には露骨にキャッキャとはしゃぐ女子グループもいるぐらいである。
(そんな人が、あんなにも取り乱すぐらい私のことを可愛いって言ってくれるなんて……)
「どうした蜜夏。顔が赤いぞ」
「えっ」
「熱でもあるのか? デートは中止にするか?」
心配そうに顔を覗き込んでくる永礼に、蜜夏はますます顔を赤くさせてしまう。
(なんか、永礼さんの照れる癖がうつったみたい……っ!)
蜜夏は慌てながら弁明した。
「熱とかじゃないです! な、なんていうか……デートって初めてなので、永礼さんのこと意識してしまって、その……」
「……ッ!」
途端に、今度顔を赤くするのは永礼の方であった。
「んなっ、何を……み、蜜夏……だからなんでそんなに可愛いことを……っ」
「し、知りませんよ! それに永礼さんがすぐそうやって顔を赤くするから、私まですぐ顔が赤くなるようになっちゃったんですから」
傍から見てバカップルのようなやり取りをしていることに二人は気付いていない。
こんな調子で、水族館の各展示を二人はスムーズに進んでいった。
今日初めて会ったとは思えないほど話は弾み、時にはお互いに照れて顔を赤くしながら、ずっと笑顔の絶えない時間が続く。
そうして二人は、イルカショーのあるエリアに到達した。
見晴らしの良い、やや遠めの席に横並びになる。
「見るところが多くて、けっこう歩きましたね」
「そうだな。疲れていないか?」
「大丈夫です。むしろたくさん色んなお魚が見れて楽しいです」
「そうか」
蜜夏が笑顔になると、永礼もまた、嬉しそうに微笑する。
「水族館をデートコースに入れておいて良かった。榊にも後でボーナスをやらないとな」
「そういえば、榊さんはあやかしなんですか? それとも人間?」
「榊は俺の親父の代から側近をしてくれている人間だ。仕事で忙しい両親よりも俺に構ってくれていたから、もはや親のようなものだな、榊は」
「榊さん、凄く永礼さんを大切にしていますもんね」
デート前のやり取りだけで、榊がどれだけ永礼を可愛がっているかわかった。
きっと榊自身も、永礼に対しては主人としてだけでなく、我が子か孫でも見ているような気分なのだろう。
「蜜夏はどうなんだ?」
「え?」
不意に返ってきた質問に、蜜夏は永礼の方を向く。
「榊のような仲の良い使用人はいるのか? そういえば兄姉もいるんだったな。仲は良いのか?」
途端に、キィンと耳鳴りがした。
まるで今までのデートの時間が夢のように、一気に現実に戻される気分だった。
目を見開いて固まる蜜夏に、永礼は首を傾げる。
「蜜夏……?」
「あ、いえ、あの……」
これまで楽しく過ごしていたからか、家のことを考えると思いっ切り心が沈んだ。
そして思い出す。家での辛い日々を。
永礼が優しく誠実に扱ってくれるから、家で自分がどういった扱いを受けていたのか忘れてしまっていた。
(そうだ……私、家を出たいんだった……)
もうあの家と関わりたくない。家を出たい。
その気持ちが一気に溢れ出し、蜜夏は永礼に告げた。
「……永礼さん」
「どうした?」
「やっぱり私……離婚、しないと、です」
暗鬱な気持ちが背中からおぶさってくるようだった。
少し前までの楽しい気持ちが、おまえには過ぎたものだと言われているようで、とても苦しい。
「……どうして?」
しかし永礼の声音は落ち着いていた。
蜜夏の本気度を感じているからか、デート前のように駄々をこねたりはしていない。
代わりに真っ直ぐと蜜夏を見て、言葉の続きを待っている。
「私は、その……家から出たいんです」
「………」
「だけど永礼さんと結婚してしまったら、それは叶わなくなってしまうから……だから……」
しばらく、永礼は黙っていた。
周囲ではイルカショーを楽しみにする人たちの声でざわめいているが、それらがまるで耳に入ってこないぐらい、お互いに話に集中している。
そんな中で蜜夏は、離婚のことを言葉にしてしまった自身に後悔が生じていることに気が付いた。
(ああ……いつの間にか永礼さんと離婚したくないって思うようになっていたなんて……)
自分自身の感情に戸惑う蜜夏の前で、永礼はゆっくりと口を開く。
「家を出たいと思うぐらい、蜜夏にとっては何か重い感情があるのだと思う。それを話してくれてありがとう」
永礼から出た最初の言葉は、問い詰めではなく感謝だった。
予想していなかった永礼の態度に、蜜夏は呆気に取られた表情で話の続きを待つ。
「蜜夏が家を出たいという気持ちはわかった。だけど……俺はどうしても、蜜夏と離婚なんてしたくない。今日初めてこうして話をした間柄だが、俺は蜜夏と過ごした今日が、かけがえのないものとなっている。蜜夏は……どうだろう?」
「それはっ……私も、同じ気持ちです」
蜜夏自身も、永礼と過ごした今日一日が本当に楽しかった。
家で出来損ないとしてあまり外に出してもらえなかった日々と比べたら、こんなにも幸せな時間は無いだろう。
「蜜夏。これからはウチで暮らすというのはどうだろう?」
「え……?」
「蜜夏の家の者が許すなら、これから蜜夏は竜宮家の花嫁としてウチで暮らせばいい」
「それは……」
それは願ってもない提案だった。
竜宮家がどんなところかはまだわからないが、少なくとも斎賀家で過ごすあの重苦しい生活からは解放されるだろう。
「でも、私……私は……」
永礼への思いと、家への思いが、蜜夏の中でぶつかり合った。
ここが往来の場であることも忘れ、ボロボロと涙を流す。
「私は、出来損ないで……竜宮家の人にも、きっと……きっといっぱい迷惑を……っ」
そこまでを口にした瞬間、永礼が、優しく、そして力強く、蜜夏を抱き締めた。
「……もう言わなくていい。俺もそれ以上は詮索しない」
「永礼さん……」
「俺は蜜夏に幸せになってほしいし、幸せにしたいと思っている。だから、俺ができることならなんでもするから……どうか、離婚するだなんて言わないでくれ」
永礼が発する言葉の一つ一つが優しかった。
抱きしめている腕の温もりも、触れ合う箇所から聞こえてくる心臓の音も。
全てが優しくて、誠実だった。
だから蜜夏からも、永礼をギュッと抱き返していた。
「永礼さん……ごめんなさい。自分のことばかりで……っ」
「何を言っている。俺だって俺のことばかりだ。俺は蜜夏と離婚をしたくなくて必死なだけだ」
そんなわけはない。
もしそうだとしたら、こんなにも相手を思いやった言葉など出てこないものだ。
二人は抱き合った余韻を感じながら、ゆっくりと距離を戻す。
それでも心の距離は、さっきよりも近くなった気がした。
「これから永礼さんの妻として……永礼さんのおウチにお邪魔することになっても、いいですか?」
「もちろんだ」
ニコリ、と微笑した永礼に、蜜夏は頬を染める。
気付けば、イルカのショーがちょうど始まるところだった。
二人は手を繋ぎ合ったまま、ステージに立つ飼育員とイルカたちを眺める。
そんな二人のことを、近くの柱から黒服の男が観察していることに、当人たちは知る由も無かった。
***
「……カワイイ」
ベッドに横たわりながら、蜜夏はクラゲのぬいぐるみをツンと突いた。
先日のデートの際、水族館で永礼が買ってくれたものだ。
あの後、イルカショーで気持ちを打ち明けられたからか、より話が弾むデートになった。
水族館を出て、竜宮家が営むレストランで食事となったが、次から次へと出てくる料理と同じように、二人の話題も尽きることが無かった。
目の前に並ぶ料理を味わう蜜夏と、そんな蜜夏の可愛さを味わう永礼。
永礼に好きな料理は何かと問えば、蜜夏が握ったおにぎりと返ってくる。
そんな話の流れから、今度はピクニックにでも行こうかという話にまで発展した。
(ほとんど初めて会ったようなものなのに……凄く話が弾んで楽しかったな……)
デートのことを思い返しながら、自然と蜜夏の口元は緩んだ。
何気に嬉しかったのは、永礼だけでなく榊との連絡まで交換できたことだ。
永礼いわく、結婚しているのだから竜宮家の使用人は蜜夏の使用人でもあるとのこと。
そして榊いわく、自分は坊ちゃまと蜜夏お嬢様の行く末をどこまでも応援するということ。
永礼だけでなく、まさか榊まで味方になってくれるとは思っておらず、蜜夏は嬉しさのあまりその場で若干涙ぐんでしまった。
そんな楽しかった思い出から数日経った。
まだたった数日だというのに、また永礼に会いたいと蜜夏は感じている。
(離婚しようと思ってたのが嘘みたい……)
クラゲのぬいぐるみをギュッと抱きしめながら、ちょっとした切なさを覚える。
あのデートの日、永礼は最初から最後まで蜜夏のことを思いやり、時には大きく照れてみせ、そして誠実であった。
蜜夏からすれば、今まで誰からもそんな対応をされたことがなかった。だから永礼の一挙手一投足に驚きながらも、それでも最後には幸せな気持ちになっていた。
それに、榊が時折見せる永礼への態度を見ているだけで、永礼が実に信頼に足り得る男なのだということも伝わってきた。
(本当に離婚してしまわなくて良かった……)
思えば、自分の都合だけで離婚を考えてしまった。そのことを蜜夏は深く反省した。
そして今となっては、離婚の提案をきっかけに、永礼と色々なことがわかり合えて良かったとすら思っている。
(次はいつ会えるかな)
そんなことを思っていた矢先、突然着信音が鳴り響いた。
画面を見ると、そこには『榊さん』の文字。
一体どうしたのかと、蜜夏は慌てて応答する。
「も、もしもし?」
『蜜夏お嬢様。突然のご連絡大変失礼いたします。実は今……蜜夏様のご家族が竜宮家に来ておりまして……』
「えっ? わ、私は何も聞いていないです」
家族が、蜜夏だけを省いて何処かへ出かけることはしょっちゅうあった。
そんなことにはもう慣れているので、蜜夏もたいして気に留めることもなくなった。
しかし、その行き先が竜宮家であるなら話は別だ。
「家同士のご挨拶でしょうか? でしたら私も急いで行かないと……」
『いえ。どうにもそういったものではなく……どうやら蜜夏お嬢様の姉君の方が永礼様と結婚をしないか、という話になっておりまして』
「え……ッ?」
まったく予期していなかった話の内容に、頭から冷や水をかけられたかのような気分になった。
「わ、私そんな話、全然っ……」
焦るあまり、上手く言葉が出てこない。
それでも電話越しの榊は、とても冷静に、そして優しい口調で続けてくれた。
『やはりそうでしたか。斎賀様たちはアポイントも無く乗り込んできて、永礼様の花嫁を長女の方にするよう提案してきたのです』
「………」
『しかもその理由が、蜜夏様がご自身で、永礼様は自分にはもったいない方だからお姉さまに永礼様を譲りたい、と仰っていたと言うのです。本当でしょうか?』
「そんな……そんなこと言ってないです。確かに永礼様は自分にはもったいないほど素敵な方ですが……それでも私は……私は永礼さんと別れたくないです!」
『その言葉が聞けて安心しました』
蜜夏自身も、自分の中に離婚の意思がもうこれっぽっちも無いことに気付かされた。
『蜜夏様。榊は先日のお二人のご様子を見て、それはもう素敵なご夫婦であると感じました。末永く、お二人で手を取り合っていってほしいと、心からそう思ったのです』
「榊さん……」
『ですから、もし蜜夏様が坊ちゃまとの離婚を考えていないのであれば……今からウチの送迎車を向かわせますので、こちらにお越しになりませんか?』
榊の言葉に、蜜夏は一度口を閉じる。
今まで、家族に逆らうようなことはしてこなかった。
そして永礼とは始め、離婚をするために出会った。
だけど今は違う。
永礼と離婚なんてしたくないし、何より、永礼が他の女性のものになってしまうなんて、そんなの嫌でたまらなかった。
たとえそれが自分の家族であろうとも……蜜夏は、断固としてお断りだった。
「送迎車を、お願いします。永礼さんの妻は私ですから」
『ええ、奥様。ただちに向かわせます』
電話の向こうで、榊が嬉しそうに微笑むのがわかった。
そうして蜜夏は、覚悟を決め、急いで出掛ける準備をするのだった。
***
「それで、話と言うのは?」
時は少しさかのぼる。
多忙な身である永礼が、先約であった会食をキャンセルし、こうして応接間にいるのは、相手が蜜夏の家族であるからだ。
斎賀家の当主であり蜜夏の父親の峰近、そして長女の愛華が、今目の前にいる。
榊が丁寧な所作でテーブルにお茶を出し、退席したところで話が始まった。
「この度は、ウチの出来損ないと婚約して下さり、大変に有難く思っております」
「出来損ない……?」
おそらく峰近は、謙遜と真実を混ぜた上で、本心からそう言っている。
だが永礼からしたら、愛しくて大好きな自身の妻を馬鹿にされたようにしか聞こえなかった。
もちろんこんなことで声を荒げる気はないが、相手によってはとっくに手が出ていただろう。
「蜜夏さんは出来損ないなんかじゃないですよ。先日顔を合わせた時も、より結婚して良かったと思ったぐらいです」
「ハハハ。竜宮童子どのは気遣いのできるお方で助かります」
どこまでも蜜夏を出来損ない扱いしたい峰近に嫌気が差し、永礼は峰近の隣に座る愛華の方へ視線を移した。
途端に愛華は頬を染め、一目で高価だとわかる豪華な着物の袖で上品に口元を隠した。永礼でなければ、その所作にドキリとしたことだろう。
そのことがわかっていない峰近は、二人が良い雰囲気を作っていると思い込んだまま話を続けた。
「いや今回はですね、その蜜夏との結婚のことでお話がありまして」
「なんですか?」
「良ければ愛華と結婚いたしませんか?」
「は……?」
寝耳に水なほど、まるで予想していなかった話の内容に、思わず永礼はそう返してしまった。
だが峰近からすると、永礼の反応はとてもいい話に驚いているように見えたらしく、意気揚々と笑った。
「竜宮童子どのはおそらく、ウチの愛華のことを知らずに結婚を申し込まれたのかと思いましてな。蜜夏は料理の腕も無ければ器量も良くない娘でして。それに比べ、長女の愛華は親の自分が言うのもなんですが実によくできた娘でして。料理界の今後の発展を考えれば、愛華との結婚の方がずっとプラスになることでしょう」
「やだ、お父様ったら」
豪快に笑う峰近に、しおらしく笑う愛華。
その二人を前に、永礼は眉根を寄せることしかできなかった。
どうにも話が噛み合わない。
それというのも、峰近は永礼が料理界を盛り上げるために結婚を申し込んできたと思っているからだ。
さらに先日の蜜夏とのデートには、愛華専属の黒服が、デートの様子を事細かに愛華へとリークしていた。
そこで知ったのが、永礼の見た目が予想していた以上に美しいことと、富と繁栄の代わりに醜くならないということだった。
そうなると尚更、愛華は自分より先に蜜夏が、しかもあんなにも格好いい殿方と結婚することが気に食わなくてたまらなかった。
だから愛華はいつも以上に父親におねだりをし、こうして永礼の花嫁を自分にしてしまおうと画策したのだった。
「永礼様」
愛らしい声音で、愛華は永礼の名を呼ぶ。
「永礼様にとって『捧げもの』というのはとても重要なものなのでしょう? 私でしたら、永礼様にとって大事な『捧げもの』になると思うのです。その覚悟も御座います」
「………」
「永礼様が斎賀家に富と繫栄をもたらして下さる代わりに、私が永礼様と永遠に添い遂げます。蜜夏とは違って、私には料理の才能もありますし、華道や茶道もしっかり嗜んでおります。私たちなら、竜宮家と斎賀家を結ぶのに相応しい結婚となるでしょう」
愛華は乙女が祈るように両手の指を絡め、その大きな目をパチパチと瞬きさせながら、永礼の方を見た。
そしてその隣に座る峰近は、自分の娘の言葉に、うんうんと満足そうに頷くばかりだった。
「………」
永礼は何も言えなかった。何から話せばいいかわからなくて。
永礼にとって蜜夏以外の者との結婚なんて、まるで考えられない。
愛華は自身を立派な『捧げもの』だと自負しているようだが、永礼からすれば蜜夏ほどの『捧げもの』はこの世に無いのだ。
果たしてどこから否定し、訂正し、言い聞かせればいいのか。
永礼の端正な顔に疲れが見え始めた、その時。
「失礼します!」
勢いよく扉が開き、三者が何事かとそちらを見る。
峰近と愛華は顔を歪め、そして永礼は目を見開き固まった。
「お話中すみません。でも、言わせて下さい。永礼さんの妻は、私です!」
そこにいたのは蜜夏だった。
急いで来たからか上気した頬を赤く染めながら、蜜夏はハッキリとそう告げた。
「蜜夏……っ」
思わぬ蜜夏からの宣言に、永礼は真っ赤になって口元を抑える。
一方、峰近と愛華は一瞬だけ呆気に取られ、そしてすぐに怒りの表情を浮かべた。
「蜜夏……おまえ! 会談中に入ってくるなどふざけるな。わきまえろ!」
「……っ」
峰近の怒鳴り声に、蜜夏はビクリと体を揺らす。
それでも蜜夏はその場から動かなかった。
「蜜夏さん、何を考えているの? こんな失態を永礼様に見せるだなんて……本当にあなたって斎賀家の恥さらしだわ」
「でも……でも私は、永礼さんの妻です」
「残念ね。妻になるのはこの私よ。あなたに永礼様はもったいなさ過ぎるでしょ?」
それは確かにそうかもしれない。
もったいないぐらい、永礼は素敵な人である。
だけど……それでも蜜夏は退かなかった。
「確かに永礼さんは自分にはもったいないかもしれません。だからこそ、これから……これから私は、永礼さんに相応しい妻になっていこうと思うのです」
「蜜夏……」
永礼は思わず蜜夏の名を呟いていた。
そうして立ち上がり、蜜夏の傍に立つ。
「永礼さん……」
「蜜夏。君がそう思うように、俺だって蜜夏に相応しい夫になれるよう、これから切磋琢磨するつもりだ」
「そんな……永礼さんは今でもう充分なのに」
「ならば蜜夏だってそうだ。今の蜜夏のことが、俺は愛しくてたまらないのだから」
二人は静かに見詰め合う。
そのまま口付けしてしまってもいいほどに、愛に満ちた雰囲気が漂っていた。
ただしこの場には、峰近と愛華、そして蜜夏と共に駆け付けた榊の姿がある。
良いムードは一旦おあずけだった。
「斎賀さん」
永礼は蜜夏から視線を外すと、鋭い目つきで峰近を貫いた。
「俺にとって『捧げもの』は蜜夏以外にあり得ない。その蜜夏を……俺の『捧げもの』を奪うということは、富と繁栄が無くなっても構わないということですが……それで良いのですか?」
瞬間、峰近の顔が歪んだ。
「『捧げもの』が無いならば、俺が富と繁栄をもたらす道理など無い。むしろ、俺から『捧げもの』である蜜夏を奪うという罰当たりなことをするならば、末代までの不幸が訪れても文句は言えまい」
「んなっ……なんだとッ?」
「そうなりたくなければ、蜜夏との結婚を認め、今後は蜜夏に関わらないと誓って下さい。そうすれば斎賀家にそれなりの富と繁栄をもたらしましょう。もちろんこの約束を破って蜜夏に接触しようものなら……言わなくてもわかりますよね?」
「う、ぐ……」
ついに峰近は黙り込んでしまった。
元々、竜宮童子の力に目がくらんでの結婚だった。
峰近にとって最も大事なのは、娘の幸せよりも家の繁栄なのだ。
「あ……愛華、帰るぞ」
「そんな!」
「竜宮童子は蜜夏と結婚した。今日はそれを認めに来た。それだけだ」
「お父様ッ!」
これ以上、永礼の不興を買うまいと、峰近はそう言って部屋を出て行く。
愛華は一度だけ蜜夏を睨みつけたが、すぐに峰近の後を追って退出していった。
「………」
嵐が過ぎ去った後のように、部屋にしばし沈黙が続く。
先に口を開いたのは永礼の方だった。
「……蜜夏」
「は、はい」
蜜夏がゆっくりと顔を上げると、そこには顔を真っ赤にしながらも、喜びでとろけそうな優しい表情を浮かべる永礼の姿があった。
「蜜夏が俺の妻だと言って現れた時……幸せで心臓が止まるかと思ったぞ」
「そ、そんな大袈裟な」
「大袈裟なものか。本当に嬉しかった」
「永礼さん……」
永礼の言葉はいつだって本心で、そして誠実だ。
蜜夏自身、永礼の妻だと宣言するのは勇気のいる行為だった。
けれど永礼が他の女性の……しかも姉のものになってしまうことを考えただけで、居ても立っても居られなかったのだ。
だからほぼ勢い任せで言ってしまったのであるが……
永礼がそれを心から嬉しく思っていることが、蜜夏にとっても幸せなことであった。
「それにしてもどうして蜜夏が此処に……?」
「榊さんが教えてくれたの」
言われて永礼は、今更ながらドアの近くで待機している榊のことを思い出した。
榊はいつものように姿勢よくその場に立っている。
「私はお二人の幸せを願っておりますので。それに坊ちゃまが、蜜夏お嬢様以外を嫁にするとは到底考えられませんでしたので」
「なるほど。よくやってくれたな榊」
「身に余る光栄です」
榊は胸に手を当て一礼する。
そうして部屋を出て行こうとする前に、永礼の方を向いて告げた。
「坊ちゃま。榊は退出しますからね」
「わ……わかっている」
「……?」
何でもお見通しだと言わんばかりの榊と、見通されていたことを恥ずかしがる永礼と、まるでわかっていない蜜夏。
永礼は何を恥ずかしがっているのだろうと蜜夏は思ったが、榊が退出したのを確認し、再び永礼から名を呼ばれた。
「……蜜夏」
「はい」
「さっきの斎賀家とのやり取りで、蜜夏が家のことで悩む必要はもう無くなった。今日からは竜宮家で暮らしていいし、そのことで家族が何か言ってくることも無いだろう」
「永礼さん……なんてお礼を言ったらいいか……」
「俺の妻なのだから、これぐらいして当然だ」
「……っ」
力強い永礼の言葉に、じんわりと涙が浮かんでしまう。
それを、優しい手付きで永礼が拭う。
「泣かないでくれ。俺は……笑っている蜜夏が一番好きだ」
恥ずかしさから一度視線を反らしつつ、もう一度改めて蜜夏を見つめ、永礼はそう告げた。
永礼は何度も蜜夏のことを可愛いと言ってきたが、蜜夏からすれば永礼だって本当に可愛いと思う。
だから、蜜夏は言った。
「あの、永礼さん」
「なんだ?」
「キス……してもいいですか?」
「なっ、なななんっ?」
貴公子のように整った顔が台無しなぐらい、永礼は大きく慌てふためいた。
「なんだか、自然とそう思ったんです。駄目ですか?」
「そ、それ、それはっ……」
何故か悔しそうな顔をする永礼に、蜜夏は少しずつ自信を無くしかけた。
やはり女性からそんなことを言うのははしたなかっただろうか。
だが、蜜夏のそんな不安を吹き飛ばすように、永礼は言う。
「それは、俺が先に、言いたかった……っ!」
「へ?」
「榊が退出したから、俺から蜜夏に口付けていいか言おうと思っていたのに……なのに……っ!」
そこでようやく、部屋から退出する際の榊と永礼のやり取りの意味がわかった。
榊は言葉にせずとも、永礼の背中を押していたのだ。
「ぷっ……あははっ、はははは」
思わず蜜夏は笑う。
こんなふうに笑うのは一体いつぶりだろうかと思った。
斎賀家でずっと姿を隠すように生きてきたのに、永礼のお陰でこんなにも生きていることが嬉しくて幸せだと感じることができた。
榊という素敵な人とも知り合うことができた。
何より、永礼という最高の夫が傍にいてくれる。
「……蜜夏」
「あはは、あ、はい?」
笑いながら永礼の方を向く。
そうして感じた、唇に当たる柔らかい感触。
気付けば、永礼に優しく口付けられていた。
「……へ?」
永礼の唇が離れ、その美しい顔を間近で見ながら、蜜夏は気の抜けた声を上げる。
「あの、今……」
「もう一度、してもいいか?」
顔を赤くしながらも、真剣にそう訊ねてくる永礼の表情は王子様そのもので。
蜜夏は一つ、静かに頷いた。
「んっ……」
ゆっくりと唇が触れ、それだけで脳が痺れるような感覚に陥る。
触れるだけの口付けなのに、体の芯が温まり、幸福感が確かにあった。
「蜜夏ほどの『捧げもの』は他に無いんだ。だから……もう二度と、離婚だなんて言わないでくれ」
「……はい」
そうして二人は、再び口付けを交わした。
離婚から始まった関係を、心から祝福するように。
【完】