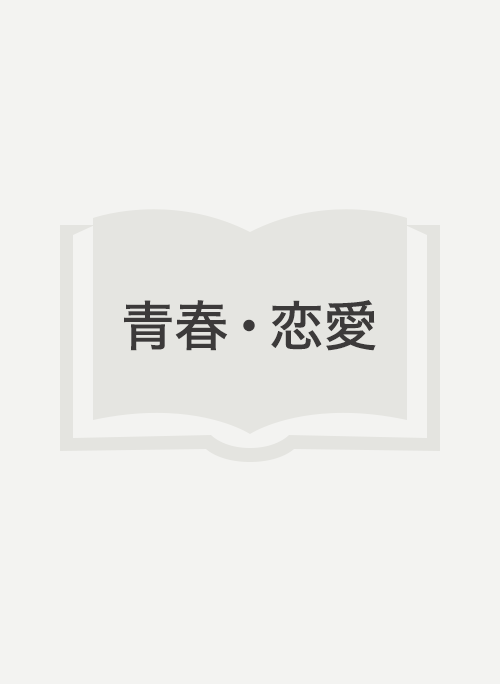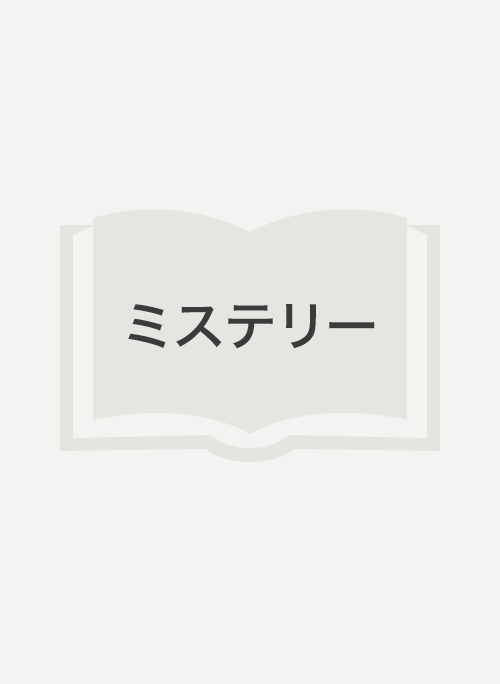憂鬱な試験が終わって陰鬱な彼と、ロートレック展に行った。アンリ・マリー・レイモン・ド・トゥールーズ=ロートレック=モンファといえばバズ・ラーマン監督の『ムーラン・ルージュ』とジョン・ヒューストン監督の『赤い風車』を思い出す。わたしは後者の方が、主題歌ともども好き。考え方によっては、不具者は五体満足な人間よりも精神的に平静であるかも知れない。『五体不満足』の乙武洋匡はどう言うだろう。わたしのように、見方によっては、ある角度から見ると美人に見え、別の角度から見ると十人並みに見え、また他の角度から見ると不美人に見えるような顔の女は、相手がどの角度から見た自分を本当の自分と思っているのだろうかと、つまらないことで思い悩む。ところが、不具者は、だれが見ても不具者だ。誰も健常な人間とは見てくれない。だから、他人が自分のことをどのように見ているかと、推察して余計なことに頭を巡らせる必要はない。ジャン・ポール・サルトルは誰が見たってシモーヌ・ド・ボーヴォワールよりロンパリだし、だれが見たって彼女より小さい醜男だ。だから彼は他人の視線をあまり気にする必要はなかった。間違ったって、『制服の処女』のロミー・シュナイダーや『シェルブールの雨傘』のカトリーヌ・ドヌーブが彼にほのかに思いを寄せるなどと言うことありえないのだから。彼が文筆に専心できたのは、そのためかも知れない。彼が、『太陽がいっぱい』のアラン・ドロン(同じフランス人でも、何と異なることか!)のような美男子だったら、ジャコモ・カサノバのように、長い長い回想録をしたためていたかもしれない。あるいは、ジャン・ポール・ベルモントやスティーブ・マックウィーンのように気さくないい男だったら人生そのものを活動的に楽しんでいたかもしれない。アンリ・マリー・レイモン・ド・トゥールーズ=ロートレック=モンファは、そういう心境で絵やポスターを描いていたに相違ない。いや、そういう心境だったからこそ、絵を描かずにはいられなかったのだ。
メニュー