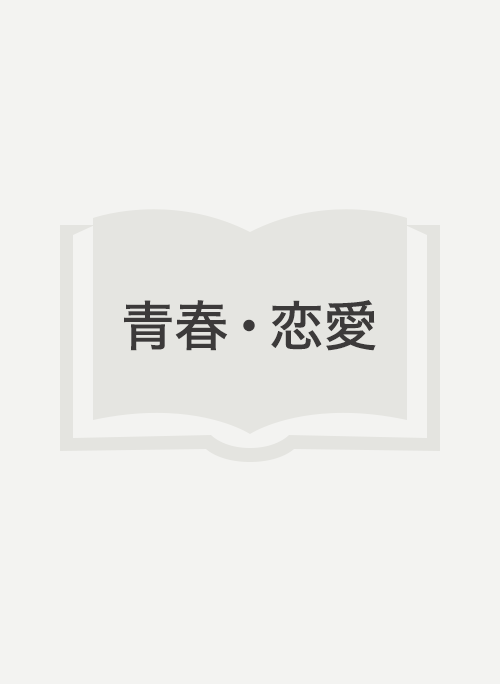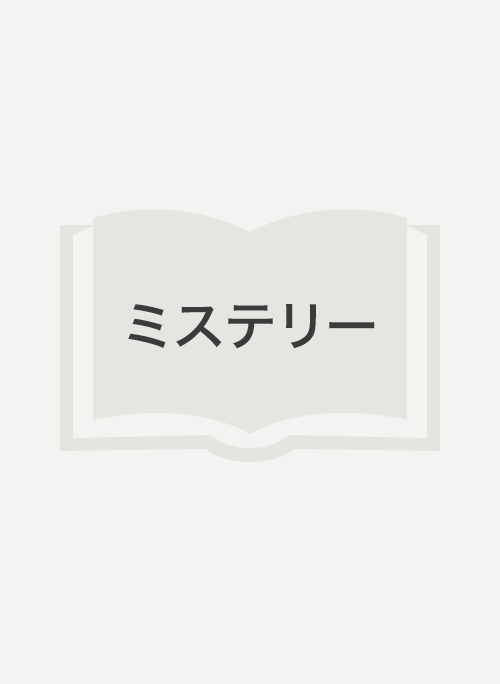心の鎧はいつも
固く冷たく閉ざされていた
白い追憶
優しさが想い出される
雪の季節にいつ果てるともない
白い追憶 あなたの愛しさ
街には雪が わたしにはみぞれ
あなたが心のポケットベルを
鳴らし続けていたけれど
わたしの心は留守番電話
テープ戻して伝言を聞く
苦い追憶
あなたが今でも望むのならば
愛し続けているならば
わたしの心は電子のメール
すぐに駆けてくどんなとこでも
愛の追跡
冬の田舎は掘り炬燵を囲み、カタカタと木枯らしになる板戸に耳を傾け、春を待つのが日々の営み。掘り炬燵は田舎の社交場。虚飾も嘘もない全裸の会話。いま、一人の来訪者。コトコトと板戸を開け、パタパタと体に纏い付く雪を叩き落す。ポッポッと燃える燠の火。口笛を吹く火鉢の鉄瓶。ああ、かかる日のノスタルジア。
冬の田舎は風呂場の湯気が、窓の外の雪景色を背景に、ユラリユラリとフラダンスをする所。竈に投げ込む湿った杉の薪木、その吐く溜息が目に染みる。燃えろ、燃えろ、みんな燃えろ。赤く、赤く、灰燼になるまで。どんどんくべろ、薪木をくべろ。みんな、みんな燃え尽せ。寒い寒い冬を追い払うため、わたしの代わりに燃えとくれ。わたしのこの冷たい命。わたしのこの冷ややかな体。炎となってメラメラと燃え上がることを知らないこの唇。心の冬に冷やされて、硬い蕾の儘のこの胸。決して溶けることのない万年雪のようなこの心。みんな、みんな、燃えてしまえ。こんな体なんか、燃えてしまえ!ああ、かかる日のノスタルジア。
ああ、パリの空の下で身も心も焦がしつくすような、いずみあきらの『フランシーヌの場合』のような命が激しく燃え上がるような恋をしたい。ルネ・クレマン監督が『パリは燃えているか』を1966年に撮った後、1969年にフランシーヌは焼身自殺した。そこで、トム・ジョーンズの『ラヴ・ミー・トゥナイト』のような歌が生まれる。
あなたの瞳に燃える愛の野獣
わたしの涙に濡れる夜のしとね
そうよ ふたりの愛は今
熱く密かに燃え上がる
今宵こそは唇合わせ
ああ この髪に指を絡ませ
愛して あなた この胸に頬埋めて
愛して あなた 夜の帷 開くまで
固く冷たく閉ざされていた
白い追憶
優しさが想い出される
雪の季節にいつ果てるともない
白い追憶 あなたの愛しさ
街には雪が わたしにはみぞれ
あなたが心のポケットベルを
鳴らし続けていたけれど
わたしの心は留守番電話
テープ戻して伝言を聞く
苦い追憶
あなたが今でも望むのならば
愛し続けているならば
わたしの心は電子のメール
すぐに駆けてくどんなとこでも
愛の追跡
冬の田舎は掘り炬燵を囲み、カタカタと木枯らしになる板戸に耳を傾け、春を待つのが日々の営み。掘り炬燵は田舎の社交場。虚飾も嘘もない全裸の会話。いま、一人の来訪者。コトコトと板戸を開け、パタパタと体に纏い付く雪を叩き落す。ポッポッと燃える燠の火。口笛を吹く火鉢の鉄瓶。ああ、かかる日のノスタルジア。
冬の田舎は風呂場の湯気が、窓の外の雪景色を背景に、ユラリユラリとフラダンスをする所。竈に投げ込む湿った杉の薪木、その吐く溜息が目に染みる。燃えろ、燃えろ、みんな燃えろ。赤く、赤く、灰燼になるまで。どんどんくべろ、薪木をくべろ。みんな、みんな燃え尽せ。寒い寒い冬を追い払うため、わたしの代わりに燃えとくれ。わたしのこの冷たい命。わたしのこの冷ややかな体。炎となってメラメラと燃え上がることを知らないこの唇。心の冬に冷やされて、硬い蕾の儘のこの胸。決して溶けることのない万年雪のようなこの心。みんな、みんな、燃えてしまえ。こんな体なんか、燃えてしまえ!ああ、かかる日のノスタルジア。
ああ、パリの空の下で身も心も焦がしつくすような、いずみあきらの『フランシーヌの場合』のような命が激しく燃え上がるような恋をしたい。ルネ・クレマン監督が『パリは燃えているか』を1966年に撮った後、1969年にフランシーヌは焼身自殺した。そこで、トム・ジョーンズの『ラヴ・ミー・トゥナイト』のような歌が生まれる。
あなたの瞳に燃える愛の野獣
わたしの涙に濡れる夜のしとね
そうよ ふたりの愛は今
熱く密かに燃え上がる
今宵こそは唇合わせ
ああ この髪に指を絡ませ
愛して あなた この胸に頬埋めて
愛して あなた 夜の帷 開くまで