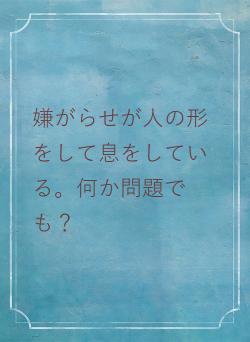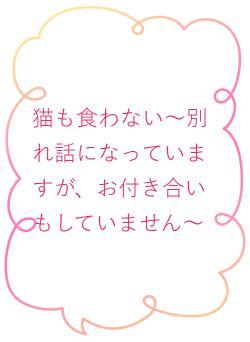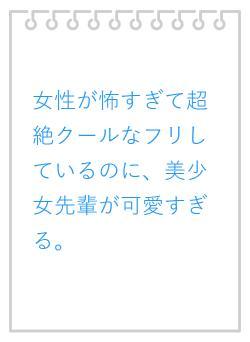春になる頃、「あのパティスリー、店の中で食べることもできるんです。バニラアイスを添えた林檎のパイは格別に美味しいですよ」とレナートが言い出した。
大好物なのである。そこまで言われたら、ミリアも断ることができなかった。
屋敷からの外出ということで、ダリアは留守番。
はじめて、ふたりで会った。
レナートの話しぶりは、外で会っても四阿で話していたときと何程も変わらず。もう慣れ親しんだ彼との会話に、ミリアは「にゃあ」と相槌を打った。
外に出る機会は、徐々に増えた。
ミリアの代役を免れたダリアは、これ幸いとばかりにミリアの寝台でいつも気持ちよさそうに寝ていた。寝ている時間が長くなってきたように感じたが、「年をとった猫はそういうものですよ」と年重の侍女はミリアに優しく言った。
観劇。夜会。レナートの邸宅での食事会。
「にゃあ」で切り抜けられぬ場面が増えて、ミリアは「レナートの婚約者」として人間の言葉で話すことも増えた。
それでも、帰りの馬車で二人きりになったりすると、返事のいくつかは「にゃあ」となる。
レナートも慣れたもので、気にした素振りもなく穏やかに会話を楽しんでいるようだった。
季節は巡り、月日が流れた。
二十歳を迎える頃、二人の結婚式が執り行われることになった。
結婚後はレナートの邸宅で暮らすことに決まっていたが、ぎりぎりまでミリアは自宅で過ごす。
その頃、ダリアはほとんど目を覚ますことがなくなっていた。
もしかしていよいよかもしれない、とミリアがレナートに伝えると、結婚式前夜に屋敷に駆けつけたレナートは思いつめた顔で「結婚式は延期しても構わない。ダリアのそばに」と言ってミリアとともに部屋へと向かった。
白猫ダリアは、寝台の横に深刻な表情で並んで立つ二人をじっと見て「にゃあ」と鳴いて目を閉ざした。
そしてそれきり起きることはなかった。
翌日、二人は予定通りに結婚式をあげた。
* * *
サヴォイ侯爵夫妻は長く、円満な夫婦生活を送った。
猫好きで有名で、屋敷にはたくさんの猫が家族のように仲良く暮らしていたという。
大好物なのである。そこまで言われたら、ミリアも断ることができなかった。
屋敷からの外出ということで、ダリアは留守番。
はじめて、ふたりで会った。
レナートの話しぶりは、外で会っても四阿で話していたときと何程も変わらず。もう慣れ親しんだ彼との会話に、ミリアは「にゃあ」と相槌を打った。
外に出る機会は、徐々に増えた。
ミリアの代役を免れたダリアは、これ幸いとばかりにミリアの寝台でいつも気持ちよさそうに寝ていた。寝ている時間が長くなってきたように感じたが、「年をとった猫はそういうものですよ」と年重の侍女はミリアに優しく言った。
観劇。夜会。レナートの邸宅での食事会。
「にゃあ」で切り抜けられぬ場面が増えて、ミリアは「レナートの婚約者」として人間の言葉で話すことも増えた。
それでも、帰りの馬車で二人きりになったりすると、返事のいくつかは「にゃあ」となる。
レナートも慣れたもので、気にした素振りもなく穏やかに会話を楽しんでいるようだった。
季節は巡り、月日が流れた。
二十歳を迎える頃、二人の結婚式が執り行われることになった。
結婚後はレナートの邸宅で暮らすことに決まっていたが、ぎりぎりまでミリアは自宅で過ごす。
その頃、ダリアはほとんど目を覚ますことがなくなっていた。
もしかしていよいよかもしれない、とミリアがレナートに伝えると、結婚式前夜に屋敷に駆けつけたレナートは思いつめた顔で「結婚式は延期しても構わない。ダリアのそばに」と言ってミリアとともに部屋へと向かった。
白猫ダリアは、寝台の横に深刻な表情で並んで立つ二人をじっと見て「にゃあ」と鳴いて目を閉ざした。
そしてそれきり起きることはなかった。
翌日、二人は予定通りに結婚式をあげた。
* * *
サヴォイ侯爵夫妻は長く、円満な夫婦生活を送った。
猫好きで有名で、屋敷にはたくさんの猫が家族のように仲良く暮らしていたという。