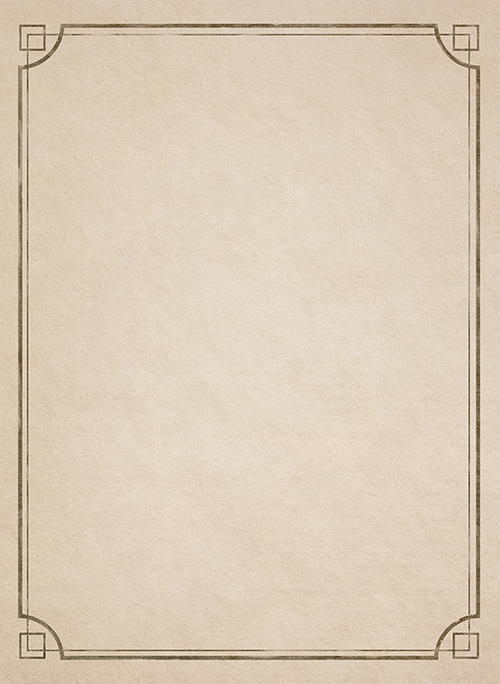僕にできるのは、ただ耐え忍ぶことだけだ。
その日からしばらくの間は、出勤のたびに緊張が全身を襲った。
一ヶ月の中で、野球部員とも、店長とも出勤の被らない日はない。授業が終わって、コンビニへ向かうべくペダルと漕ぐと、野球部員のあの陰湿な笑みと、店長の取ってつけた笑顔が僕の頭に浮かんだ。
もしも、今日また何かの加減でそれらを目にすることがあったら、と想像するだけで足は不思議と重くなっていった。だからと言って、出勤を拒否することはできない。店長に電話をしたところで、以前のような裏切り行為があるのでは無いかと疑念を抱かれる(そして実際、その疑念は的中している)。
一つ嘘をつくごとに、僕はあの場所に行きづらくなっていく。裏切りや、疑念といった全てを払拭し、元の通りに戻るためには地道な努力こそ最も適した行動だった。野球部員の存在があるので、全て元通りというわけにはいかないだろうが。
それから高校を卒業するまで、僕は居心地の悪さと懸命に戦いながらアルバイトに励んだ。
途中に何度か、辞めてしまった方が身のためなんじゃ無いかとも考えたが、結局は辞めなかった。辞めるための具体的な道筋を頭に思い浮かべると、どうしても石川梨沙の顔が浮かんでくるのだ。
頭の中で、彼女は何も言わず感じの良い笑みを浮かべてこちらを見ている。彼女という存在を思い浮かべるだけで、僕はどうしてかアルバイトを辞める決断だけができなくなっていた。
そして彼女のことが脳裏に浮かぶのは、辞めようかと迷ったタイミングだけだった。他のどの場面においても、僕は石川梨沙を忘れたように生活している。退屈な授業でまどろんでいる時にだって、浮かんではこない。
この辛い賃仕事を辞めよう。そう考えた時にだけ現れる、幻のような存在だ。ある意味では呪いの類では無いか、と僕は思った。
直接的に本人が何かをしたわけでは無いのだろうが、彼女の存在が僕をそこに留めて離さない錨の役割を担っているのは間違いがない。
どのような形でもいい。僕は彼女と決着をつけなくてはならない。
高校を卒業した僕は、家からそれほど離れていない所にある専門学校に入学した。
そこは人体の仕組みや働きについて正確で膨大な知識を身につけるための場所だった。オープンキャンパスに参加した際に聞いたのは、多くの卒業生たちが医療やスポーツの現場で活躍しているという話だった。
二年間積み上げた知識や技術は、小さなものではないというのが向こうの一番口にしたい主張であるらしかった。僕は熱弁する女性講師の話を半分感心して、半分嘲るような気持ちで聞いていた。
学校の概要を説明してから、講師は具体的にこの学校で何が身につく
その日からしばらくの間は、出勤のたびに緊張が全身を襲った。
一ヶ月の中で、野球部員とも、店長とも出勤の被らない日はない。授業が終わって、コンビニへ向かうべくペダルと漕ぐと、野球部員のあの陰湿な笑みと、店長の取ってつけた笑顔が僕の頭に浮かんだ。
もしも、今日また何かの加減でそれらを目にすることがあったら、と想像するだけで足は不思議と重くなっていった。だからと言って、出勤を拒否することはできない。店長に電話をしたところで、以前のような裏切り行為があるのでは無いかと疑念を抱かれる(そして実際、その疑念は的中している)。
一つ嘘をつくごとに、僕はあの場所に行きづらくなっていく。裏切りや、疑念といった全てを払拭し、元の通りに戻るためには地道な努力こそ最も適した行動だった。野球部員の存在があるので、全て元通りというわけにはいかないだろうが。
それから高校を卒業するまで、僕は居心地の悪さと懸命に戦いながらアルバイトに励んだ。
途中に何度か、辞めてしまった方が身のためなんじゃ無いかとも考えたが、結局は辞めなかった。辞めるための具体的な道筋を頭に思い浮かべると、どうしても石川梨沙の顔が浮かんでくるのだ。
頭の中で、彼女は何も言わず感じの良い笑みを浮かべてこちらを見ている。彼女という存在を思い浮かべるだけで、僕はどうしてかアルバイトを辞める決断だけができなくなっていた。
そして彼女のことが脳裏に浮かぶのは、辞めようかと迷ったタイミングだけだった。他のどの場面においても、僕は石川梨沙を忘れたように生活している。退屈な授業でまどろんでいる時にだって、浮かんではこない。
この辛い賃仕事を辞めよう。そう考えた時にだけ現れる、幻のような存在だ。ある意味では呪いの類では無いか、と僕は思った。
直接的に本人が何かをしたわけでは無いのだろうが、彼女の存在が僕をそこに留めて離さない錨の役割を担っているのは間違いがない。
どのような形でもいい。僕は彼女と決着をつけなくてはならない。
高校を卒業した僕は、家からそれほど離れていない所にある専門学校に入学した。
そこは人体の仕組みや働きについて正確で膨大な知識を身につけるための場所だった。オープンキャンパスに参加した際に聞いたのは、多くの卒業生たちが医療やスポーツの現場で活躍しているという話だった。
二年間積み上げた知識や技術は、小さなものではないというのが向こうの一番口にしたい主張であるらしかった。僕は熱弁する女性講師の話を半分感心して、半分嘲るような気持ちで聞いていた。
学校の概要を説明してから、講師は具体的にこの学校で何が身につく