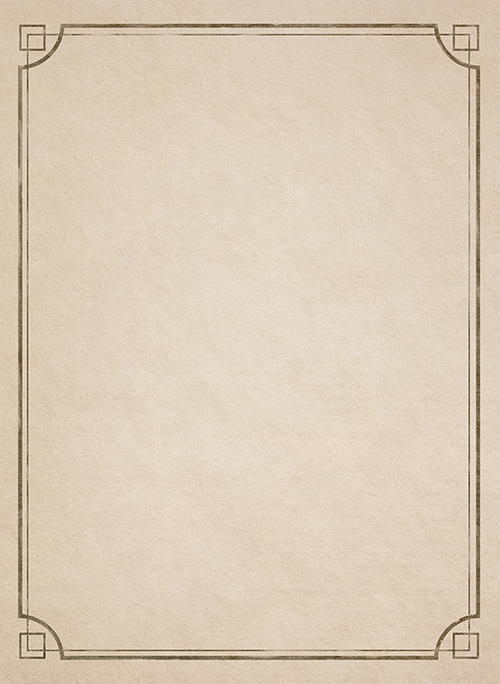告以外に聞こえるものがなくなってしまった。
最初のうち、僕は深夜ならではの業務というものを石川梨沙から教わっていた。彼女は僕と久しぶりに会ったはずなのだが、まるでつい昨日も一緒に働いたと言わんばかりの、なんでもない様子で淡々と話をした。そんな彼女の調子に合わせるように、僕の方も今まで通りの態度で彼女と接した。
一通り新たな業務について聞き終わった後に、石川梨沙はトイレ掃除に向かった。僕は店内の商品整理や、清算業務を任された。そこからしばらく、お互いに口はきかなかった。
店の中には、僕と石川梨沙の他には誰もいなかった。新たに入店してくる客はいないし、それどころか駐車場には車も停まっていない。厳密にいえば一台だけ駐車してあったが、おそらく石川梨沙の車なのだろうと僕は推察した。
淡々と業務をこなすのは、僕にとって苦痛を伴うものではなかった。むしろ深夜勤がこれほどまでに静かな環境で働けるものだと知れて、嬉しいくらいだった。
だが、石川梨沙の存在が僕の胸中にほんのわずかな居心地の悪さを感じさせていた。
久しぶりに会ったはいいものの、彼女はまるで記憶の一部を消されてしまったかのような態度を取る。直前まで僕が予想していたのは、これまでのように質問攻めを行う彼女の姿だ。現実との大きな乖離のせいで、ここにいる石川梨沙が実は偽物で、誰かが変装した姿なのではないかとすら勘繰ってしまう。
しかし、思い返してみれば自然なことなのかも知れない。僕にとって石川梨沙とは、ある意味においては特別な人間だ。あの店長の下で働き続けるのが良いことなのか悪いことなのかは別として、彼女のような存在があったからこそ、僕はここに残っているのは疑いようも無い事実だ。一方で、石川梨沙にとって、いや、石川梨沙の人生の中で、僕と言う一個人はどの程度の存在感を放っていただろうか。これまでの人生を彼女自身がなぞっていった時、特筆すべき項目として僕の名前が挙がるだろうか。
業務をこなしつつ冷静になってその可能性について思考したが、考えるほどに現実味を帯びていないものであるという結論が強固なものとなっていった。
石川梨沙にとって、僕はこれまでに出会ってきた数多い人物のうちの一人でしかないのだ。一年ぶりに再会したからと言って、わざわざ騒ぎ立てるほどのものではない。本来なら、僕も彼女と言う人間についてそのように考えるべきなのだ。
トロッコのレールを切り替えるようにして、僕は考えを切り替えた。
やがてするべき作業も順調に進行し、後は時間が来るのを待つだけと言う状態になりつつあった。石川梨沙の提案で、僕たち二人はバックヤードに移り、休憩することにした。店内の様子は監視カメラで確認で
最初のうち、僕は深夜ならではの業務というものを石川梨沙から教わっていた。彼女は僕と久しぶりに会ったはずなのだが、まるでつい昨日も一緒に働いたと言わんばかりの、なんでもない様子で淡々と話をした。そんな彼女の調子に合わせるように、僕の方も今まで通りの態度で彼女と接した。
一通り新たな業務について聞き終わった後に、石川梨沙はトイレ掃除に向かった。僕は店内の商品整理や、清算業務を任された。そこからしばらく、お互いに口はきかなかった。
店の中には、僕と石川梨沙の他には誰もいなかった。新たに入店してくる客はいないし、それどころか駐車場には車も停まっていない。厳密にいえば一台だけ駐車してあったが、おそらく石川梨沙の車なのだろうと僕は推察した。
淡々と業務をこなすのは、僕にとって苦痛を伴うものではなかった。むしろ深夜勤がこれほどまでに静かな環境で働けるものだと知れて、嬉しいくらいだった。
だが、石川梨沙の存在が僕の胸中にほんのわずかな居心地の悪さを感じさせていた。
久しぶりに会ったはいいものの、彼女はまるで記憶の一部を消されてしまったかのような態度を取る。直前まで僕が予想していたのは、これまでのように質問攻めを行う彼女の姿だ。現実との大きな乖離のせいで、ここにいる石川梨沙が実は偽物で、誰かが変装した姿なのではないかとすら勘繰ってしまう。
しかし、思い返してみれば自然なことなのかも知れない。僕にとって石川梨沙とは、ある意味においては特別な人間だ。あの店長の下で働き続けるのが良いことなのか悪いことなのかは別として、彼女のような存在があったからこそ、僕はここに残っているのは疑いようも無い事実だ。一方で、石川梨沙にとって、いや、石川梨沙の人生の中で、僕と言う一個人はどの程度の存在感を放っていただろうか。これまでの人生を彼女自身がなぞっていった時、特筆すべき項目として僕の名前が挙がるだろうか。
業務をこなしつつ冷静になってその可能性について思考したが、考えるほどに現実味を帯びていないものであるという結論が強固なものとなっていった。
石川梨沙にとって、僕はこれまでに出会ってきた数多い人物のうちの一人でしかないのだ。一年ぶりに再会したからと言って、わざわざ騒ぎ立てるほどのものではない。本来なら、僕も彼女と言う人間についてそのように考えるべきなのだ。
トロッコのレールを切り替えるようにして、僕は考えを切り替えた。
やがてするべき作業も順調に進行し、後は時間が来るのを待つだけと言う状態になりつつあった。石川梨沙の提案で、僕たち二人はバックヤードに移り、休憩することにした。店内の様子は監視カメラで確認で