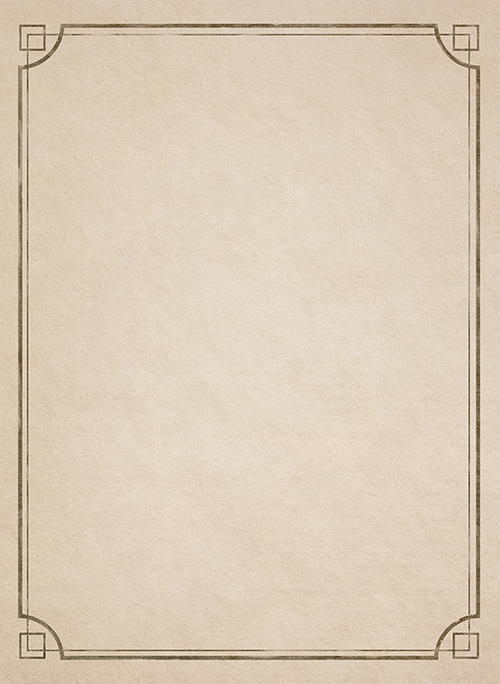「徳田くんと今日一緒なのは、石川くんだね」
僕は思わず耳を疑った。そして確かめるように店長に尋ねた。
「石川さんって、石川梨沙さんですか?」
「そうだよ。うちに石川さんは、他にいないだろ?」
「でも石川さんのシフトって、もっと遅い時間からのはずでしたよね。また変わったんですか?」
「実は、少し前にあいつから相談されてたんだ。シフト変更の話、あれ、もう一度変えることはできますかってね。家庭の事情で、もう少し早い時間からにしたいんだって言われたんだよ。できることなら彼女には、あのままの時間帯でお願いしたかったんだけどね? 家庭の事情と言われたら仕方ない。それに、あの石川くんが詳しいことは話せないって言うんだ。珍しいだろ、清廉潔白で、嘘ひとつついたことのないあの石川くんが、口をつぐんでしまうなんてよっぽどだ。経営者の俺としては辛い決断だったが、なんとか受け入れたよ。その石川くんの代わりに、前田くんが明け方まで働くことになったんだ。前田くんは何か文句を言っていたが、元々あいつのことは好かん。俺としてはこれでほぼ顔を見なくて済むし、それを考えると嬉しいくらいだな」
店長は大きな声をあげ、豪快に笑って見せた。下品な笑い声は、僕の頭の中に山賊のイメージ像を思い起こさせた。そんな店長の笑い声が止むのと同時に、バックヤードの扉が開かれる音がした。このタイミングで入ってくるのは、今からタイムカードを切って働く人物以外に居ない。
はっとして扉の方を見やると、石川梨沙の姿があった。
店長は僕の時より幾分高い声を発して彼女を迎えた。待っていました、と言わんばかりの喜びようだった。
「店長さん、笑い声が大きすぎて外まで聞こえてましたよ」
にこやかに笑って、彼女は言った。
店長は薄気味悪く笑って謝った。
僕と石川梨沙の二人が出勤し、高校生やパートの主婦たちから業務の引き継ぎを終えて交代すると、店長も仕事を終えて帰っていった。
帰る直前、店長は客のいないタイミングを見計らって帰宅する旨を伝えた。そして長い間働き続けてくれている僕と石川梨沙の二人になら、安心して仕事を任せられると言った。話の最中、僕はどちらかといえば石川梨沙の方を向いて話す店長がやはり気にかかった。彼だけではない。ここにいる人間はおおかた、石川梨沙を気にいる傾向がある。気に入るあまり、僕という存在を軽く見ているのではないかとすら思えてくる。石川梨沙が頼りにされ、存在感を増すたびに、僕の気配や影みたいなものが少しずつ失われているようだった。
バックヤードで談笑していた高校生たちが一人ずつ消え、ついに最後の一人も帰ってしまうと、店の中にはスピーカーから鳴らされている広
僕は思わず耳を疑った。そして確かめるように店長に尋ねた。
「石川さんって、石川梨沙さんですか?」
「そうだよ。うちに石川さんは、他にいないだろ?」
「でも石川さんのシフトって、もっと遅い時間からのはずでしたよね。また変わったんですか?」
「実は、少し前にあいつから相談されてたんだ。シフト変更の話、あれ、もう一度変えることはできますかってね。家庭の事情で、もう少し早い時間からにしたいんだって言われたんだよ。できることなら彼女には、あのままの時間帯でお願いしたかったんだけどね? 家庭の事情と言われたら仕方ない。それに、あの石川くんが詳しいことは話せないって言うんだ。珍しいだろ、清廉潔白で、嘘ひとつついたことのないあの石川くんが、口をつぐんでしまうなんてよっぽどだ。経営者の俺としては辛い決断だったが、なんとか受け入れたよ。その石川くんの代わりに、前田くんが明け方まで働くことになったんだ。前田くんは何か文句を言っていたが、元々あいつのことは好かん。俺としてはこれでほぼ顔を見なくて済むし、それを考えると嬉しいくらいだな」
店長は大きな声をあげ、豪快に笑って見せた。下品な笑い声は、僕の頭の中に山賊のイメージ像を思い起こさせた。そんな店長の笑い声が止むのと同時に、バックヤードの扉が開かれる音がした。このタイミングで入ってくるのは、今からタイムカードを切って働く人物以外に居ない。
はっとして扉の方を見やると、石川梨沙の姿があった。
店長は僕の時より幾分高い声を発して彼女を迎えた。待っていました、と言わんばかりの喜びようだった。
「店長さん、笑い声が大きすぎて外まで聞こえてましたよ」
にこやかに笑って、彼女は言った。
店長は薄気味悪く笑って謝った。
僕と石川梨沙の二人が出勤し、高校生やパートの主婦たちから業務の引き継ぎを終えて交代すると、店長も仕事を終えて帰っていった。
帰る直前、店長は客のいないタイミングを見計らって帰宅する旨を伝えた。そして長い間働き続けてくれている僕と石川梨沙の二人になら、安心して仕事を任せられると言った。話の最中、僕はどちらかといえば石川梨沙の方を向いて話す店長がやはり気にかかった。彼だけではない。ここにいる人間はおおかた、石川梨沙を気にいる傾向がある。気に入るあまり、僕という存在を軽く見ているのではないかとすら思えてくる。石川梨沙が頼りにされ、存在感を増すたびに、僕の気配や影みたいなものが少しずつ失われているようだった。
バックヤードで談笑していた高校生たちが一人ずつ消え、ついに最後の一人も帰ってしまうと、店の中にはスピーカーから鳴らされている広