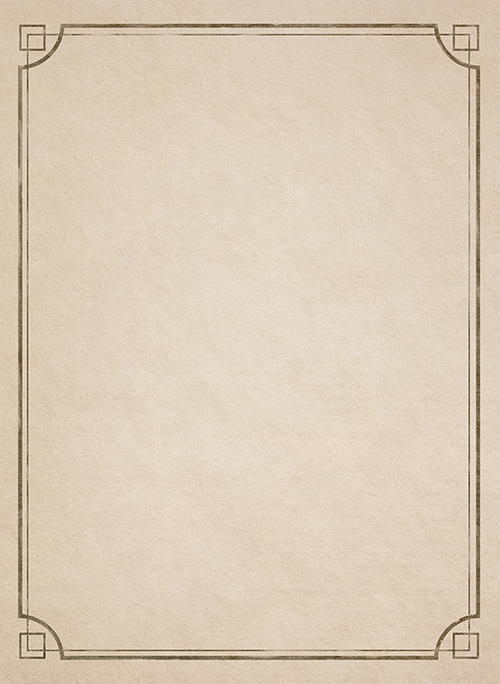くことになったわけだが、必要書類を提出した翌日の出勤で店長に呼び止められた。
「徳田くん。進路の方はどうなっているの?」
タイムカードを切って店内へ向かおうとしていた所だった。店長は寝不足なのか、目の下に大きなクマができていた。風邪気味なのだろう、口元に白いマスクも付けている。端から見ていてそれは、どうにも弱った獣を連想させた。こんな状態で森に入れば、狩人たちの手であっという間に仕留められてしまうかもしれない。
「専門学校に入学することにしました。そのための書類も、昨日提出をしてきました」
店長は「そうか、そうか」などと言って頷いた。安心したようにも見えるし、獲物が罠にかかった時のような、安堵の表情にも見えた。
「それで、ここでのアルバイトは続けるのかな」
店長がそう訊いた。顔は相変わらず具合が悪そうだったが、その内側には何か、悪意でできた良くない類のものが含まれているように感じ取れた。
高校卒業を控えたこの時期になって、僕は店長の存在を鬱陶しくは思うものの、わかりやすく脅威と見做して恐れたりはしなくなっていた。ある程度意見を言えるようになったし、店長もまた僕の意見に耳を貸すようになっていた。
一時は野球部員の密告のせいで立場が危うくなったものの、落としかけた信頼をどうにか元の位置まで戻せたというわけだ。三年という月日は、やはり伊達ではない。
そういうことなので、僕は店長にアルバイトを継続しろと脅しをかけられた場合でも拒否することができる。自分は卒業を機にきっぱりと辞めて、新生活に向かって準備をするのだと伝えることは無論、可能だった。
だが僕は、店長からの問いに対し、首を縦に振った。
「続けようと思います。ただ、学校でのスケジュールもあるので、できることなら遅い時間帯にシフトを移動したいんです。今通っている高校より、専門学校は遠いので夕方は厳しそうなんです」
僕がそう伝えると、店長は実に機嫌良さそうに笑った。声をあげて笑うと、すぐに口元に手をやって咳き込んだ。体調はあまり芳しくなさそうだった。
「もちろん、今まで通りに出勤しろとは言わないよ。徳田くんの無理のない範囲で構わない。出てくれるだけでもありがたいよ」
と、店長は言った。次に右手を差し出して、握手を求めた。右手は直前に、咳をする際に口元に当てられた手だった。マスク越しだったとはいえ、そんな手を固く握りしめたくはなかったのだが、渋々握手に応じた。
僕の方は殆ど力を込めなかったが、代わりに店長は右手に目一杯の力を込めた。
「徳田くん。進路の方はどうなっているの?」
タイムカードを切って店内へ向かおうとしていた所だった。店長は寝不足なのか、目の下に大きなクマができていた。風邪気味なのだろう、口元に白いマスクも付けている。端から見ていてそれは、どうにも弱った獣を連想させた。こんな状態で森に入れば、狩人たちの手であっという間に仕留められてしまうかもしれない。
「専門学校に入学することにしました。そのための書類も、昨日提出をしてきました」
店長は「そうか、そうか」などと言って頷いた。安心したようにも見えるし、獲物が罠にかかった時のような、安堵の表情にも見えた。
「それで、ここでのアルバイトは続けるのかな」
店長がそう訊いた。顔は相変わらず具合が悪そうだったが、その内側には何か、悪意でできた良くない類のものが含まれているように感じ取れた。
高校卒業を控えたこの時期になって、僕は店長の存在を鬱陶しくは思うものの、わかりやすく脅威と見做して恐れたりはしなくなっていた。ある程度意見を言えるようになったし、店長もまた僕の意見に耳を貸すようになっていた。
一時は野球部員の密告のせいで立場が危うくなったものの、落としかけた信頼をどうにか元の位置まで戻せたというわけだ。三年という月日は、やはり伊達ではない。
そういうことなので、僕は店長にアルバイトを継続しろと脅しをかけられた場合でも拒否することができる。自分は卒業を機にきっぱりと辞めて、新生活に向かって準備をするのだと伝えることは無論、可能だった。
だが僕は、店長からの問いに対し、首を縦に振った。
「続けようと思います。ただ、学校でのスケジュールもあるので、できることなら遅い時間帯にシフトを移動したいんです。今通っている高校より、専門学校は遠いので夕方は厳しそうなんです」
僕がそう伝えると、店長は実に機嫌良さそうに笑った。声をあげて笑うと、すぐに口元に手をやって咳き込んだ。体調はあまり芳しくなさそうだった。
「もちろん、今まで通りに出勤しろとは言わないよ。徳田くんの無理のない範囲で構わない。出てくれるだけでもありがたいよ」
と、店長は言った。次に右手を差し出して、握手を求めた。右手は直前に、咳をする際に口元に当てられた手だった。マスク越しだったとはいえ、そんな手を固く握りしめたくはなかったのだが、渋々握手に応じた。
僕の方は殆ど力を込めなかったが、代わりに店長は右手に目一杯の力を込めた。