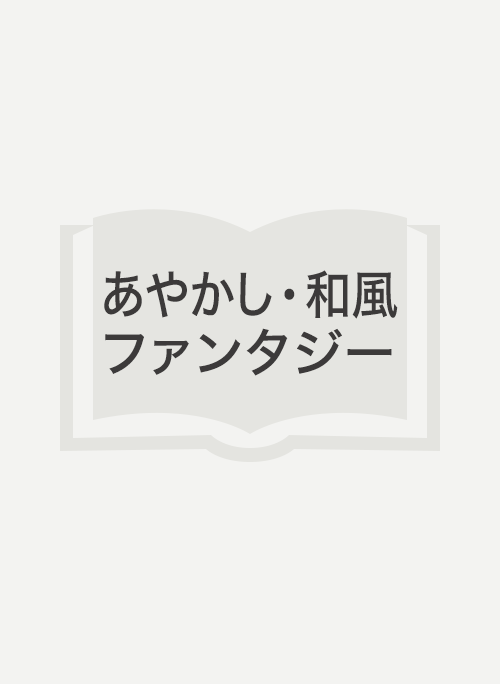あんみつを堪能したあと、甘味処を営む夫婦に挨拶をして店を出た。
灯璃の案内のもと様々な店に行き、彼がどのようなものが好きなのか少しだけ知れたような気がする。
学生の頃に立ち寄っていた書店に今の時季に美しく咲き誇る花畑など、すべてが初めてで千冬は胸が弾んだ。
夕日に照らされ地面に伸びる影を見て町を見始めてから、かなりの時間が経過したことに気がつく。
「もうこんな時間か。日が暮れる前にそろそろ帰るか」
「はい」
灯璃が運転手に念話を送り、自動車が来るまで道の端で待つ。
少し冷たい風が頬を撫でる。
「寒くはないか」
「平気です。鬼城さまは……?」
「ありがとう、私も大丈夫だ。……千冬」
「はい」
ふと名前を呼ばれて返事をすると灯璃は千冬の小さな手をそっと握った。
急に伝わる体温に胸が高鳴り、戸惑いで瞳が揺れる。
恥ずかしさで視線を逸らしそうになるが真剣な眼差しがそれを許さなかった。
「私のことを鬼城ではなく、灯璃と呼んでくれないか」
「そ、それはできません」
「どうしてだ?」
即答で断った千冬だが灯璃もすかさず理由を問う。
返事を求められて急いで頭の中で適切な言葉を探しながら声にして伝える。
「鬼城さまとわたしでは立場が違いすぎます。下のお名前で呼ぶなど恐れ多いです」
首を横に振り、若干早口になる千冬。
花嫁として鬼城家に迎え入れられて数日が経過しているのに、まだ自分を卑下していた。
決して控えめな性格が駄目ということではない。
ただ、どこか感情を押し殺すような表情に卑下することで自分自身を傷つけているような言葉に灯璃は胸が苦しくなった。
千冬がそのようになったのは嶺木家の人間たちが原因。
それはすでに知っているが買い物に連れて行くだけで、そう簡単には心に負った深い傷は癒やせない。
(千冬を苦しめるすべてから解き放したい)
物理的に嶺木家の屋敷から離れたといって、つらい記憶は忘れることはできない。
(傷ついた分、いやそれ以上に千冬に愛をそそいで幸せにする)
灯璃は膝を軽く折り曲げ、どこか憂いに満ちた千冬の瞳を覗き込んだ。
「私たちの間に立場など関係ない。上や下ではなく、対等の存在でいたいんだ」
「でも……」
灯璃は手を伸ばし千冬の白い頬に触れた。
夕方の冷たい風のせいか、ひんやりとした体温が手のひらに伝わる。
「怖がる必要は何もない。その愛らしい声で唇で私の名を呼んでくれないか」
千冬の瞳が大きく揺れ、閉じていた唇がそっと開く。
「……ま」
「ん?」
ほとんど声は消えて、最後の一文字がようやく聞こえる。
口をぱくぱくとさせている千冬が愛らしく見えて灯璃は微笑みながら自分の耳を彼女の唇に近づけた。
もう一度言わないといけないのかと、うっと声が聞こえたが、うずうずと目の前で待ち構えている灯璃を見て観念したように口を開いた。
「と、灯璃さま……」
林檎のように赤く染まった頬に潤んだ瞳がとても愛らしく理性を保つのに必死だった。
先ほどよりも僅かに大きな声で発せられた名前は確かに灯璃の耳に届く。
喜びがじんわりと胸に広がった。
「ありがとう、千冬」
灯璃は優しく壊れ物を扱うように千冬を抱きしめた。
「あ、の……。今は外ですし、他の方もいらっしゃいますから……」
顔を上げ上目遣いで訴える姿は灯璃の中で抑えている欲を倍増させるだけだ。
「屋敷だったら良いのか?」
「ち、違いますっ!」
珍しく大きな声で否定をし、むくれている。
千冬が頬を膨らましているのに初めて見る一面に嬉しくなった。
それを言えばさらに怒るだろうが。
「すまない、すまない」
腕から解放し謝りながら申し訳なかったという意味を込めて頭を撫でる。
普段は冷静沈着な灯璃がご機嫌をとるようにしている状況に可笑しくなってきたのか千冬は思わず小さく吹き出した。
「……ふふっ」
寒さを感じ始める夕方。
空は少しずつ夕闇に包まれていき、行き交う人々は家路を急いでいるのか誰もが足早だ。
二人は迎えの自動車がつくまでの何でもない時間がとても愛おしく感じたのだった。
一方その頃。
帝都に構える嶺木家の屋敷の門前に一台の自動車が止まった。
運転手が扉を開け、降りてきたのは黒と赤の着物を身に纏った薫子だった。
少し先には、数分前に帰宅し玄関に向かって歩いている依鈴の背中が見える。
すでに嶺木家については調査済み。
千冬以外にも当主とその妻、妹まで細かく頭に入っている。
「ごめんください」
凛とした美しき声に依鈴は、聞こえた方角へり返ると薫子に気がついた。
散っていく桜の花びらが辺りを舞い、薫子の天女のように美しさが際だっていた。
「……どちらさまでしょう?」
放たれる神秘的な雰囲気に圧倒されて魅入ってしまっていたことに気がつき、若干警戒をしながら口を開く。
あの男と同じ瞳の色だと勘づいたときには薫子のぷるんとした唇から放たれる言葉が先だった。
「突然のご訪問お許しください。私、鬼の一族の鬼川薫子と申します」
「……どうしてそのような方が我が屋敷に?もしかして貴方さまも鬼城さまと何か企んでいらっしゃるの?」
薫子は依鈴の返事の内容については想定内だった。
小さく口角を上げると距離を一歩縮める。
依鈴は一部の女子から女帝と言われるほど堂々とした立ち居振る舞いだが薫子を目の前にして思わず後ろに下がりそうになる。
しかし自分が帝都で名高い嶺木家の人間であることが誇りの依鈴はその場から逃げようとはしなかった。
「やはり灯璃さまも来られていたのですね。噂通り、人間の花嫁にはとことん甘いのですから」
「何がいいたいのですか?」
人間より位の高いあやかし。
そのあやかしの中でも最高位に君臨する鬼に対しては敬うべきだが、薫子のはっきりしない遠回しな話し方に苛つきが募る。
これが鬼ではなく身分が低い者ならば敬語など使わず身の程をわきまえろと一刀両断していただろう。
千冬を虐げてきた依鈴が敬語で話す相手など同世代でそうはいない。
「これは申し訳ありません。私達の仲が悪くなる前に単刀直入に伝えた方がよろしいようですわね」
「私達の仲……?」
薫子とは今しがた出逢ったばかりなのに、なぜ以前から親交があるような言い方なのか依鈴にはわからなかった。
「話は他でもありません。貴方さまの姉、千冬さまの件です」
「お姉さまが鬼城さまの花嫁に選ばれたことは知っていますよ」
本当は自分より下だと見下していた姉が財力、権力などすべてをもっている灯璃の花嫁に選ばれたことは認めたくないが紛れもない事実。
いちいちそんなことを薫子は伝えにきたのかと呆れてしまいそうになる。
「話はそれで以上ですか?私も忙しいのでこれで失礼いたし……」
「私は鬼城灯璃の元婚約者です」
凛とした大きな声が依鈴の耳にはっきりと届く。
要領、器量が良い依鈴はその言葉だけで薫子が何を言いたいのかおおよそわかった。
元は鬼城灯璃と鬼川薫子は婚約していた仲。
しかしそこに千冬が現れて、その婚約は破棄になったのだ。
自分の身に起きた状況にそっくりで信じがたい。
依鈴も数年前に両親から時田清二を紹介されて女学校を卒業したら結婚をするという約束だった。
見た目や財力に問題はなく、政略結婚にしては特に不自由はなかったのだが。
忘れもしないあの日。
ご機嫌に買い物を済ませて帰ると清二の父親から連絡がきて白紙にさせてもらうと怒号と共に一言。
夢見ていた優雅な結婚生活も隠していた千冬の瞳を清二に見られて、あっという間に散っていった。
明日からその命が消え去る寸前まで徹底的に虐めるつもりだったのに千冬は屋敷から突如としていなくなり、どこかで死んだかと思えば鬼と出逢って花嫁になったのだ。
祟り神と同じ紫紺色の瞳をもつ姉など不幸になると嶺木家に来た灯璃に伝えたかったのに彼は聞く耳をもたなかった。
しかもどこから情報を手に入れたのか家族が千冬を虐めていたことまで知っていた。
何かの間違いだと誰もが二人を比べれば依鈴を嫁にほしいというはず。
そんな自信も灯璃の前にしては絶望に変わった。
自分に甘い父親に鬼城家には私が嫁がせてと頼み込んだが、首を縦に振ることはなかった。
しかもこれ以上目立つとこの家の存続に関わるから大人しくしていなさいと叱られてしまった。
時田家から広まったのか依鈴の妹が紫紺色の瞳をもっているという噂が女学校でも広まりつつある。
嶺木家の娘である依鈴にごまをすっていた学友も一人、また一人と離れていくのが日に日に増えていった。
千冬に謝罪をすれば嶺木家の没落は免れるがそんなこと依鈴の自尊心が許さない。
両親も判断を決めかねているためどうしたらと考えていたところに今の薫子の言葉だ。
「それでは鬼川さまもお姉さまを恨んでいるのね?」
「ええ。それはもう彼女の存在をなかったものとしたいくらいに。貴方さまもそれは同じでしょう?」
「どうしてそれを?」
「鬼川家の従者によれば嶺木家の内情を調べるのは容易いことですわ」
いつの間にか家について調べられていたことは不快に感じるが、それもどうでもよくなるほど目の前に藁にもすがるような思いにさせる光がある。
「私は灯璃さまとの結婚を、貴方さまは幸せを手に入れる姉への恨みがある。どうでしょう?利害が一致するのならば私達、手を組むというのは」
頭の良い依鈴はすぐにわかる。
嶺木家と鬼川家の力を合わせれば強大なものとなり千冬を花嫁の座から引きずり下ろすことができる可能性があると。
「もちろん、私からお願いをしているのですから貴方さまにもさらに利益をもたらしましょう。……例えば鬼の一族のみが集まるパーティーに特別に招待しましょう。貴方さまが花嫁に選ばれる確率が高くなりますよ。鬼川家の圧力をかければある程度は可能ですわ」
鬼の中で三番目の地位に立つ鬼川家の娘ならば他の家の者など力で抑えることも容易だろう。
千冬を嶺木家へ戻し、自分は鬼の一族の男性と結婚なんて依鈴にとってこんな良い話は他にない。
「一体私は何をすれば良いの?」
「話が早くて助かりますわ。私に良い案があります」
「……中へどうぞ」
依鈴は詳細を聞くため薫子を屋敷の中へ招き入れたのだった。
冷たく吹く風が不気味な音を鳴らしながらこれから起こる最悪の事態を予知しているようにも聞こえた。
灯璃の案内のもと様々な店に行き、彼がどのようなものが好きなのか少しだけ知れたような気がする。
学生の頃に立ち寄っていた書店に今の時季に美しく咲き誇る花畑など、すべてが初めてで千冬は胸が弾んだ。
夕日に照らされ地面に伸びる影を見て町を見始めてから、かなりの時間が経過したことに気がつく。
「もうこんな時間か。日が暮れる前にそろそろ帰るか」
「はい」
灯璃が運転手に念話を送り、自動車が来るまで道の端で待つ。
少し冷たい風が頬を撫でる。
「寒くはないか」
「平気です。鬼城さまは……?」
「ありがとう、私も大丈夫だ。……千冬」
「はい」
ふと名前を呼ばれて返事をすると灯璃は千冬の小さな手をそっと握った。
急に伝わる体温に胸が高鳴り、戸惑いで瞳が揺れる。
恥ずかしさで視線を逸らしそうになるが真剣な眼差しがそれを許さなかった。
「私のことを鬼城ではなく、灯璃と呼んでくれないか」
「そ、それはできません」
「どうしてだ?」
即答で断った千冬だが灯璃もすかさず理由を問う。
返事を求められて急いで頭の中で適切な言葉を探しながら声にして伝える。
「鬼城さまとわたしでは立場が違いすぎます。下のお名前で呼ぶなど恐れ多いです」
首を横に振り、若干早口になる千冬。
花嫁として鬼城家に迎え入れられて数日が経過しているのに、まだ自分を卑下していた。
決して控えめな性格が駄目ということではない。
ただ、どこか感情を押し殺すような表情に卑下することで自分自身を傷つけているような言葉に灯璃は胸が苦しくなった。
千冬がそのようになったのは嶺木家の人間たちが原因。
それはすでに知っているが買い物に連れて行くだけで、そう簡単には心に負った深い傷は癒やせない。
(千冬を苦しめるすべてから解き放したい)
物理的に嶺木家の屋敷から離れたといって、つらい記憶は忘れることはできない。
(傷ついた分、いやそれ以上に千冬に愛をそそいで幸せにする)
灯璃は膝を軽く折り曲げ、どこか憂いに満ちた千冬の瞳を覗き込んだ。
「私たちの間に立場など関係ない。上や下ではなく、対等の存在でいたいんだ」
「でも……」
灯璃は手を伸ばし千冬の白い頬に触れた。
夕方の冷たい風のせいか、ひんやりとした体温が手のひらに伝わる。
「怖がる必要は何もない。その愛らしい声で唇で私の名を呼んでくれないか」
千冬の瞳が大きく揺れ、閉じていた唇がそっと開く。
「……ま」
「ん?」
ほとんど声は消えて、最後の一文字がようやく聞こえる。
口をぱくぱくとさせている千冬が愛らしく見えて灯璃は微笑みながら自分の耳を彼女の唇に近づけた。
もう一度言わないといけないのかと、うっと声が聞こえたが、うずうずと目の前で待ち構えている灯璃を見て観念したように口を開いた。
「と、灯璃さま……」
林檎のように赤く染まった頬に潤んだ瞳がとても愛らしく理性を保つのに必死だった。
先ほどよりも僅かに大きな声で発せられた名前は確かに灯璃の耳に届く。
喜びがじんわりと胸に広がった。
「ありがとう、千冬」
灯璃は優しく壊れ物を扱うように千冬を抱きしめた。
「あ、の……。今は外ですし、他の方もいらっしゃいますから……」
顔を上げ上目遣いで訴える姿は灯璃の中で抑えている欲を倍増させるだけだ。
「屋敷だったら良いのか?」
「ち、違いますっ!」
珍しく大きな声で否定をし、むくれている。
千冬が頬を膨らましているのに初めて見る一面に嬉しくなった。
それを言えばさらに怒るだろうが。
「すまない、すまない」
腕から解放し謝りながら申し訳なかったという意味を込めて頭を撫でる。
普段は冷静沈着な灯璃がご機嫌をとるようにしている状況に可笑しくなってきたのか千冬は思わず小さく吹き出した。
「……ふふっ」
寒さを感じ始める夕方。
空は少しずつ夕闇に包まれていき、行き交う人々は家路を急いでいるのか誰もが足早だ。
二人は迎えの自動車がつくまでの何でもない時間がとても愛おしく感じたのだった。
一方その頃。
帝都に構える嶺木家の屋敷の門前に一台の自動車が止まった。
運転手が扉を開け、降りてきたのは黒と赤の着物を身に纏った薫子だった。
少し先には、数分前に帰宅し玄関に向かって歩いている依鈴の背中が見える。
すでに嶺木家については調査済み。
千冬以外にも当主とその妻、妹まで細かく頭に入っている。
「ごめんください」
凛とした美しき声に依鈴は、聞こえた方角へり返ると薫子に気がついた。
散っていく桜の花びらが辺りを舞い、薫子の天女のように美しさが際だっていた。
「……どちらさまでしょう?」
放たれる神秘的な雰囲気に圧倒されて魅入ってしまっていたことに気がつき、若干警戒をしながら口を開く。
あの男と同じ瞳の色だと勘づいたときには薫子のぷるんとした唇から放たれる言葉が先だった。
「突然のご訪問お許しください。私、鬼の一族の鬼川薫子と申します」
「……どうしてそのような方が我が屋敷に?もしかして貴方さまも鬼城さまと何か企んでいらっしゃるの?」
薫子は依鈴の返事の内容については想定内だった。
小さく口角を上げると距離を一歩縮める。
依鈴は一部の女子から女帝と言われるほど堂々とした立ち居振る舞いだが薫子を目の前にして思わず後ろに下がりそうになる。
しかし自分が帝都で名高い嶺木家の人間であることが誇りの依鈴はその場から逃げようとはしなかった。
「やはり灯璃さまも来られていたのですね。噂通り、人間の花嫁にはとことん甘いのですから」
「何がいいたいのですか?」
人間より位の高いあやかし。
そのあやかしの中でも最高位に君臨する鬼に対しては敬うべきだが、薫子のはっきりしない遠回しな話し方に苛つきが募る。
これが鬼ではなく身分が低い者ならば敬語など使わず身の程をわきまえろと一刀両断していただろう。
千冬を虐げてきた依鈴が敬語で話す相手など同世代でそうはいない。
「これは申し訳ありません。私達の仲が悪くなる前に単刀直入に伝えた方がよろしいようですわね」
「私達の仲……?」
薫子とは今しがた出逢ったばかりなのに、なぜ以前から親交があるような言い方なのか依鈴にはわからなかった。
「話は他でもありません。貴方さまの姉、千冬さまの件です」
「お姉さまが鬼城さまの花嫁に選ばれたことは知っていますよ」
本当は自分より下だと見下していた姉が財力、権力などすべてをもっている灯璃の花嫁に選ばれたことは認めたくないが紛れもない事実。
いちいちそんなことを薫子は伝えにきたのかと呆れてしまいそうになる。
「話はそれで以上ですか?私も忙しいのでこれで失礼いたし……」
「私は鬼城灯璃の元婚約者です」
凛とした大きな声が依鈴の耳にはっきりと届く。
要領、器量が良い依鈴はその言葉だけで薫子が何を言いたいのかおおよそわかった。
元は鬼城灯璃と鬼川薫子は婚約していた仲。
しかしそこに千冬が現れて、その婚約は破棄になったのだ。
自分の身に起きた状況にそっくりで信じがたい。
依鈴も数年前に両親から時田清二を紹介されて女学校を卒業したら結婚をするという約束だった。
見た目や財力に問題はなく、政略結婚にしては特に不自由はなかったのだが。
忘れもしないあの日。
ご機嫌に買い物を済ませて帰ると清二の父親から連絡がきて白紙にさせてもらうと怒号と共に一言。
夢見ていた優雅な結婚生活も隠していた千冬の瞳を清二に見られて、あっという間に散っていった。
明日からその命が消え去る寸前まで徹底的に虐めるつもりだったのに千冬は屋敷から突如としていなくなり、どこかで死んだかと思えば鬼と出逢って花嫁になったのだ。
祟り神と同じ紫紺色の瞳をもつ姉など不幸になると嶺木家に来た灯璃に伝えたかったのに彼は聞く耳をもたなかった。
しかもどこから情報を手に入れたのか家族が千冬を虐めていたことまで知っていた。
何かの間違いだと誰もが二人を比べれば依鈴を嫁にほしいというはず。
そんな自信も灯璃の前にしては絶望に変わった。
自分に甘い父親に鬼城家には私が嫁がせてと頼み込んだが、首を縦に振ることはなかった。
しかもこれ以上目立つとこの家の存続に関わるから大人しくしていなさいと叱られてしまった。
時田家から広まったのか依鈴の妹が紫紺色の瞳をもっているという噂が女学校でも広まりつつある。
嶺木家の娘である依鈴にごまをすっていた学友も一人、また一人と離れていくのが日に日に増えていった。
千冬に謝罪をすれば嶺木家の没落は免れるがそんなこと依鈴の自尊心が許さない。
両親も判断を決めかねているためどうしたらと考えていたところに今の薫子の言葉だ。
「それでは鬼川さまもお姉さまを恨んでいるのね?」
「ええ。それはもう彼女の存在をなかったものとしたいくらいに。貴方さまもそれは同じでしょう?」
「どうしてそれを?」
「鬼川家の従者によれば嶺木家の内情を調べるのは容易いことですわ」
いつの間にか家について調べられていたことは不快に感じるが、それもどうでもよくなるほど目の前に藁にもすがるような思いにさせる光がある。
「私は灯璃さまとの結婚を、貴方さまは幸せを手に入れる姉への恨みがある。どうでしょう?利害が一致するのならば私達、手を組むというのは」
頭の良い依鈴はすぐにわかる。
嶺木家と鬼川家の力を合わせれば強大なものとなり千冬を花嫁の座から引きずり下ろすことができる可能性があると。
「もちろん、私からお願いをしているのですから貴方さまにもさらに利益をもたらしましょう。……例えば鬼の一族のみが集まるパーティーに特別に招待しましょう。貴方さまが花嫁に選ばれる確率が高くなりますよ。鬼川家の圧力をかければある程度は可能ですわ」
鬼の中で三番目の地位に立つ鬼川家の娘ならば他の家の者など力で抑えることも容易だろう。
千冬を嶺木家へ戻し、自分は鬼の一族の男性と結婚なんて依鈴にとってこんな良い話は他にない。
「一体私は何をすれば良いの?」
「話が早くて助かりますわ。私に良い案があります」
「……中へどうぞ」
依鈴は詳細を聞くため薫子を屋敷の中へ招き入れたのだった。
冷たく吹く風が不気味な音を鳴らしながらこれから起こる最悪の事態を予知しているようにも聞こえた。