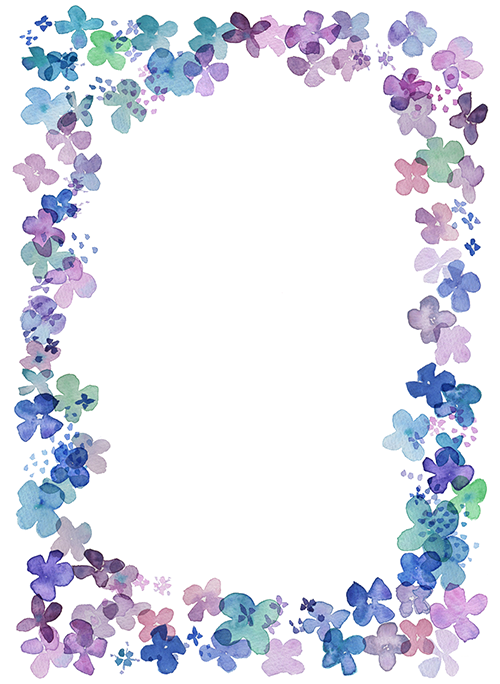1
「レオナルド様、おはようございます」
屋敷内で、視線の合うメイドたちに次々に声をかけられる。
レオナルドはこの屋敷の人間ではないのだが、俳優のような甘い顔立ちと優雅な物腰がメイドたちの心をわしづかみにしてはなさず、メイドたちの間では王子様扱いをされている。
だから、何度「やめてください」と言っても、「わたしたちには王子様です!」と言ってやめてくれない。
レオナルドは諦めてはいなかったが、悪口を言われているわけではないので、「レオナルド様」と呼ばれるたび、苦笑いで応対していた。その苦笑いすらも、メイドたちにとっては『微笑みの貴公子』などと言われていたのも知らずに。
いつも通り、メイドたちにに微笑み返したレオナルドは、本来の『様』をつけられるべき人物の部屋の前まで足を運んだ。
「シオン様。失礼いたします」
ため息ともとれるような一息をつくと、レオナルドは趣のある木製の重厚な観音扉を静かに開けた。
レオナルドは、背中まである薄茶色の髪をきちんと後ろで束ね、身なりもその立ち姿もきれいだ。そんないつもはキチッと背筋をのばしているレオナルドも、この部屋の前では前かがみにもなった。
見渡せば、大きな窓にはベルベットのように光沢のある上品な紅いカーテンが左右の金糸で編み込まれたタッセルに巻かれている。
開かれた窓からの風で、レースをふんだんに使われた白のレースカーテンがフワリと時折あおられていた。
奥にも扉があり、寝室を含め別室が二つある。レオナルドが足を踏み入れた部屋だけでも、飴色に光る高級家具が点在していて、全く圧迫感のない広くて豪華な部屋だ。
しかし、その中央には場違いとも思われるほど無機質な、ただ広いだけの作業台。そのわきには、白い布張りのトルソー。
規則正しく布を送っては縫い合わせる、ミシンの音が響いていた。
高速で動かしているため、音も通常より大きくなっているが、呼びかける声が聞こえないほどではない。
なんの反応もみせないのは、作業に没頭しているせいか邪魔をされたくないからか。またはその両方か。
ノックなら、閉された扉の前で何度も。一度に三回鳴らすものを、十セットはした。それでも返事をもらえなかった。
早急にお伝えしなければならない事柄があり、その相手は確実に部屋の中にいるとわかっている。
「レオナルド様、おはようございます」
屋敷内で、視線の合うメイドたちに次々に声をかけられる。
レオナルドはこの屋敷の人間ではないのだが、俳優のような甘い顔立ちと優雅な物腰がメイドたちの心をわしづかみにしてはなさず、メイドたちの間では王子様扱いをされている。
だから、何度「やめてください」と言っても、「わたしたちには王子様です!」と言ってやめてくれない。
レオナルドは諦めてはいなかったが、悪口を言われているわけではないので、「レオナルド様」と呼ばれるたび、苦笑いで応対していた。その苦笑いすらも、メイドたちにとっては『微笑みの貴公子』などと言われていたのも知らずに。
いつも通り、メイドたちにに微笑み返したレオナルドは、本来の『様』をつけられるべき人物の部屋の前まで足を運んだ。
「シオン様。失礼いたします」
ため息ともとれるような一息をつくと、レオナルドは趣のある木製の重厚な観音扉を静かに開けた。
レオナルドは、背中まである薄茶色の髪をきちんと後ろで束ね、身なりもその立ち姿もきれいだ。そんないつもはキチッと背筋をのばしているレオナルドも、この部屋の前では前かがみにもなった。
見渡せば、大きな窓にはベルベットのように光沢のある上品な紅いカーテンが左右の金糸で編み込まれたタッセルに巻かれている。
開かれた窓からの風で、レースをふんだんに使われた白のレースカーテンがフワリと時折あおられていた。
奥にも扉があり、寝室を含め別室が二つある。レオナルドが足を踏み入れた部屋だけでも、飴色に光る高級家具が点在していて、全く圧迫感のない広くて豪華な部屋だ。
しかし、その中央には場違いとも思われるほど無機質な、ただ広いだけの作業台。そのわきには、白い布張りのトルソー。
規則正しく布を送っては縫い合わせる、ミシンの音が響いていた。
高速で動かしているため、音も通常より大きくなっているが、呼びかける声が聞こえないほどではない。
なんの反応もみせないのは、作業に没頭しているせいか邪魔をされたくないからか。またはその両方か。
ノックなら、閉された扉の前で何度も。一度に三回鳴らすものを、十セットはした。それでも返事をもらえなかった。
早急にお伝えしなければならない事柄があり、その相手は確実に部屋の中にいるとわかっている。